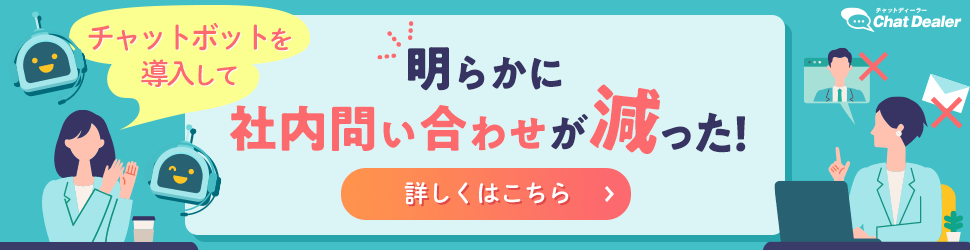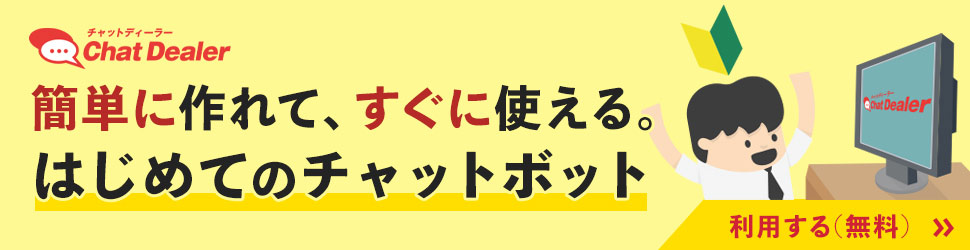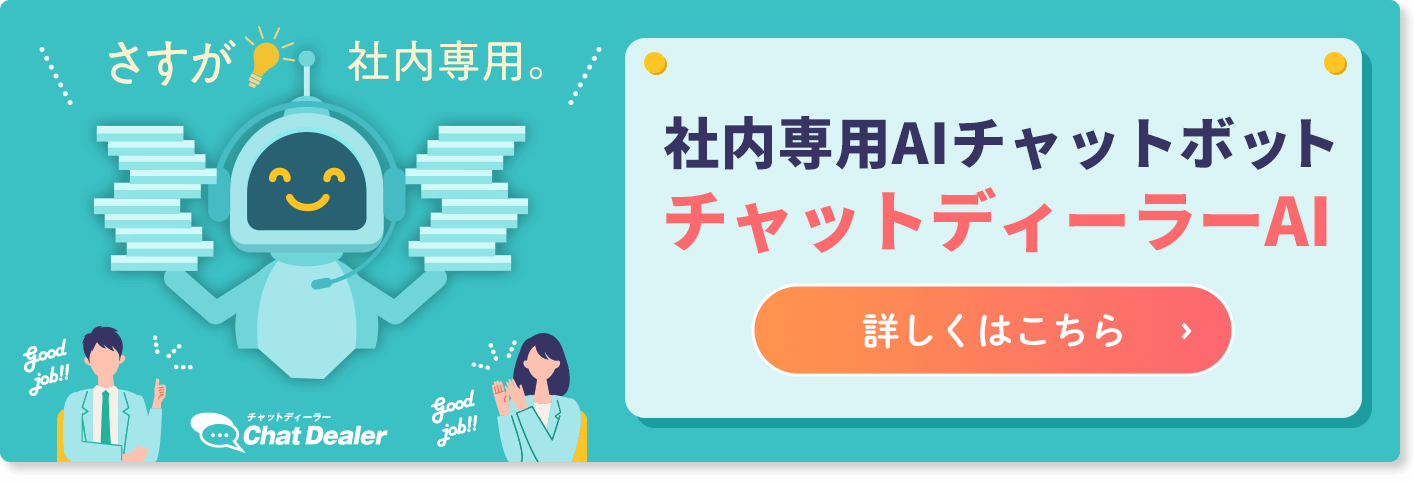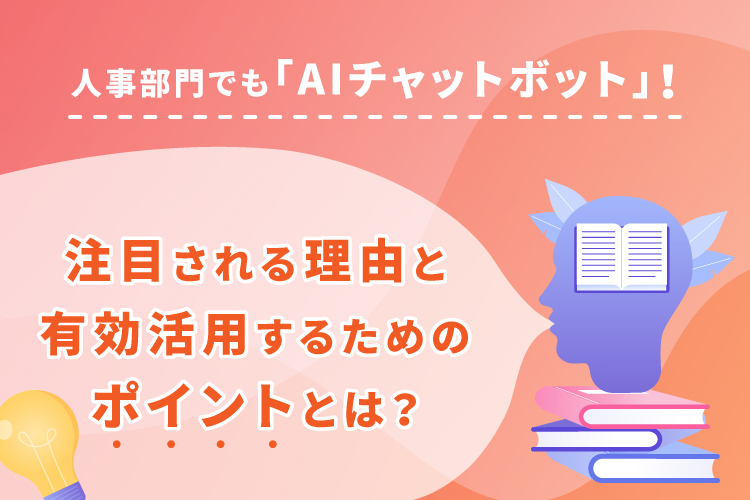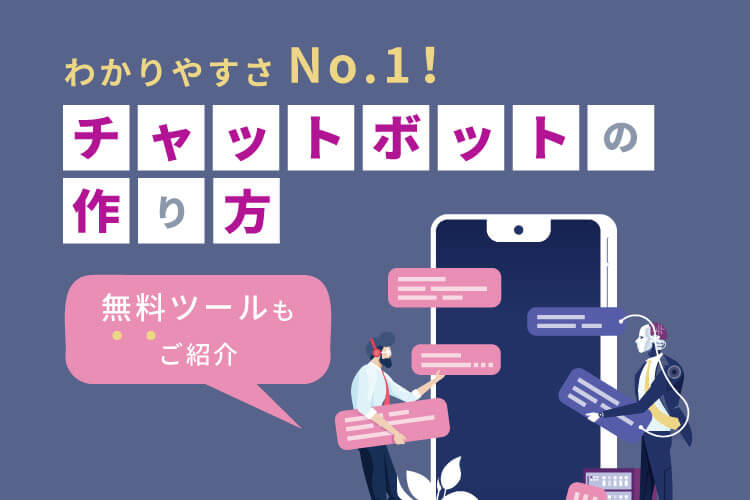【総務部門向け】AIチャットボットの導入で期待できる効果と活用方法とは?
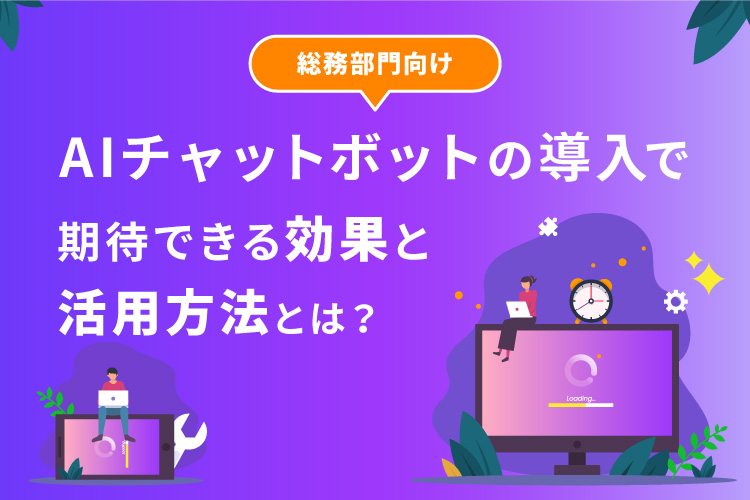
企業の事務業務や管理業務などを担う総務部門。企業によって違いはありますが、その業務は多岐にわたり、従業員からの問い合わせ対応を担当しているという場合もあるでしょう。
ただ、この問い合わせ対応に多くの時間を要しており、その他の業務を圧迫しているという課題を持つ企業は多いようです。このような状況をそのままにしておくことは、対応スピードの悪化による企業全体の生産性低下や、総務部門の負担増加による人材流出など、さまざまな懸念が考えられます。
問い合わせ対応を効率化する方法は、いくつか考えられますが、その中で効果的であるのが「AIチャットボット」の活用です。
そこで、この記事では、AIチャットボットの導入で期待できる効果から、より有効活用する方法まで詳しく解説していきます。
総務部門が行う対応業務に関して、課題をお持ちの場合は、ぜひ最後までご一読ください。
この記事にたどり着いたあなたにオススメ
総務部門におすすめなチャットボットをご紹介しています。
総務部門でもAIチャットボットの活用が広まっている?

AIチャットボットとは、AI(人工知能)を搭載した自動会話システムです。ユーザーに入力された質問に対して、チャットボットが自動で最適な回答の判断・選択を行い、ユーザーに返す仕組みとなっています。ECサイトや企業のサービスサイト内などに設置することで、問い合わせ対応業務の大幅な効率化や負担軽減が期待できることから、現在ではさまざまな業界・業種で活用されています。
端末画面のサイドにチャット画面が表示されているのを見たことがある方や、実際に使ってみたことがある方も多いのではないでしょうか。
AIチャットボットはカスタマーサポートで活用されるイメージが強くありますが、社内ヘルプデスクでも活用されています。近年では社内問い合わせ対応の効率化・負担軽減に大きく寄与することから、総務部をはじめとした社内バックオフィス業務を担う部門からも注目を集めています。
特に総務部は、問い合わせ対応が多岐に渡り、さらに同じような問い合わせが繰り返される傾向にあるため、負担が掛かりやすい部門です。
このように総務部が抱える課題解決には、チャットボットが大きな効果を発揮します。では、総務部門がAIチャットボットを導入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。次章で詳しく見ていきましょう。
総務部門でAIチャットボットを活用するメリット

先述しましたが、総務部門の業務は多岐にわたり、あくまでその中のひとつとして、従業員からの問い合わせへの対応が挙げられます。人手不足や働き方改革の影響で、一人ひとりの生産性を高めていく必要に迫られる現在、さらに総務部門の負担が増大しつつあるといえるでしょう。
また、総務部門の対応が追いつかなくなったとき、従業員の業務効率に悪影響を与えてしまう恐れもあります。
そこで、注目されているのが対応業務を一部自動化できる「AIチャットボット」です。ここでは、AIチャットボットを活用するメリットについて、総務部門側と従業員側に分けてご紹介していきます。
総務部門のメリット
問い合わせを受ける総務部門では、一部の問い合わせを自動化することで問い合わせ件数が減少し、業務負担が減少するメリットが生じます。
問い合わせ件数の削減
総務部門に寄せられる問い合わせは、異動や休暇取得に伴う申請、旅費精算などの手続き関連から、社内システムの取り扱いまで多岐に渡ります。
そのほとんどは、マニュアルやFAQに記載されていることが多いですが、情報量が膨大で見つけにくく、従業員は「聞いたほうが早い」と判断して総務部門に問い合わせるケースが多いといえます。
対しAIチャットボットは、会話形式で回答にたどり着くことができるため、FAQやマニュアルを比較して、高い利用率・解決率が期待できるでしょう。
本来なら、マニュアルやFAQを確認すれば、解決できるような簡単な問い合わせへの対応を自動化できることで、問い合わせ件数の削減を図ることができるのです。
総務部門の業務負担軽減
問い合わせ件数の削減が実現できれば、総務部門の大幅な負担軽減が期待できるでしょう。
簡単な問い合わせへの対応はAIチャットボットに任せ、複雑な内容に特化して対応を行うことで、他の業務に集中して取り組めるようになりますし、「またこの質問か」「マニュアルを読めば分かるのに」というような、心理的ストレスの軽減にもつながります。
総務部門の担当者が、ストレスなく働きやすい環境を整えるためにも、AIチャットボットの導入が必要なのです。
コスト削減
AIチャットボットの導入は、コスト削減も期待できます。
総務部門が問い合わせ対応業務に圧迫されていると、そのほかの業務に手をつけることができず、どうしても残業が強いられるケースも考えられます。その場合、残業代が発生しますし、こういった状況が続くと人材流出につながり、新たに採用コストや教育コストが発生する可能性も考えられます。
もちろん、AIチャットボットの導入には費用がかかりますが、長期的な目線で見ると、コスト削減につながるのです。
まずは総務部門側のメリットについて3つご紹介しましたが、従業員側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。次章で見ていきましょう。
ナレッジの蓄積になる
チャットボットには、問い合わせ内容や会話をログとして記録する機能が搭載されています。この機能を活用することで、総務部に寄せられる問い合わせ・意見・要望といったデータをナレッジとして蓄積して、今後の対応や業務改善に活かすことができます。
社内でアンケートやリサーチを実施することなく、自動で貴重なデータ(ナレッジ)を収集・蓄積できることも、総務部がチャットボットを活用するメリットのひとつです。
従業員のメリット
従業員にとって「ちょっと聞きたい」「マニュアルのどこに書いてあるのか教えて欲しい」という簡単な内容は、即時に回答が欲しいものです。
AIチャットボットを利用すれば、「すぐに」「いつでも」質問することができ、業務を止めずにすむため、生産効率が上がるメリットがあります。
すぐに回答を得られる
出張前手続きや経費の精算など、期限がタイトな手続きほど手間がかかり、周囲に聞く人がいないものです。
「前に一度やったことがあるけれど、やり方を忘れてしまった。」「マニュアルの場所が分からない」など、作業が進まず本来やりたいことに着手できないのはストレスに感じるでしょう。
メールや電話での問い合わせは、担当者がすぐに対応できないこともありますが、AIチャットボットなら自動でかつリアルタイムに回答が来るので、「待つ」ストレスが無くなりスムーズに問題を解決してくれるのです。
24時間365日利用できる
社内のバックオフィス部門は18時前後で終業することが多く、外出や対人応対が主務である営業部門などは、就業時間内に問い合わせする余裕がないこともあるでしょう。
また、テレワークの推進により対応者が不在の場合も多く、回答がいつになるのか分からない状態で待たされることもあります。
AIチャットボットは24時間365日対応しているので、問い合わせニーズが高い時間帯と受付時間のミスマッチを無くし、曜日や時間を気にすることなく気軽に利用でき、問題を即時解決してくれます。
チャットボットツールが総務に適しているポイント
総務部の問い合わせ対応を削減する方法には、FAQや社内マニュアル等もあります。多くの企業では、社内ルール・規則・定型的な内容等はFAQ・マニュアルで一般的に提供されています。
しかし、これらの方法は必要な情報を探すのに手間・時間が必要となり、また解決に至らないケースも発生します。結局総務部に問い合わせた方がスムーズに解決できるため、利用率も上がらず内容の精度や利便性の向上も行われないという事情があります。
チャットボットであれば、対話を通じてスムーズかつスピーディーに問題を解決することができます。また、操作も直感的で分かりやすく利用のハードルも低いため、社内での利用率向上も容易に高めることが可能です。
チャットボットが持つ「利用されやすいこと」「使いやすいこと」「スムーズに回答を得られること」という特性は、総務部の業務を代替させて業務効率化・業務負荷軽減を図るのに非常に適していると言えるでしょう。
総務部門でAIチャットボットを有効活用するには?

総務部門、従業員双方にメリットのあるAIチャットボットですが、より効果的に活用していくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか?
ここでは、AIチャットボットを有効活用するポイントをいくつかご紹介します。
過去に寄せられた質問には回答できるようにする
過去に寄せられたことのある問い合わせ内容は、今後も従業員から質問される可能性が高いといえます。そのため、過去に寄せられた質問は、必ず回答できるように設定しましょう。
また、過去の問い合わせ内容から、「こんな質問も寄せられるかも」というものがあれば、あわせて設定しておくといいでしょう。
もちろん、AIチャットボットは学習を繰り返すことで、徐々に回答精度を高めていくという点が特徴があります。しかし、導入初期からなるべく高い解決率を目指すには、こういった過去に実際あった問い合わせ内容を参考にしてみることが効果的です。
チューニングを欠かさない
AIチャットボットは、会話を繰り返し学習することで回答精度が高まってくるツールです。
この特性を有効利用するためには、質問に正しく答えを返しているか、質問の意味を正しく理解しているかなど、定期的なメンテナンスが欠かせません。
設計段階では想定していなかった質問内容や、アプローチの仕方(表現)などのデータを集め、修正や追加を繰り返し学習させることで正答率を上げていくのです。
チューニングを怠ると、回答制度が下がり利用者の満足度は落ちてしまいます。
求めている回答が得られなくなると利用頻度は下がっていくため、導入時にはまめにチューニングを行い、ツールを育てる時間を作りましょう。
回答内容を工夫する
AIチャットボットは、回答内容を工夫することも重要です。
従業員は、「何かしら不明な点があるから」問い合わせをしてきます。まずどの従業員が見ても分かるように、専門的な用語は避けるようにしましょう。
また、チャットボットは電話での対応を違い、画像や動画などさまざまな形で回答を送ることができます。例えば、社内で利用しているシステムの使い方について質問された場合は、実際の画面をスクリーンショット、または録画したものを活用して回答するなど、工夫してみてください。
確かに、画像や動画を用意することは手間がかかりますが、こういった工夫をすることで解決率の改善が期待できます。今後の業務効率化を考え、回答の作成は丁寧に行うようにしましょう。
利用データを分析する
利用者にとって、AIチャットボットを継続して活用するかどうかは「回答精度」で決まります。
チャットボットはいくつかの段階を設け、質問内容を切り分けしながら回答にたどり着きますが、質問の途中で「求めている選択肢がない」「質問の意味を理解してもらえない」などの理由で、回答に行きつく前に「離脱」されてしまうこともあります。
蓄積されたデータを分析することで、離脱箇所を特定し、選択肢の追加や表現の修正、寄せられる質問を再学習させれば、ユーザーが求める答えを返すことができ、継続利用につながります。
管理がしやすいツールを選ぶ
AIチャットボットは、データを蓄積することにより学習し育っていくツールのため、構築後の管理は不可欠です。
- 回答できなかった質問に、回答を追加する
- 離脱された階層に、選択肢を追加する
- 間違った回答を修正する
- 問い合わせ内容の集計と分析を行う
このような再学習(チューニング)を定期的に行う必要があるため、管理は簡単で手間のかからないツールを選びましょう。
また、どのような質問が多かったのか、問い合わせに集中した時間帯、解決までにかかった時間などが一目でわかりやすくレポートされていることも重要なポイントです。
総務におけるチャットボット導入手順
チャットボットの導入には一定のプロセスを踏襲する必要があります。総務部のチャットボット導入においても同様です。ここでは、総務部のチャットボット導入の手順についてご紹介します。
これから導入を検討している方は、スムーズに導入を進めるためにも、導入の手順を把握・理解しておきましょう。
導入の計画を立てる
総務部にチャットボットを導入するステップは、まずは導入の計画を立てることからはじまります。自社の状況に照らし合わせながら、次のような要件を決定していきます。
- チャットボット導入の目的
- 目指すべきゴール(理想の状態)
- 運用ルール
- 運用メンバー
- メンテナンスのスケジュール
- 導入日・導入までの進捗スケジュール
チャットボットの導入目的や計画が曖昧なままでは導入上手くが進まず、また総務部にとってベネフィットのあるチャットボットの作成・運用も難しくなります。そのため、総務部にチャットボットを導入する際には、必ず導入計画については明確に設定しておきましょう。
掲載が必要なFAQをまとめる
総務部にチャットボットを導入するには、チャットボットに対応を行わせるためのFAQデータが必要となります。FAQとは、よくある質問と回答を集めたものを指します。
チャットボットを作成する準備として、まずは総務部に寄せられる問い合わせと回答をまとめてFAQを作成します。問い合わせを行う質問者が抱える課題やニーズについても洗い出しておきます。
いざ何もない状態からFAQを作成しようとすると考えがまとまらなかったり作成が進まなかったりするケースが良くあります。そこでおすすめとなる方法が、プリセットをカスタマイズする方法です。
プリセットとは、あらかじめ想定される質問・回答のたたき台のことです。プリセットを自社に合わせてカスタマイズすることで、比較的スムーズに網羅的なFAQを作成することができるため、ぜひお試し下さい。
チャットボットを作成する
チャットボットの作成方法には、自社開発を行う方法とチャットボット作成ツールを活用する方法があります。低コストでスムーズにチャットボットを作成できるため、一般的には後者の方法で作成を行います。
FAQがまとまったら、チャットボットを利用するユーザーが辿るシナリオを作成していきます。想定される質問の流れを想定して、ユーザーができるだけスムーズに回答を得られるように質問文や分岐を設計するのがポイントです。
できあがったシナリオをチャットボットに設定すれば、チャットボットの作成は完了です。
テスト運用を行う
作成したチャットボットは、本運用を行う前にテスト運用を行って、使い勝手・回答精度・操作性などに問題が無いかをチェックします。複数のテスト担当者が利用者視点でチャットボットのテストを行い、できるだけ漏れが無いようにチェックを入れていきます。
テストを行わずに本運用を始めてしまうと、チャットボットのクオリティが担保されていないため予想外のイレギュラーやトラブルが発生するリスクがあります。
導入開始直後からスムーズにチャットボットの利用を推進するためにも、利用率を高めていくためにも、テスト運用は必ず実施しておきましょう。
社内に周知し利用してもらう
総務部門の効率化・負担軽減のためにチャットボットを導入しても、社内で活用されなければ意味がありません。そのため、総務部門への問い合わせ用のチャットボットを導入する際には、社内に周知して積極的に利用を促進することが重要です。
社内でチャットボットの活用が進まない大きな原因は、周知不足であるケースが多々あります。チャットボットの活用メリットや利便性を繰り返し周知して、社内に文化として定着させるようにしましょう。
チャットボットの利用を促進するためには、社内セミナーや勉強会を開催して、チャットボットのパフォーマンスをデモンストレーションを行う方法もおすすめです。
反応をもとに改善する
チャットボットは一度導入して終わりではなく、利用データ・利用者の反応を基に繰り返し改善を重ね、回答率・回答精度を高めていくことが重要となります。改善を怠ると「思うような回答が得られない」「使いづらい」といった理由で利用者も離れてしまうため、総務部の業務効率化・業務負荷軽減という本来の目的も達成できなくなります。
チャットボットの継続的改善を定着させるためには、担当者を設けて改善する時期をスケジューリングするなど、メンテナンスの仕組化を行っておくのがおすすめです。
総務部への問い合わせを軽減するためにも、利用者にベネフィットを提供するためにも、チャットボットの継続的な改善は必ず実施するようにしましょう。
総務部門向けチャットボットツール「チャットディーラーAI」

ここでは、AIチャットボット「チャットディーラーAI」をご紹介します。チャットディーラーは、今までカスタマーサポート向けのシナリオチャットボットを提供していましたが、社内専用のAIチャットボットを新たにリリースしました。チャットディーラーAIの主な特徴は次の通りです。
-
学習済みAIを搭載
総務部門に寄せられることが予想される問い合わせ内容を学習済みであることです。設定・導入をスムーズに行うことが可能となり、導入初期から高い回答精度を期待できます。
-
有人チャットの併用・切替も可能
有人チャットへの切り替え機能も搭載しており、チャットボットで解決できない問い合わせに対してもスムーズに問題を図ることが可能です。
-
コンサルティング・サポートも充実
追加費用なしで専属のコンサルサポートを受けることができるため、初めてチャットボットを導入する方も安心して目標達成・パフォーマンスの発揮が可能です。
チャットディーラーAIの総務部のおける導入事例を紹介
複数のクラウドサービスを提供する株式会社ラクスの総務部人事課では、メールやチャットによる問い合わせ対応により、コア業務に着手するリソースが圧迫されるという課題を抱えていました。
問い合わせ対応に遅れると質問者の業務が停滞することから優先せざるを得ず、総務部においても定期的に実施する業務や締め切りのある業務を抱えているため、課題を解決するためにチャットボットを導入して問い合わせ対応を代替させることに着手。
チャットディーラーAIを導入したところ、総務部に寄せられる問い合わせ対応件数を50%削減することに成功。リソース圧迫の課題も解決され、総務部の業務効率化・業務負荷軽減を図ることができました。
現在においても、フィードバックを基にさらなる改善を重ね、問い合わせ件数削減・業務効率化・業務負荷軽減を目指しています。
【インタビュー】総務がAIチャットボットを導入して問い合わせ対応件数を50%削減!
チャットディーラーAIについては、以下のページから無料で資料をダウンロードできます。ぜひ、チェックしてみて下さい。
まとめ
自動応答ツールAIチャットボットの導入は、総務部門と従業員双方の業務負担を減らし、本業務の生産効率を上げることができます。
定期的なチューニングを行い回答精度の高いツールに育てれば、従業員自身で問題を解決でき、総務部門の貴重な時間を奪われません。
利用率、正答率を上げるには導入後のチューニングも重要になってくるので、管理しやすいツールを選ぶことも重要な課題です。
企業規模や環境に合わせ最適なツールを選定し、社内全体の業務効率を向上させましょう。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。