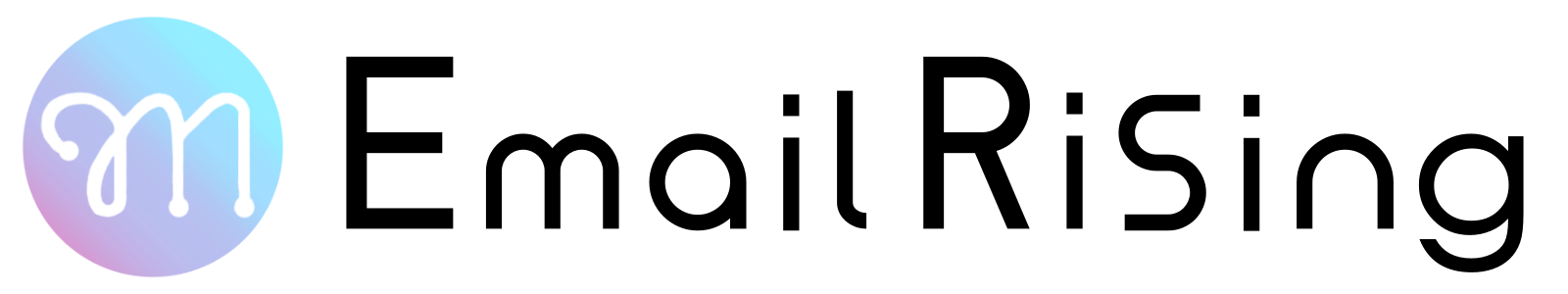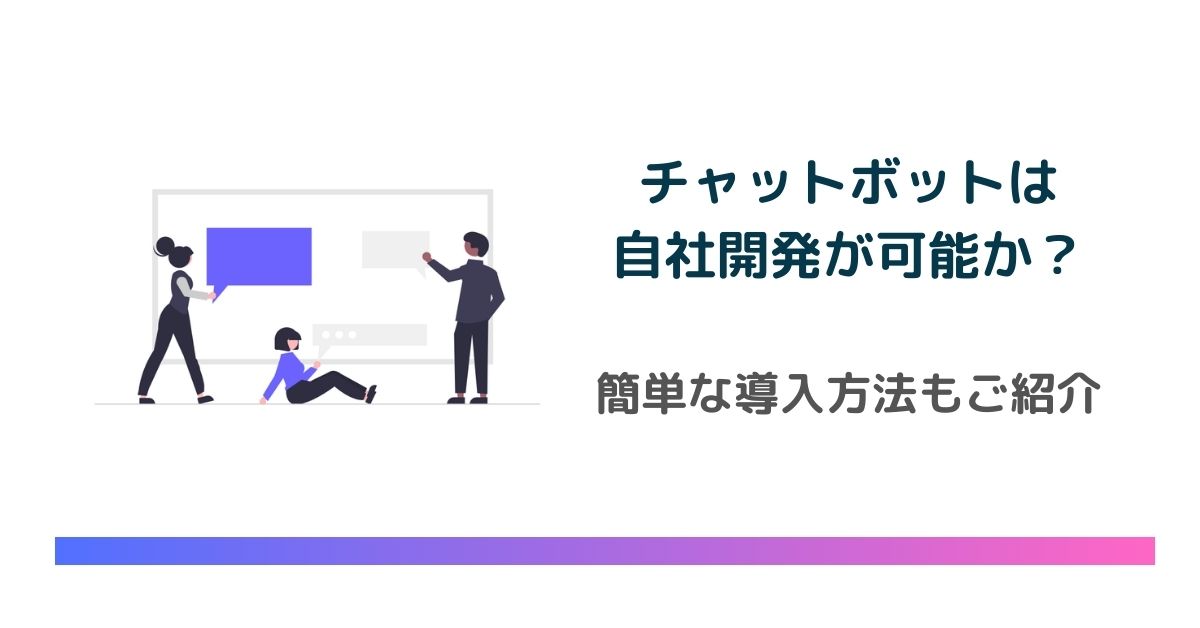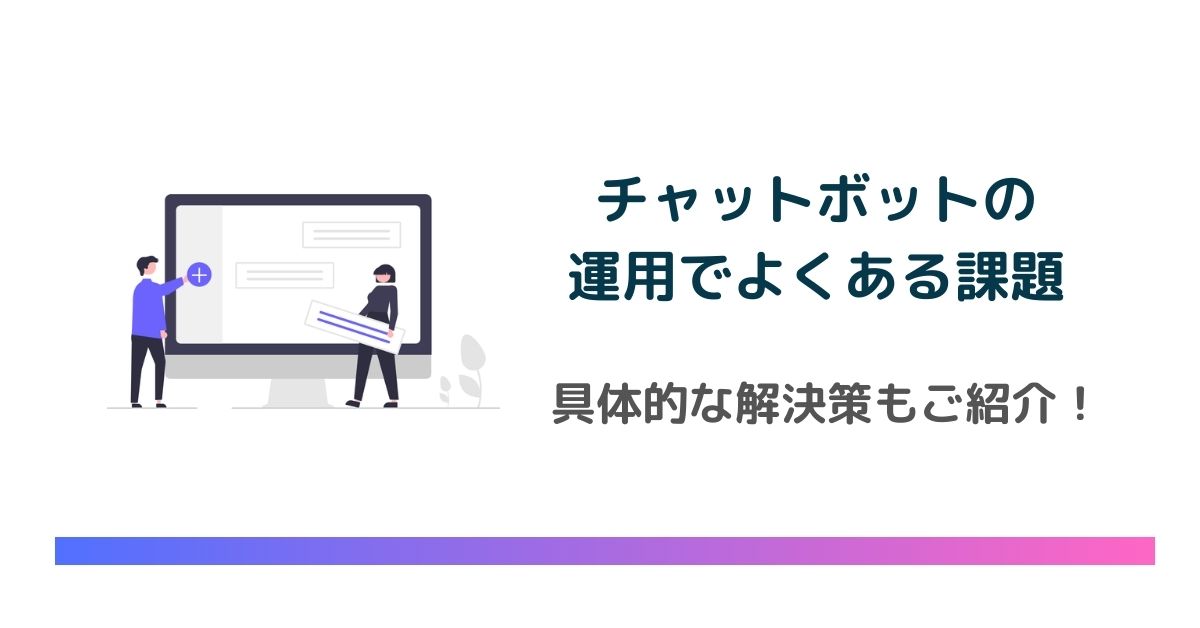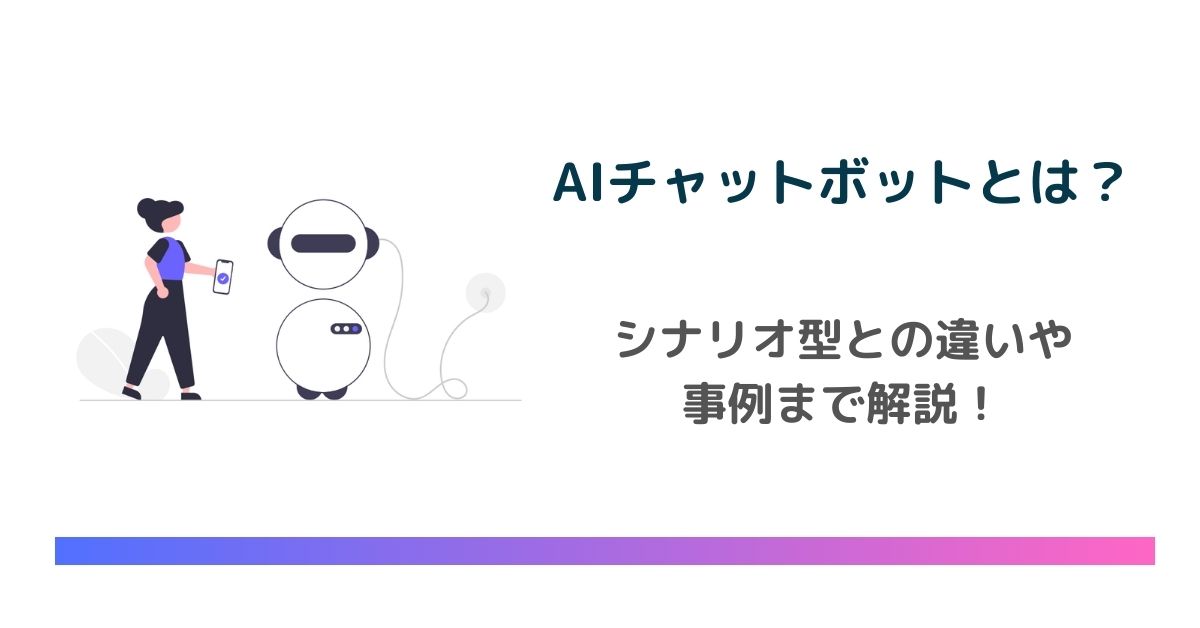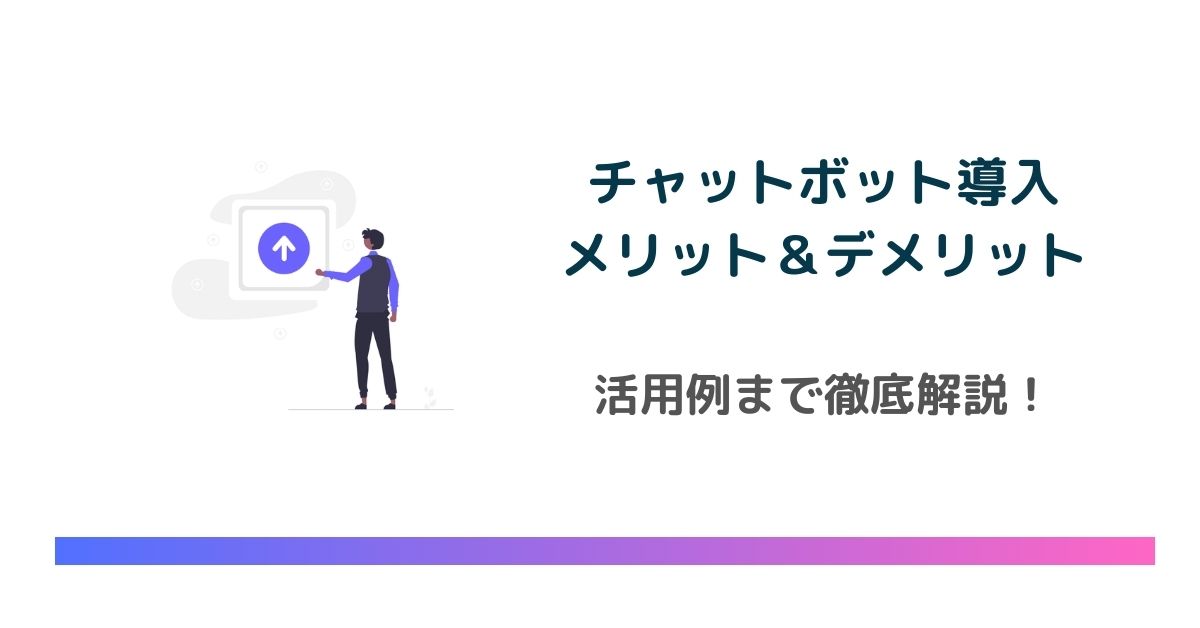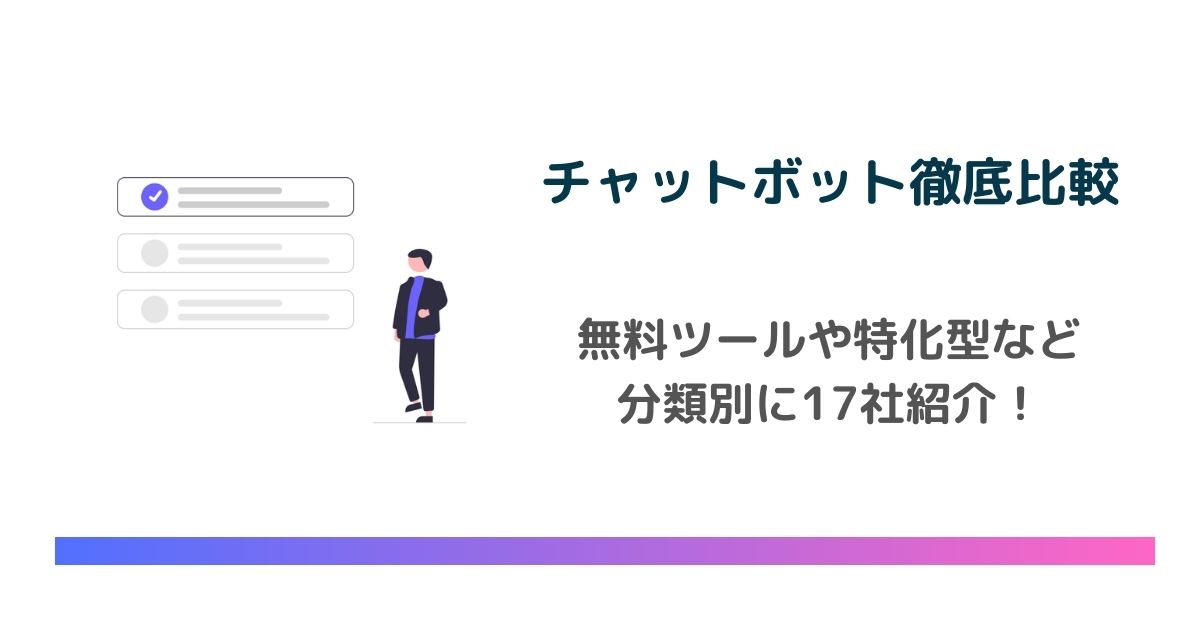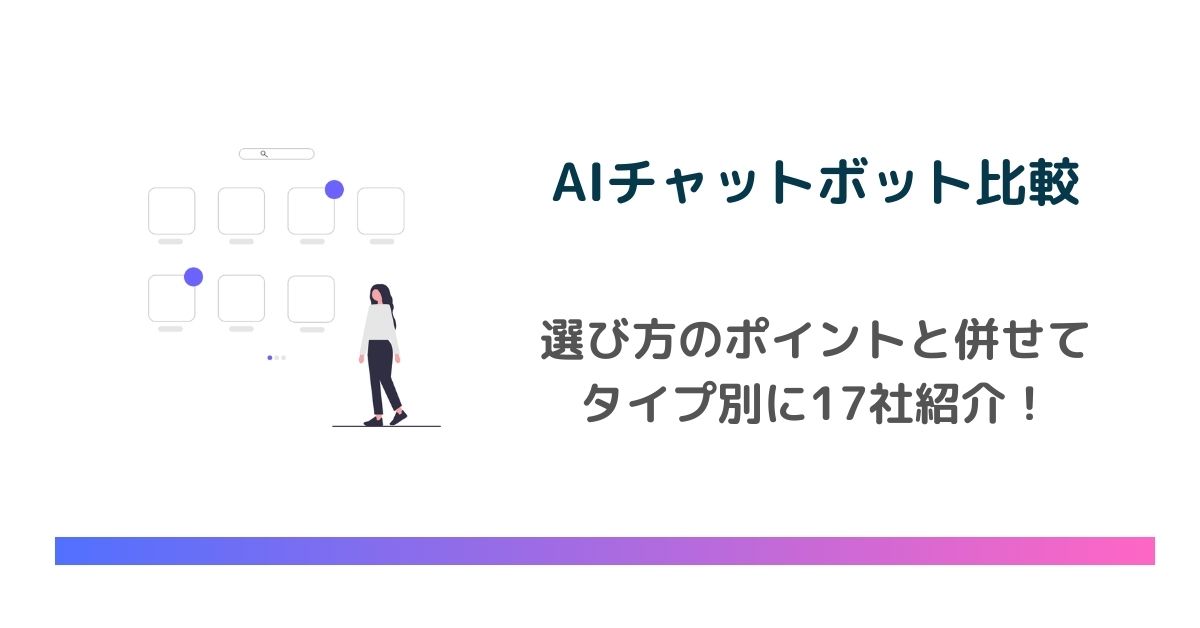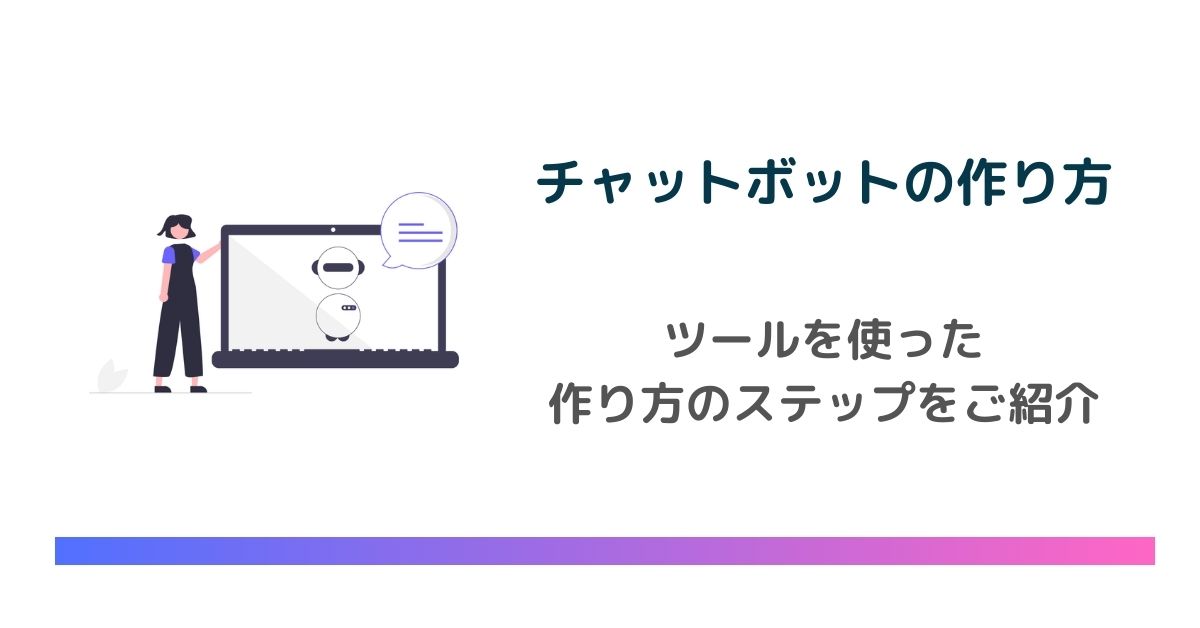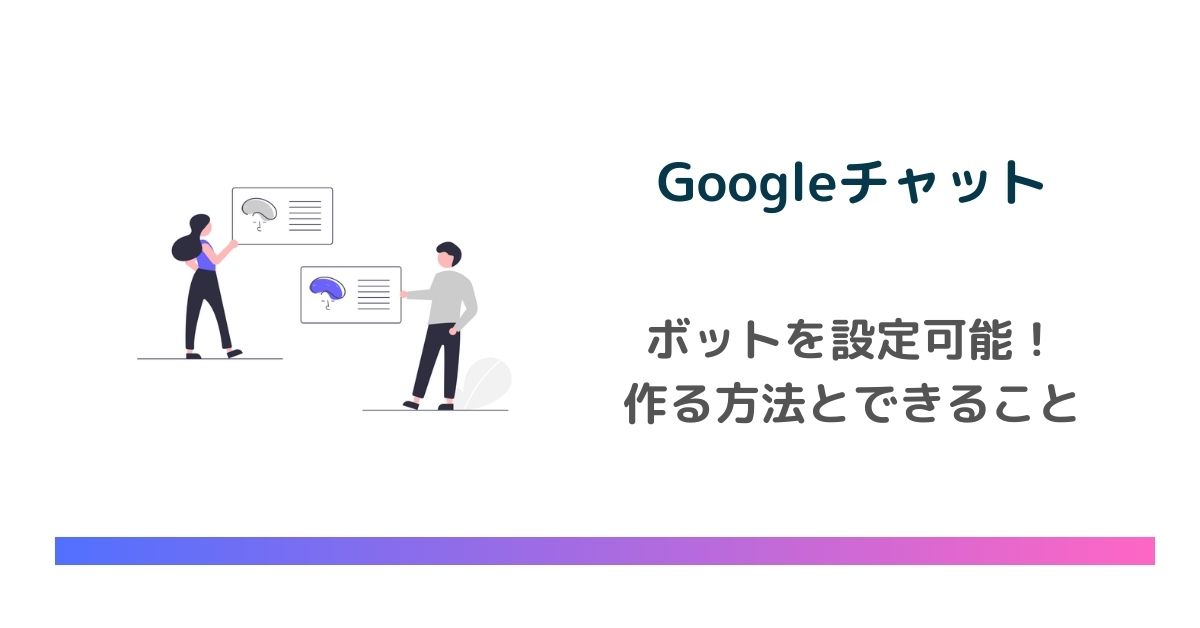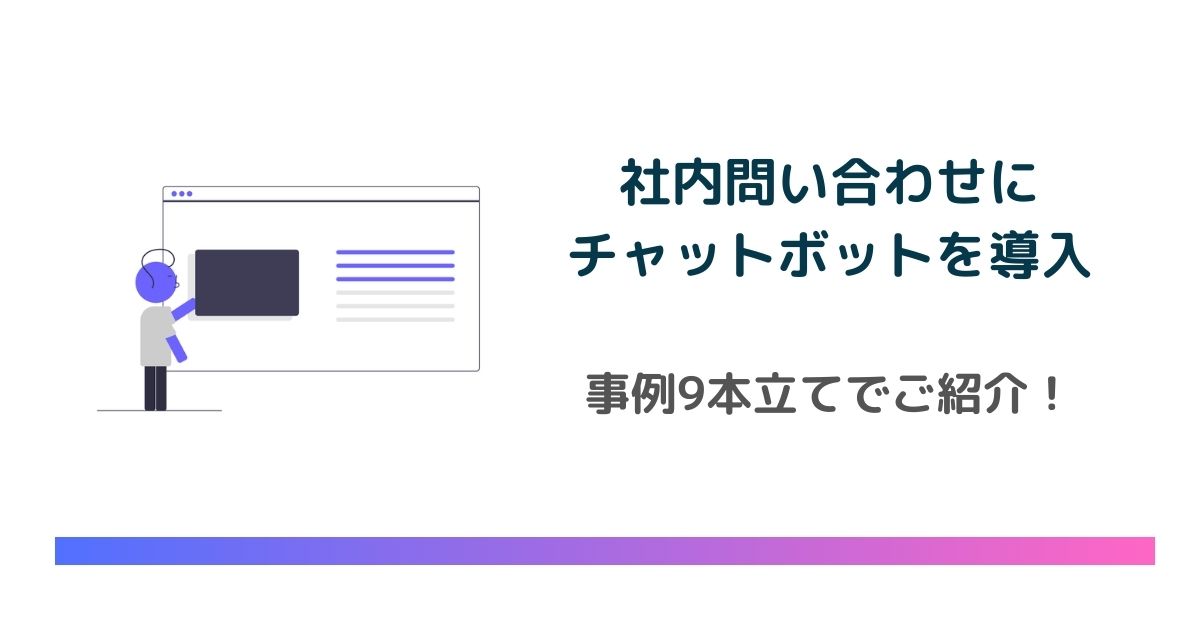
働き方改革やDXの推進により、ITをうまく活用した「社内業務の生産性向上」が強く求められています。
そこで注目されているのが「チャットボット」です。社内問い合わせ対応の効率化にチャットボットが効果的らしいという噂は果たして本当でしょうか?
どのように活用できるのか、事例を交えてご紹介します。
なぜ社内問い合わせにチャットボット?
チャットボットは、BtoCだけでなく企業内での活用にもうってつけです。
企業の情報システムや経理・総務・人事労務といった管理部門(バックオフィス)は、毎日のように社内各部署から質問が舞い込みます。
しかし、それらは社内マニュアルに載っているようなトラブルやサポートに関連した「よくある問い合わせ」ということがほとんど。
「さっき答えたばかりなのに、また同じ問い合わせが……」とうんざりしつつも、作業の手を止めて対応せざるを得ません。
このように社内問い合わせに時間をとられて仕事を効率よく進めたくても進められない、また、そもそもメインで取り組む必要のあるコア業務に着手できないという課題があります。
社内問い合わせでありがちな課題
先ほども少し触れましたが、日々社内のヘルプデスクに寄せられる問い合わせは、マニュアルや社内FAQを確認すれば解決するものも多くあります。
社員が「どのマニュアルを確認すればいいのか」「どこの窓口に問い合わせをすればいいのか」を把握していないことが課題です。特に従業員数の多い大企業の場合は、マニュアルの複雑化、社内問い合わせ窓口の多さから、上記のような課題を抱えているでしょう。
重複する社内問い合わせ内容に対して一つひとつ、人手を割いて対応することは効率的とはいえません。
社外向けの業務改善が優先され、つい優先順位が低くなりがちな社内問い合わせの業務効率化。実は、解決すべき課題が、どんどん山積みになっていることも少なくはありません。
実際に、企業はどのような課題を抱えているのでしょうか。
社内FAQを利用してもらえない
社内FAQとは、よくある社内問い合わせ内容を蓄積してデータベース化しておくことで、社員が窓口に問い合わせをせずに、自分自身で解決できるようにする仕組みです。
社内問い合わせ業務の負担軽減のために社内FAQを立ち上げたものの、なかなか社員に利用してもらえないという状況に悩む担当者の方もいるはずです。
問い合わせる側の社員からすると、情報が多くFAQから必要な解決策が探せない、急いでいるため社内窓口に直接問い合わせた方がはやい、という理由から社内FAQを活用せずに問い合わせてくるケースが多いと考えられます。
問い合わせ対応が属人化している
社内問い合わせ業務でよくある課題のひとつに、特定の担当者に業務や進捗が偏るという属人化が挙げられます。属人化が起こると、担当者により対応の可否や対応品質にムラが生じてしまうため、主要な担当者として活動している人物が席を外したり休んだりしている場合に、利用者に対して回答を提供できないケースが生じます。
また、特定の担当者に業務負荷が集中して、心身の負担となるという懸念もあります。問い合わせをした側の社員からすると、問題が解決しなければ先の業務を進めることができず、時間と労力を大きくロスしてしまうでしょう。
対応部署の属人化は企業の業務効率が悪化する要因となるため、問い合わせ対応部署をスムーズに機能させるためにも、また利用者がスムーズに回答を得るためにも、できるだけ早急に解決すべき課題となります。
弊害としてコア業務に着手できない
社内問い合わせ対応に忙殺された結果、本来であれば優先的に着手すべきコア業務に取り組めない弊害が発生します。
結果、残業時間が多くなり、生産性の低下を招いてしまうのです。社員からの問い合わせを放置することは難しく、自身でコントロール可能な業務はついつい後回しになってしまいます。
特に繁忙のタイミングと重なると担当者の負担が甚大で、体調不良や離職などに繋がる危険もあるでしょう。
社内チャットボット導入のメリット
社内チャットボットを導入すれば、社内問い合わせ対応を中心に数多くのメリットを得ることができます。主なメリットについては以下の通りです。
- 社内問い合わせ対応の業務効率化・負荷軽減・コスト削減を図れる
- 社内に散在するナレッジ・ノウハウ・マニュアルを集約でき、業務の属人化解消を図れる
- 社員がいつでもどこでも速やかに回答を得て、問題を自己解決できる
このように、社内チャットボットを導入すれば、社内問い合わせ対応で抱える多くの課題を解決すると同時に、対応部署・利用者双方の業務効率を向上できるため、企業全体の生産性を高めることができます。
社内チャットボットを導入すべき会社規模の目安
社内チャットボットは業務効率化や業務負荷軽減に高い有用性を発揮するツールですが、会社規模が小さいとコストやメンテナンスの労力に対するチャットボットの恩恵が見合わなくなってきます。
一般的には、社内チャットボットを導入した方がよいとされる会社規模の目安は、社員数100人以上とされています。社員数が100人を上回れば、投下したコストや労力に対する十分なリターンが期待できるでしょう。もちろん、社員数が多ければ多いほど、業務自動化や業務効率化の恩恵もより大きなものとなる傾向にあります。
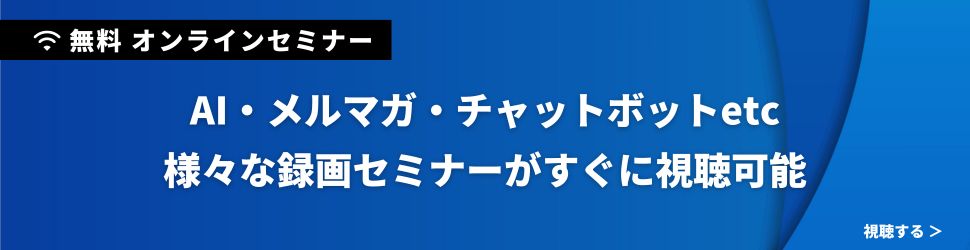
社内向けチャットボットの「部門別・シーン別」活用方法
社内向けチャットボットはさまざまな部門・活用シーンにて使われています。ここではいくつか例を挙げて紹介します。
情報システム部・社内ヘルプデスク
企業の情報システム部では、社内IT環境の整備・運用・管理を担当しながら、社員からのITに関する問い合わせ対応も行わなければならないため、いかに業務自動化や業務効率化を進めてリソースを捻出するかが重要となります。
チャットボットを導入して問い合わせ対応を自動化することで、有人での問い合わせ対応件数を大幅に削減することが可能となり、本来のIT関連の業務に注力するリソースを確保することができます。
一方社内ヘルプデスクは、社内からの業務に関するさまざまな問い合わせに対応しているため、社員数が多い場合や、多数の拠点や店舗を展開している企業の場合は問い合わせ件数が多くなりがちです。返答のスピードが落ちてしまうと、問い合わせを行った社員の業務が停滞してしまう問題にもつながります。
チャットボットを導入すれば、問い合わせ件数に関わらず常に安定的に対応を行うことが可能となるため、社内ヘルプデスクの業務負荷を軽減することが可能です。問い合わせを行う社員も時間・場所・混雑状況に左右されず回答を得られるため、自身の業務をスムーズに進めることが可能となります。
人事部・総務部・経理部などのバックオフィス
人事部・総務部・経理部といったバックオフィス部門も、多くの問い合わせが寄せられる部門です。バックオフィス部門への問い合わせは、資料やFAQを参照すれば自己解決できる簡単な内容から、専門的で複雑な内容まで、あらゆるものが混在しているのが特徴です。これら全てに有人で対応していると時間とリソースを奪われ、業務効率が悪化します。
そこでおすすめとなるのが、チャットボットと有人対応を混在させる方法です。すぐに解決できる問い合わせや簡単な問い合わせはチャットボットに任せ、個別対応が必要な難しい問い合わせに関しては有人対応へ流すことで、無駄な労力を省いて効率的な問い合わせ対応業務を行うことができます。
本部オフィスと現場が離れている場合
複数の拠点や現場を展開しており、本部オフィスで問い合わせ対応を一手に引き受けている場合は、電話・メール・チャット等を用いた問い合わせが本部に集中します。対応部署は大きな負担を抱えることとなり、問い合わせ対応が追い付かず拠点や現場の社員はスムーズに回答を得られないという懸念もあります。
このような場合においては、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化が非常に効果的です。多方面から問い合わせが集中しても件数に関わらず対応を行うことが可能となるため、本部の負荷を軽減できます。問い合わせを行う社員も場所や時間に左右されず、いつでもどこでも回答を得ることが可能となります。
社内情報共有が進んでいない場合
マニュアル共有・FAQの整備・ナレッジマネジメントツールの導入など、社内で情報共有の仕組みを構築していても、社員が利用してくれずに情報共有が進まない場合があります。
このようなケースにおいても、チャットボットの活用が高い有用性を発揮することが可能です。手軽に利用できるチャットボットをこれらの窓口として活用することで、社員は気軽に欲しい情報を探し出すことが可能となり、情報共有や自己解決を促進することができます。
社内向けチャットボットは社外向けチャットボットと違う?
社内向けチャットボットと社外向けチャットボットでは、対象となるユーザーが全く異なることから、機能面においてもさまざまな違いが見られます。
ここでは、社内向けチャットボットと社外向けチャットボットでは、具体的にどのような点において違いがあるのかを解説します。
社内用テンプレートが用意されている
チャットボットの導入時には、ロボットに学習させるためのFAQ(質問と回答がセットになったコンテンツ)を整備する必要があります。より多くの問い合わせニーズに対応するには、質の高いFAQを網羅的に作成する必要がありますが、この作業には膨大な労力がかかるため、チャットボット導入の工数がかかる原因となっています。
社内向けチャットボットの場合は、社内向けFAQのテンプレートが用意されていることが多く、簡単なカスタマイズでFAQを整備することが可能です。テンプレートが充実した製品を選べば、FAQを整備する時間と労力を大幅に削減することができます。
社内用にチューニングされている
チャットボット導入時には、学習用のデータを集めてAIの学習やチューニングを行う必要があります。近年では、導入時の工数を省くため、あらかじめ汎用的なデータの学習とチューニングを済ませた製品が一般的となってきています。
社内向けチャットボットにおいては、多くの企業の社内問い合わせ対応事例等を学習データとして、社内用に学習やチューニングが行われているのが特徴です。質問のパターンやシナリオが網羅されており、自社用に調整するだけですぐに導入を行うことができます。
さまざまな社内向けシステムとの連携が可能
外部連携はチャットボットのパフォーマンスを向上させるための重要な機能です。社内用チャットボットと社外用チャットボットでは、連携させるシステムに大きな違いが見られます。
社内向けチャットボットは、社内でより便利に利用するために、FAQシステム・ナレッジ共有ツール・ビジネスチャット等、メール配信システムなどさまざまな社内向けシステムとの連携が可能であるのが特徴です。
反対に、社外向けチャットボットでは、顧客対応等や販売促進をより利便化するために、SFA・CRM・MA等のシステムとの連携が可能となっています。
相性が良いツールと一緒に使う
チャットボットと相性が良いツールはメール配信システムです。この2つを組み合わせることで、様々な使い方ができます。
その中でも最も汎用的なのが、チャットボット内で反応が大きかったコンテンツや質問が多かった内容をコンテンツにしてメール配信システムで一斉送信することです。これは社内向けでも社外向けでも問題ありません。
さらに、チャット内でリード情報を獲得することができれば、メルマガ配信のリストに追加することも可能となります。
また、チャットボットはあくまで受け身のツールとなるためこちらからのアクションができません。一方でメールであれば攻めの情報発信ツールとして活用できます。
これらのことからもチャットボットとメール配信システムの相性は良いと言えるでしょう。
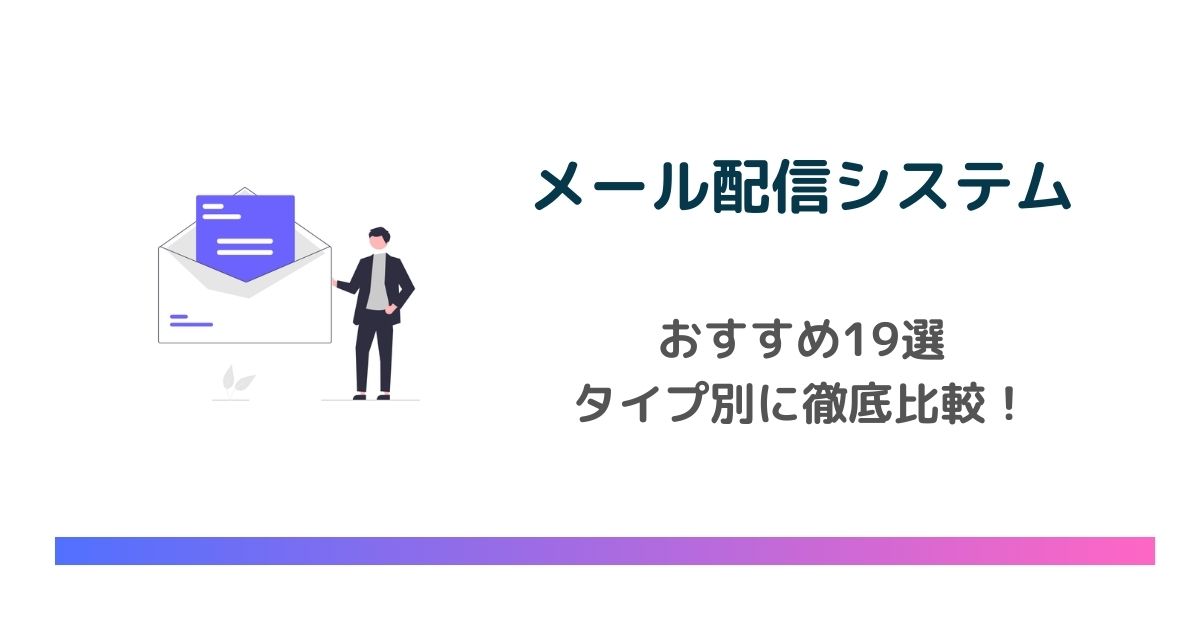
社内向けにチャットボットを導入した事例9本
【導入事例①】サッポロホールディングス株式会社
課題
働き方改革の一環として、業務のあり方を根本的に見直すことに。ナレッジが属人化、FAQの所在がわからないなど社内問い合わせ対応に時間が割かれ、作業効率や生産性の低さが課題に。
導入効果
すぐに問題解決をしたい質問者がたらい回しにされることなく、AIチャットボットを利用して求める回答に迅速にたどりつくことができた。スピーディーな自己解決により時間のロスが減り、お客様と向き合う時間を創出できた。
サッポロに聞くAI導入の極意、「社内問い合わせAI」で顧客対応の時間をひねり出す |ビジネス+IT
【導入事例②】株式会社ベルパーク
課題
最新テクノロジーによる事業推進の一環として、総務人事への問い合わせ対応の自動化が必要になった。
導入効果
社内問い合わせ対応の業務効率が飛躍的に上がり、社員の潜在ニーズの解決を実現。AIチャットボットの導入で社全体の生産性向上に貢献した。
ジェナがベルパーク様における、AIチャットボット「hitTO」の活用事例を公開|株式会社ジェナのプレスリリース
【導入事例④】株式会社ラクス
課題
領収書のペーパーレス化に伴い、社内問い合わせが増加。経理部門の月末月初の業務に支障が出て、生産性を著しく損なう事態に。
導入効果
月平均30件あった問い合わせ対応の稼働時間が約半分に削減。よくある質問に対しては、社内チャットボットがマニュアルへ誘導することで自己解決を促すことに成功。やり取りの往復も激減した。
【インタビュー】社内問い合わせ対応に「チャットボット」を導入した効果とは | 経理プラス
【導入事例③】横河レンタ・リース株式会社
課題
社内ヘルプデスクに寄せられる問い合わせは日に50件以上だが、同じような質問ばかり。FAQマニュアルや新たな問い合わせをトピックス化して社内共有しても読まれずに電話問い合わせが減らない。
導入効果
チャットボット導入後はピーク時の1/10にまで減少。問い合わせ対応が減った分、目の前の作業に集中することができ、ヘルプデスクの業務効率をアップさせた。
チャットbotを導入して、「社内ヘルプデスクの電話対応」をやめてみた結果 (1/4) – ITmedia エンタープライズ
【導入事例④】遠鉄グループ
課題
AIを活用した業務体制の改善が問われる中、お客様の問い合わせ対応として社内チャットボット導入を検討。Q&Aページを用意しているが、問い合わせフォームから似た質問がひっきりなしに寄せられる。
導入効果
社内導入にて実証実験を行い、精度向上のコツとしてAIを育成することを認識する。遊園地サイトでの実装により電話やメールでの問い合わせ負担を減らし、お客様の自己解決に貢献した。
浜松の老舗企業グループが「チャットボット」で業務改善 | マイナビニュース
【導入事例⑤】三井物産
課題
多くの従業員を抱え、幅広い事業を展開するため、社内業務の確認事項が膨大な量になっていた。
特に機械・インフラ事業においては同じ内容の問い合わせが頻発。
導入効果
社内チャットボットの導入によって、精度の高い回答品質を2ヶ月で安定運用できるようになり、問い合わせ対応業務は導入前の1/3ほどに改善された。
チャットボットが対応することで属人化も改善され、引き継ぎ作業への負担が軽減された。
わずか2ヶ月で社内の質問受付体制を3分の1に縮小し、業務品質も向上
【導入事例⑥】ダイキン工業株式会社
課題
社内問い合わせに対応するための電話対応の工数が膨らんでいた。
さらに、問い合わせる側も、問い合わせる前に情報を探したりする工数が発生していたため、双方の業務効率化が課題だった。
導入効果
社内チャットボットの導入によって、問い合わせ対応に関連する社員の工数が削減できた。
また、チャットボットへの質問内容のログから重点的にケアが必要なジャンルの洗い出しもできて社内FAQの精度を上げることにもつながった。
【導入事例⑦】株式会社日清製粉グループ
課題
社内向けのITヘルプデスクが属人化してしまい、対応のクオリティもスピードも担当者次第になってしまっていた。
導入効果
既存のFAQを活用してチャットボットを構築でき、問い合わせへの回答へもスムーズに誘導することができるようになった。
属人化を防ぎ、社内で展開できるようになったため、ITヘルプデスク以外の総務や人事部門でのチャットボット 構築にも取り組んでいる。
【導入事例⑧】西武鉄道株式会社
課題
情報システム部で社内向けヘルプデスクの運用をしており、問い合わせ対応の効率化が課題。テクノロジーを活用した業務効率化を目指していた。
導入効果
チャットボットの導入後、3ヶ月で問い合わせ対応業務を約30%削減。
メンテナンスも簡単で部内外の展開も迅速に可能なため、業務が属人化してしまう心配もありません。
チャットボット導入によりヘルプデスク業務の全体の効率化を実現|RICOH Chatbot Service
【導入事例⑨】パシフィックコンサルタンツ株式会社様
課題
テレワークなどの柔軟な働き方ができる社風が特長だが、職人肌の社員が多いことから長時間労働が常態化していたため、生産性の向上と業務効率化の必要性があった。
導入効果
AIチャットボットの導入により、管理部門と従業員の双方の視点として『回答内容の均一化』ができたので、社内トラブルの原因にもなる回答内容の属人化を防ぐことができるようになった。
また、営業時間外や休日でも質問できるので、従業員にとっての利便性にも貢献した。
HRチャットボットと“一緒に働く”新しいユーザー体験がテレワークなどの「働き方改革」を推進!
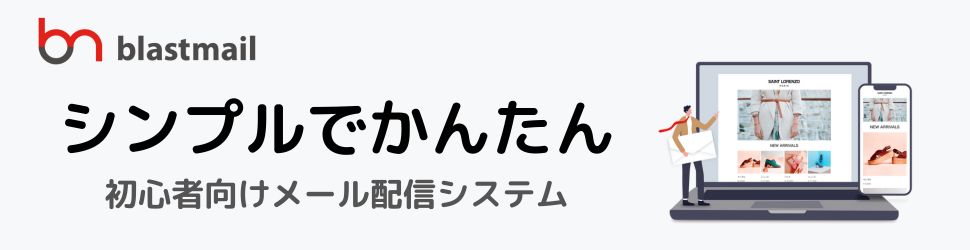
<ダメ絶対!>社内向けチャットボットを導入するときの禁止事項
多くの企業で社内問い合わせ業務にもチャットボットを活用していることがわかりました。
では、チャットボットを導入する際に、気をつけるべきことはあるのでしょうか?社内向けにチャットボットを導入する際の禁止事項をご紹介します。
「回答可能な質問数を増やす」だけ考えるのはNG
まずはどんな質問にも回答できるようにチャットボットの質問数を増やすことを考えがちですが、実はNG事項です。
増えるだけでは、活用されなかった社内FAQと同じく、社員にとって使い勝手の悪いツールとなってしまい、チャットボットがなかなか浸透しなくなることが考えられます。
これまで対応していた問い合わせの内容を参考に、社員がどんなことで対応がわからなくなってしまうのか、問題の原因部分を考えて必要な質問に絞り、チャットボットを充実させて行く方がより効率的といえるでしょう。
解決できなかったときの対処が用意されていない
もちろん、チャットボット上だけで解決することが難しい問い合わせ内容も多く発生しているでしょう。そのようなケースには、問い合わせフォームのリンクを表示させるなど、チャットボット以外の社内問い合わせ方法へと誘導することが必要です。
チャットボットだけでは解決できなかった問題に対して、社員が次に何をすべきなのか提示することで、問題解決のスピードもよりはやくなるでしょう。
チャットボットで、しっかり問題解決の対策まで誘導することによって、業務がストップしてしまうことを防ぐことができます。
“導入して終わり”にならない
チャットボットを構築し、導入したことでこれまでの課題が全て解決するわけではありません。
実際にチャットボット を社内問い合わせで活用してみて、どのような質問が多いのか、本当に設定した回答で解決しているのかを定期的にメンテナンスする必要があります。
チャットボット導入後、すぐに完全な形で運用していくことは難しいかもしれませんが、運用していくなかで、より精度を高め業務効率化を測ることが大切です。
定期的なメンテナンスを繰り返すことが、先々の業務効率化につながるということを意識してチャットボットの運用を続けるようにしましょう。
チャットボットの導入で進める「働き方改革」や「DX」!
いかがでしょうか?
実際に社内チャットボットを導入した企業は、一定の成果を挙げて課題を解決していることがわかりました。導入のハードルは低いですが、ただ導入しただけでは思ったような効果はありません。普及のための工夫、利用者を増やすためのトライ&エラーを得て、チャットボットは機能します。
社内問い合わせ対応から解放され、本来のコア業務に集中できる理想的な働き方改革やDXを実現するためにチャットボットの導入を検討してみませんか?
チャットボットのQ&A
- 社内チャットボットを導入するメリットは?
-
従業員からのよくある問い合わせに自動回答してくれるので、管理部門の対応負担を削減できます。その結果、メイン業務に取り組む時間を生み出すことで生産性の向上に寄与します。一方で、即時回答により質問をした従業員の待ち時間も削減できるので、双方によってメリットがあるといえます。
- 社内のどのような部門で導入されていますか?
-
情報システム・総務・人事労務・経理などのバックオフィスはもちろん、営業事務など社内ヘルプデスクの役割を求められる部門で幅広く導入されています。単一の部門だけでなく、複数部門に横断して利用することで高い費用対効果を見込めます。