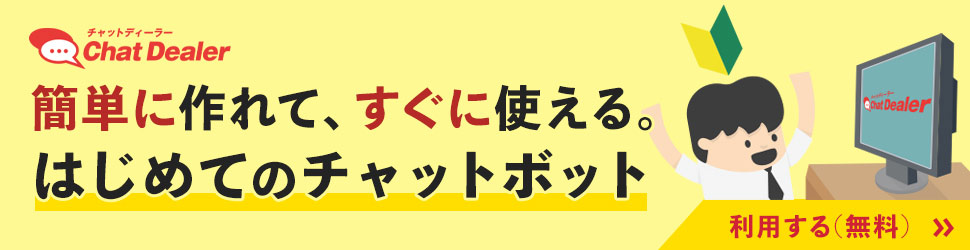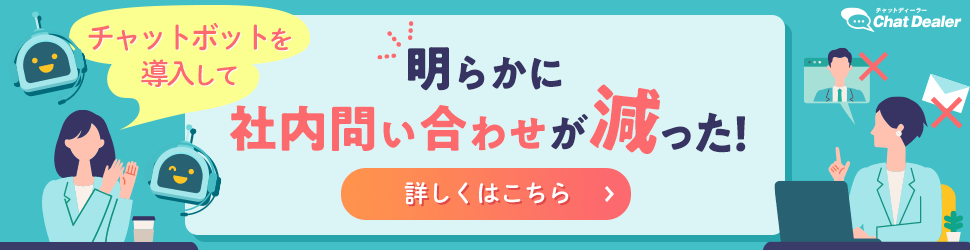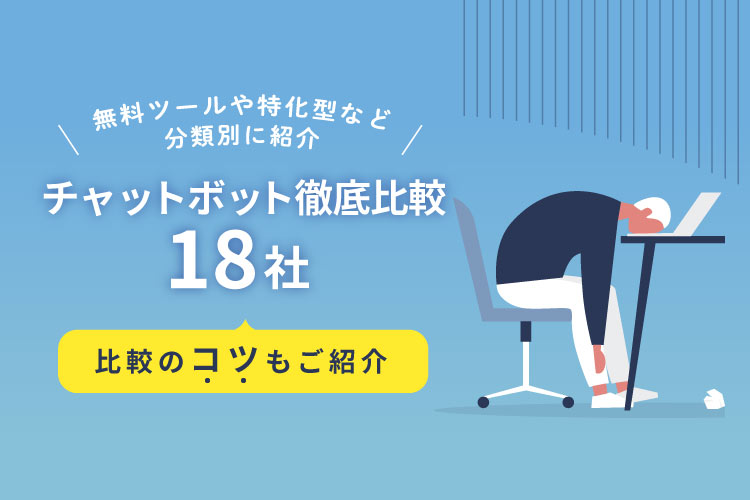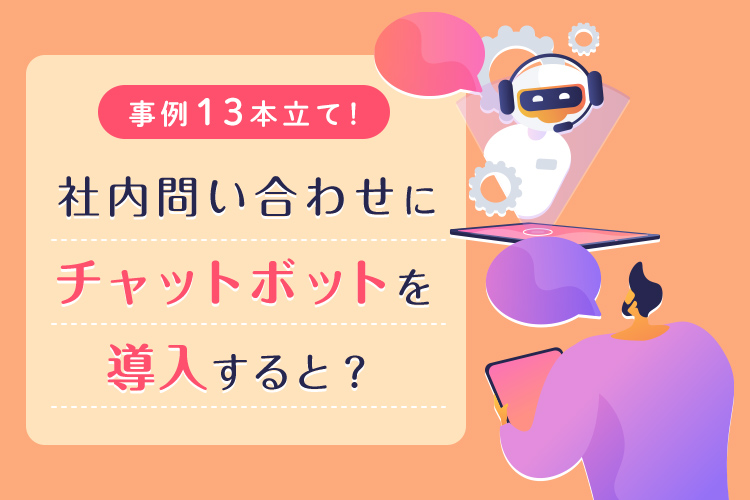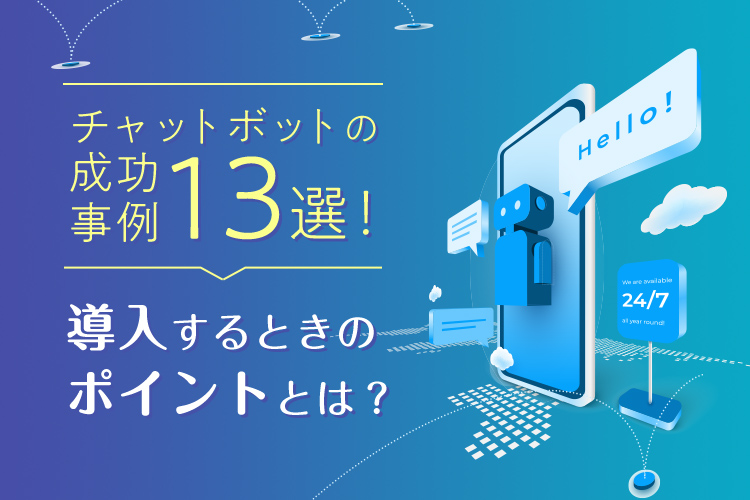チャットボット(chatbot)とは?基本知識とビジネスで実現できること・導入事例を解説
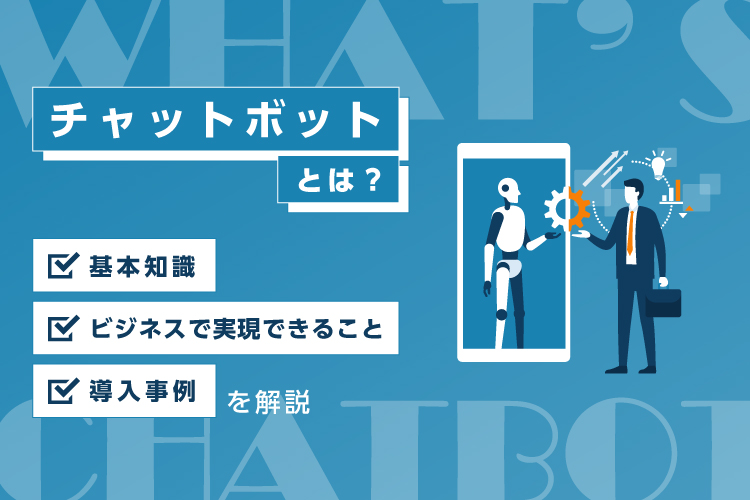
現在、多くのECサイトや企業ホームページで使用されている「チャットボット」。業務効率化と顧客満足度向上を実現する手段として、業種を問わず多くの企業から注目されています。
今回は、チャットボットのメリットを、導入事例とともに詳しく解説。 チャットボットの歴史、仕組み、種類、作成方法なども交えてご紹介します。
チャットボット(chatbot)とは?

チャットボット(chatbot)とは、WEBサービスなどで利用されている「自動会話プログラム」を意味します。
チャットはインターネット上で、テキストを利用した双方向的なコミュニケーションを実現する仕組みです。一方、ボットはロボットの略語で、自動化プログラムを意味します。チャットボットは、これら「チャット」と「ボット」を組み合わせた造語です。
チャットボットは、WebサイトやLINEの画面上に表示され、利用者からの問い合わせやカスタマーサポートの補助などを自動でおこないます。その利便性は多くの企業から注目され、実際に多くのWEBサービスで導入・活用されています。

引用:弊社ホームページ
https://www.chatdealer.jp/
チャットボット(chatbot)の歴史と進化
チャットボットの元祖は、1966年に登場した自然言語処理プログラム・Eliza(イライザ)と言われています。ElizaはiPhoneに搭載された音声アシスタント機能「Siri」の起源としても知られていますが、音声ではなく、テキストでの対話のため、 まさにチャットボットの原型と言えるでしょう。
1997年にMicrosoft・Office97に「Officeアシスタント」が搭載されます。こちらは、ユーザーのソフトウェア使用をサポートする、チャットボットのようなヘルプ情報検索機能です。
2011年にはiPhone4sから、人工知能型音声アシスタント機能「Siri」が搭載されました。2016年には、Facebook、Google、Microsoftなど世界を代表するIT企業がチャットボットサービスを展開。翌年にはGoogleやAmazonがAI搭載スピーカー(スマートスピーカー)を販売し大きな話題となりました。
このように近年ではAI搭載のチャットボットも登場するなど、AIが身近となり、活用シーンも増えています。
チャットボットは現在、Web接客やデジタルマーケティングなどの分野で活用されています。業務効率化などに大きな効果をもたらしている一方、まだ人による細やかな応対に及ばない部分があることも事実です。しかしAI分野は日々、目覚ましい発展を遂げています。今後、AI搭載のチャットボットがさらに高精度で細やかな応対を実現し、ユーザーへより高い利便性をもたらすことが期待されます。
チャットボット(chatbot)の仕組み
チャットボットが動作する仕組みは、以下の3ステップとなります。
1. 「ボット」が、ユーザーからの問いかけを解釈し、回答を生成する
2. 「API」がボットから生成された回答を、インターネット経由で「アプリケーション」へ送る
3. 「アプリケーション」(テキストを表示するWebブラウザやチャットツールなど)へ、ボットから生成された回答が表示される
このように、チャットボットは「アプリケーション」「ボット(Bot)」「API」の3つが協働することで、会話をしているかのような受け答えを成立させています。
なお、APIとは「Application Programming Interface」の略称で、現在はWebサービスやアプリの開発者向けに、有償・無償を問わず数多くのAPIが公開されています。
また、ボットは主要機能として、以下の3つを備えます。
・メッセージ解析/キーワード分析
ユーザーからのメッセージを解析し、キーワードを抽出します。ここにAIを利用すれば、学習を繰り返すことで、より精度の高い解析と判断が可能となります。
・ルール/シナリオ
ユーザーに最適な回答を提供するための、チャットボットの挙動に関する規定を指します。ここにAIを利用すればユーザーとのやりとりを通じて、 ルールやシナリオを追加し、より高精度のやりとりを期待することもできます。
・データベース
ユーザーが求める回答を提供するための、情報源を指します。ここにAIを利用すれば、 会話ログをデータベースとして構築することも可能となります。
チャットボット(chatbot)の種類
チャットボットは「人工知能型」と「人工無能型」の2種類に大別することができます。いずれも、機能の優劣によって名付けられているわけではありません。また、それぞれをさらにアルゴリズムごとに分類することも可能です。
人工知能型と人工無能型
人工知能型と人工無能型の違いは「AI搭載の有無」です。
人工知能型とは「AI型」「機能学習型」などと呼ばれており、近年の研究や技術の進展によって登場しました。人工知能型のチャットボットは、ディープラーニングなどに代表される機械学習によって会話データを分析し、より精度が高くスムーズな会話を実現します。
一方、人工無能型とは「AI非搭載型」を意味しています。選択肢型(シナリオ型)がその代表格で、機械学習なしにユーザーと会話することが可能です。
近年では人工知能型チャットボットも増えてきましたが、人工無能型でもユーザーとの会話やサポートを担うことができます。つまり、チャットボットの全てにAIが搭載されているわけではありません。
人工無能型チャットボットのアルゴリズム
人工無能型チャットボットは、特定のパターンの範囲内で動作することが大きな特徴です。そして、人工無脳型の動作範囲を決めているのがアルゴリズム(問題解決のための処理方法)です。以下、人工無能型チャットボットの3つのアルゴリズムをご紹介します。
・Eliza型
人工会話システムの元祖である自然言語処理プログラム・Eliza(イライザ)から名づけられたアルゴリズムです。相づちや「はい/いいえ」などの簡単な反応、さらにユーザーの言葉の要約などを通じてコミュニケーションを成立させます。積極的な会話や情報提供よりも、聞き役に向いたアルゴリズムと言えるでしょう。
・選択肢型
Q&A(質疑応答)形式で会話をするアルゴリズムです。あらかじめ設定された選択肢を選ぶことで、ユーザーが欲しい情報にたどり着くことができます。
・辞書型
ワード入力形式で会話をするアルゴリズムです。ユーザーが入力したフリーワードに対して、データベースに登録された単語を参照し、回答を提示します。
チャットボット(chatbot)で実現できること

チャットボットの導入によって、実現できる大きなメリットは以下の4点です。
・カスタマーサポート業務の効率化
・蓄積したデータを定量的に把握
・柔軟な顧客対応
・顧客満足度の向上
顧客との接点の場が増やせるだけでなく、業務効率化や顧客満足度の向上も同時に期待できます。ビジネスシーンで様々な貢献が期待できるチャットボットのメリットについて、1つずつ具体的にチェックしていきましょう。
問い合わせ対応の効率化
従来、問い合わせ対応は、人的コストがかかる業務の1つでした。電話では1対1の応対が必要で、質問が重複する場合もその都度回答する必要があります。繁忙期にはスタッフを増員しなければならないケースもあります。さらにメールの場合も、1つずつ内容を確認して対処しなければなりません。
一方、チャットボットは複数人への応対が可能です。簡単な質問やよくある質問は全て、チャットボットが対応します。チャットボットでは対応しきれない問い合わせだけ、スタッフが応対すれば良くなるため「問い合わせ対応の労力の削減」と「人件費の大幅カット」を同時に実現することが可能です。
蓄積したデータを定量的に把握
AIが一般にも普及した現在、データ(情報)が各企業における「資産」として、より存在感を増しています。
チャットボットを導入すれば、「ユーザーの声」という大切なデータの蓄積が容易となり、定量的な把握が可能となります。データを定量的に把握することによって、以下のようなメリットを享受することができます。
・ユーザーが自社に求めるサービスや商品を浮き彫りにすることができる
・潜在的な顧客ニーズを掴むことで、効果的なマーケティングを展開することが期待できる
・自社の商品やサービス、サイトなどの問題点の早期発見と対策が可能となる
なお、電話やメールの内容をデータ化しようとすると、人の手による業務負担が増大しますが、チャットボットではその心配がありません。また、電話やメールによる問い合わせよりも手軽なため、より速く、より多くの顧客データが集まることも期待できます。
柔軟な顧客対応
スタッフ(人間)による顧客対応では、休日や夜間の対応が難しく、タイムラグが生じます。
そこで、チャットボットを活用することで、24時間365日の顧客対応が可能となります。また、チャットボットは電話やメールよりも気軽に問い合わせることが可能なため、顧客接点の増加やコンバージョンへつなげることが期待できます。さらに、チャットボットが窓口となることで、顧客が情報を探し回る手間を削減することができるため、顧客満足度の向上にも寄与します。
ユーザー体験の向上
チャットボットは、ユーザーに対して以下のように利便性以上の体験を与えることも期待できます。
・会話をしているような楽しさや親しみを感じることができる
・簡単な検索と素早いレスポンスによって「電話がつながりづらい」「メールの返信が遅い」といったユーザーの不満を取り除くことができる
・人間が相手ではないため質問・問い合わせのハードルが低くなる
・時間を気にせず質問・問い合わせができる
チャットボット(chatbot)の導入事例

チャットボットを業務効率化や顧客ニーズの把握、顧客満足度の向上などに活用する企業は少しずつ増えています。特に、設定の手軽さと専任担当者によるサポートに強みがある株式会社ラクスのチャットボットサービス「チャットディーラー」は、業種を問わず幅広い企業で導入されています。
ここからは「チャットディーラー」の導入事例として以下3社のケースをご紹介します。
問い合わせ総数を削減 ~株式会社マクロミル 様~

株式会社マクロミルは、日本を代表するリサーチ企業として、グローバルに事業を展開しています。
そんな株式会社マクロミルでは、サポート窓口が平日のみ営業している関係で返信までにタイムラグが生じることが課題となっていました。また、サポート担当者の問い合わせ業務の負担が大きく、その解決策も模索していました。
そこでチャットディーラーを導入したところ、導入前年と比較してトータルの問い合わせ数を20%削減。ユーザーの自己解決を的確にサポートしつつ、業務効率化を達成しました。
新たな顧客ニーズを把握 ~株式会社理究 様~
株式会社理究は「理英会」「どんちゃか」「国大Qゼミ」「ことばの学校」「YOM-TOX」などの教育事業を展開する企業です。
そんな株式会社理究では、ユーザーが求める情報にスムーズにたどり着けておらず、 Webサイトの利便性向上が課題となっていました。
そこでチャットディーラーを導入したところ、チャットの選択率の集計を通じて、ユーザーのニーズ(知りたい情報)をレポートの数値として具体的に把握することが可能となりました。メンテナンスいらずの利便性でデータを蓄積しつつ、より良いWebサイト改修へと活用しています。
顧客満足度を向上 ~山本クリニック 様~

山本クリニックは、鳥取県米子市に院を構える人気クリニックです。豊富な診療科目やサービスを提供しており、訪れる数多くの患者さんの美と健康を支えています。
そんな山本クリニックでは、営業時間中は常に予約や問い合わせの電話対応が必要な状態で「スタッフの業務負担の軽減」と「お客様へのサービス向上」を両立することが課題となっていました。
そこでチャットディーラーを導入したところ、受電数が減少。スタッフの業務負担の軽減を達成しました。さらに、チャット経由で予約するケースも増え、電話が繋がりづらかったお客様へのフォローも実現しています。
その他にも「チャットディーラー」の導入事例がございますので、ぜひこちらをご覧ください。
チャットボット(chatbot)作成方法

チャットボットの作成方法には、以下の4つがあります。
・メッセージングアプリAPI
Facebook、LINE、Slackなどが提供するAPIを利用してチャットボットを作成する方法です。特定のプラットフォームで開発したいケースに向いています。
・Bot開発フレームワーク
Amazon Lex、botkitなど、チャットボット開発に適したフレームワークを利用して作成する方法です。複数のプラットフォームで開発したいケースに向いています。
・クラウド利用の人工知能サービス
IBM Watson、Witなど、クラウドで利用可能な人工知能サービスを利用して作成する方法です。 ユーザーに対するリアクション精度を向上させたいケースなどで活用できます。
・チャットボット作成・支援サービス
ウェブブラウザ上でチャットボットが作成できるサービスを利用した方法です。上記3つとは異なり、プログラミングの知識がなくても、手軽にオリジナルなチャットボットを作成・導入できる点が大きなメリットとなります。
そんなチャットボット作成・支援サービスの中でも、簡単に設定・効果検証できるように設計された「チャットディーラー」は、使い勝手も抜群です。
チャットディーラーは専任担当者によるサポートも手厚いため、チャットボットのスムーズな導入が期待できます。クラウドサービスの老舗企業である株式会社ラクスが提供するサービスなので、信頼性も高いです。そんなチャットディーラーには、他に、以下のようなメリットがあります。
・CSV(エクセル)形式のQ&Aを取り込むだけで簡単チャットボット作成
・アップデートによる製品改良を毎月実施
・1契約につき5サイトまで設置OK
・自動対応と有人対応の組み合わせ可能
チャットボットの作成方法は複数ありますが、それぞれに特徴があるため、作成スタイルに応じて、最適な作成方法を選択する必要があります。また、チャットボットで実現したいことによっても特化すべき機能が変わるため、導入目的を作成前に明確にしておくことが重要です。
ただしチャットボットを1から自社製作するのには、想像以上に多くの人的・時間的コストがかかる恐れがあります。加えて、完成したチャットボットが期待通りに挙動する保証もないため、チャットボットが設置できないリスクも発生します。仮に、チャットボットが問題なく挙動しても、その後、保守点検業務の負担が強いられます。
このような点を考えると、チャットボットを1から自社制作するよりも「チャットボット作成・支援サービスを利用すること」が最もスピーディーで確実な方法ということができます。
*ツール選びの詳しいコツは下記を参照くださいませ
まとめ
働き方改革などによって、企業は「労働生産性の向上」「業務負担の軽減」などの実現が求められています。業務の一部自動化は、これらの課題に対するソリューションですが「チャットボットの導入」は、最も簡単で効果的な業務自動化の1つと言えるでしょう。
全てを自社制作するのは大変ですが、作成・支援サービスを利用すれば、簡単に高性能なチャットボットを設置することが可能です。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。