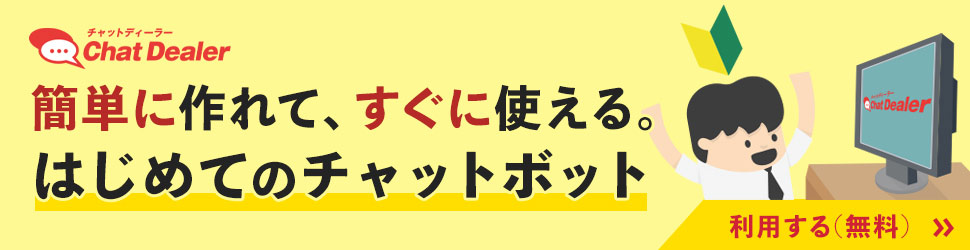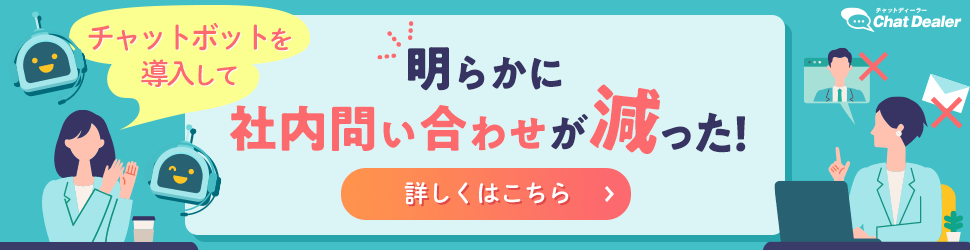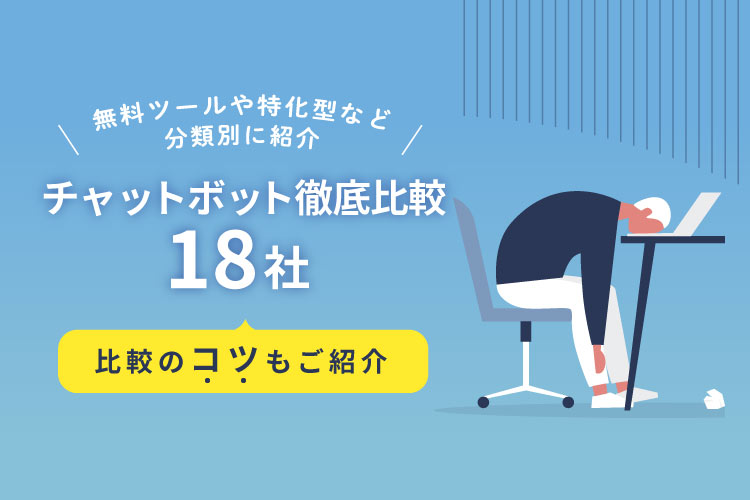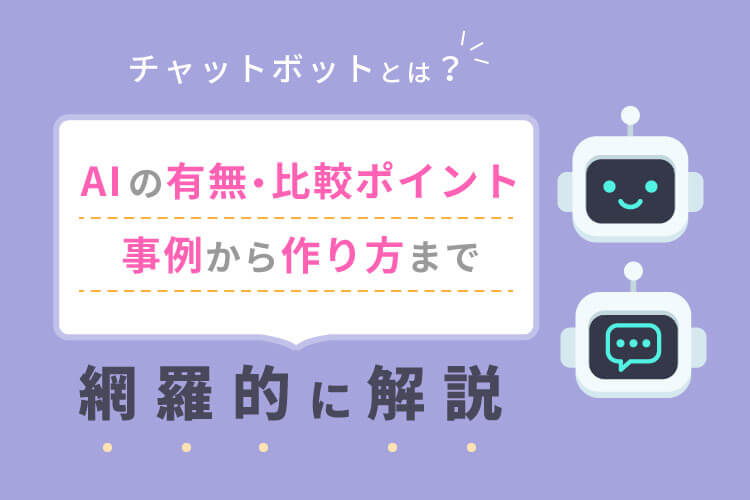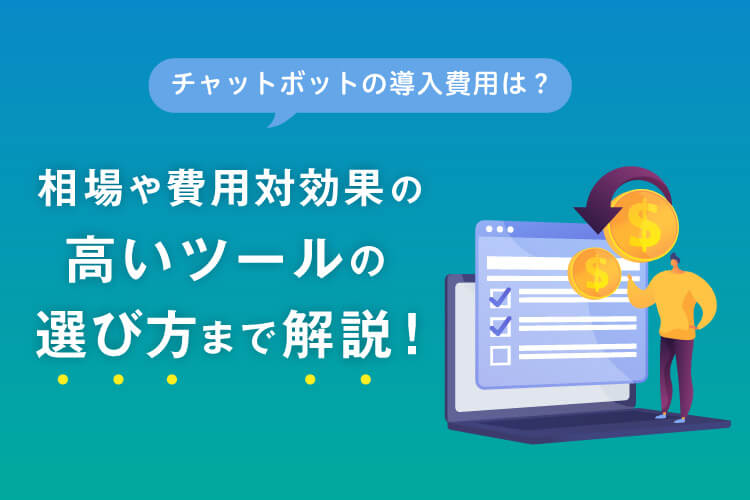チャットボットの失敗事例からわかる導入成功の方法|導入前・運用時でそれぞれやるべきことを解説
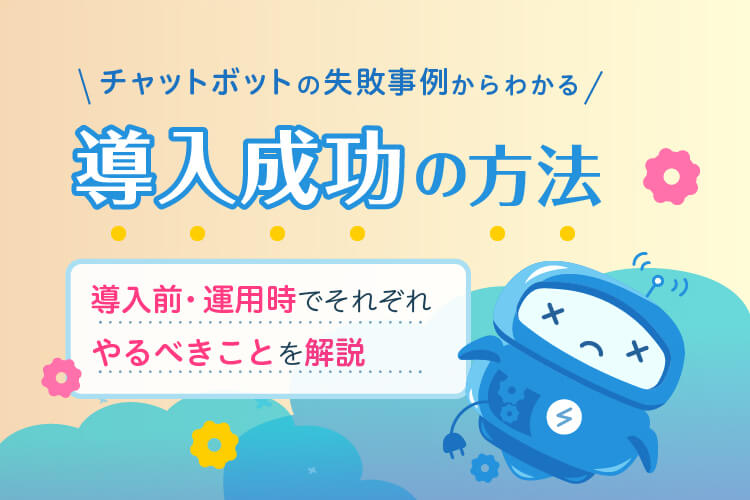
業務効率化の文脈でチャットボットを導入する企業は多くありますが、導入後に思うような成果が出ずに終わってしまった、という声を多くお聞きします。
そこで今回はチャットボット導入で失敗する理由を紐解いた上で、失敗しないための方法・成功事例を紹介していきます。
チャットボット導入で失敗する理由

そもそも「チャットボット導入の失敗」とはどのような状態を指すのでしょうか。
多くの場合、チャットボット導入の失敗とはユーザーが求める要求を満たせていない状態を指します。つまり、スムーズに回答が得られない状態・使い勝手が悪く利用されない状態や、回答を得ても問題解決に繋がらない状態などは、全てチャットボット導入の失敗と言えるでしょう。
一方で、これらの状態を改善することができれば、チャットボット導入の失敗を回避することができます。チャットボット導入に失敗する理由について詳しく見ていきましょう。
効果がわからない
チャットボット導入に失敗してしまう大きな理由として、導入効果を実感できないという原因が多くあげられます。このような場合には、まずはチャットボットの導入効果について計測を行い、施策の妥当性や数値をもとにした改善を施すことが重要となります。
まずは以下のような指標を用いて、チャットボット導入の効果測定・経過観察を行いましょう。
対応部署への問い合わせ件数
チャットボットの導入効果を検証するにあたって最も重要となるのが、問い合わせ対応部署への流入件数です。チャットボットに代替させてどの程度問い合わせを低減できたのかを計測することで、導入効果を判断することができます。
件数が減少していない場合は、利用率や解決率などに問題があると考えられます。
社員の自己解決率
チャットボットは有人対応を利用する代わりに社員が問題を自己解決できてこそ意味があるため、社員の自己解決率を計測することは導入効果を判断するうえで非常に重要です。
チャットボットの利用データやオンラインアンケート等を利用して、どの程度の解決率をはじき出せているのかを計測しましょう。
利用されていない
チャットボットの導入を行っても、社内で利用されていないことから導入効果を得られないという失敗ケースも多くあります。利用されなければ当然問い合わせ件数の削減にも社員の自己解決や業務効率向上にも貢献することはできないため、以下のようなチャットボットの利用率を高める施策も必要となってきます。
- チャットボットの利便性・有用性を社内に周知
- 誰もがアクセスしやすい場所にチャットボットを設置
- チャットボットの使い方を勉強会・研修会でレクチャー
チャットボットの利用率は意識的に働き掛けないとなかなか向上させることはできないため、単に導入・設定を行うだけでなく利用率向上の施策は積極的に行っていきましょう。
回答の精度が低く解決できない
チャットボットを導入したものの回答精度・回答品質が低い場合には、利用した社員が問題や疑問を解決できずに失敗してしまう原因となります。いずれ利用されなくなって従来と同じく対応窓口に問い合わせ対応を行うようになってしまうでしょう。
チャットボットは導入時にFAQを整備して終わりではなく、運用データをもとに常にブラッシュアップを重ねてこそ、はじめて十分な回答精度を発揮できるツールです。
回答精度・回答品質の低さで失敗しないためには、必要十分なメンテナンスやチューニングを行うこと、またそのための体制を社内で構築しておくことが重要となります。
運用コストも含めて費用対効果が合わない
チャットボットの導入・運用には、ツールの初期費用や月額利用料に加えて運用チームにメンテナンスやチューニングを行わせる人的コストが発生します。AI搭載型の高機能・高性能なチャットボットの場合は、運用に必要なコストも高額になる場合もあります。
にもかかわらず、あまり問い合わせ件数を削減できていなかったり、社内で利用されていなかったりする場合には、費用対効果が合わずに導入が失敗してしまう原因となります。
基本的にチャットボットは正しく活用すれば、問い合わせ対応部門の人的コストを大きく上回るコストパフォーマンスを発揮できる特性を持つツールです。投下したコストに対して十分なパフォーマンスが得られていない場合には、目的・用途に合った活用ができているか、また利用率や回答精度を高める施策を行えているかを全面的に見直す必要があるでしょう。
費用対効果が合わない
チャットボットの導入・運用には、ツールの初期費用や月額利用料に加えて運用チームにメンテナンスやチューニングを行わせる人的コストが発生します。AI搭載型の高機能・高性能なチャットボットの場合は、必要なコストも高額になる場合もあります。
にもかかわらず、あまり問い合わせ件数を削減できていなかったり、社内で利用されていなかったりする場合には、費用対効果が合わずに導入が失敗してしまう原因となります。
基本的にチャットボットは正しく活用すれば、問い合わせ対応部門の人的コストを大きく上回るコストパフォーマンスを発揮できる特性を持つツールです。費用対効果が合わない場合には、目的・用途に合った活用ができているか、また利用率や回答精度を高める施策を行えているかを全面的に見直す必要があるでしょう。
チャットボット導入の失敗事例

チャットボット導入の失敗事例として、今回は以下の2つを取り上げます。
- 現場のニーズを十分に反映していなかった
- ユーザー利用率が徐々に低下した
これらの失敗事例に共通するのは、チャットボットを利用する人間の側に立ってチャットボットの設計・登録を行っていないことです。チャットボット開発側が経営層の意見ばかりを取り入れたり、自身がイメージするチャットボット像だけを反映させたりすることによって、実際のニーズに合わないチャットボットが出来上がってしまいます。
使う側のニーズに合わないチャットボットは次第に使われなくなるため、ユーザー目線のチャットボット設計・登録が成功への鍵を握ります。
失敗事例①現場のニーズを十分に反映していなかった
ある企業ではステークホルダーの情報や取引時のルールなどを社内情報として蓄積していましたが、それらの情報に手軽にアクセスするシステムがありませんでした。
そこでチャットボットを導入し、営業担当者が手軽に必要な情報へとアクセスできるようデータベースを作成しましたが、登録した情報がどれも実際の質問内容に適したものでなく、回答精度が低いものとなってしまったため、誰も使わなくなってしまったのです。
この失敗事例からいえることは、現場のニーズを十分に聞き取りした上で、実際の質問項目を用意する必要があった、ということです。単にチャットボットにたくさんの情報を登録しただけでは、本来意図する情報を引き出すことができません。
失敗事例②ユーザー利用率が徐々に低下した
ある企業では社内ヘルプデスクの件数削減と社員の利便性向上を目的としてAIチャットボットを導入しましたが、導入月から徐々にユーザー利用率が低下していきました。
原因はチャットボットに対する質問が事前に想定していなかったものが多く、回答への誘導や回答内容が不適切なものになっていたことにあります。
チャットボットに対して想定していない質問が来るのは避けられないことですので、ある程度の質問パターンは想定しながらも、定期的なメンテナンスによって回答精度のチェックを行い、必要に応じて改善や追加を行っていく事が重要です。事前にチャットボットの運用目的を明確化しておくことで、想定されるメンテナンスの範囲も予測することが可能となり、スムーズにPDCAを回していくことができます。
失敗事例③チャットボットが適していなかった
チャットボットは多くの企業が生産性向上・業務効率化等のために導入している優れたツールですが、どのようなケースにおいてもパフォーマンスを発揮できるとは限りません。そもそもチャットボットでの課題解決が適さないケースというのも存在します。
ある企業では、ナレッジ共有を目的にチャットボットを導入したものの、自社で共有するナレッジの件数が1,000件以上と膨大であり、また対話でのFAQ形式で回答できないような詳細な情報を取り扱う必要があることから、適切な回答を行えずに失敗してしまいました。
このようなケースでは、例えばFAQシステムやナレッジ共有ツールを導入した方が目標達成・課題解決には適していると言えるでしょう。
失敗事例④導入目的が不明確だった
Webシステムを開発する新興ベンチャー企業D社では、業務効率化・生産性向上のために、目的・課題が曖昧なまま人気の高いチャットボット製品を導入しました。しかし、自社の環境・状況や明確な目標設定もないまま導入を行ったため、パフォーマンスも費用対効果も不十分となり失敗に終わってしまいました。
チャットボットの導入は、明確な課題や目的がないと単に面倒な設定やFAQの整備を繰り返してリソースやコストを消費するだけで、何も生まないというケースは多くあります。
勢いや思い付きで導入して失敗する企業の事例は多くあるため、導入時には目的・課題の明確化はもちろん、シミュレーション等も行って具体的な運用イメージを固めておくことが重要となります。
失敗事例⑤メンテナンスに工数を割けていなかった
チャットボットは導入時点で最大限のパフォーマンスを発揮することはできず、ビジネスの状況によって適切な回答の内容も変化し続けるため、運用を成功させるには必要十分なメンテナンスを定期的に実施することが必須です。
ところが、メンテナンスの必要性は理解したうえで導入を行ったものの、実際にメンテナンスを行ってみると想像以上に工数がかかってしまい、十分なチューニングを行えないという失敗事例は多くあります。
チャットボットのメンテナンス工数は、実際に着手してみないと見積もれないケースも多く、利用状況によっても増減するケースがあるため、運用が安定化するまでは多めに工数を確保しておくことが重要となります。
チャットボット導入で失敗しない方法

チャットボット導入で失敗しないためには、チャットボット導入を行う部署の理解が得られている必要があります。どういったニーズがあり、導入の必要性を認識している状態が望ましいといえます。
また、導入後は効果の実感が可視化できるように数値目標を設定しましょう。導入部署で追うべき数値を決めておくことで、成功に向けた施策の展開を進めることができます。
導入時の失敗防止策
チャットボット導入を失敗させないために、導入時にできる失敗防止策には以下のようなものがあります。
-
導入目的の明確化
目的が曖昧なままでは、導入・運用に関するあらゆる点において有効な判断ができないため、失敗の可能性が高くなります。まずは導入・運用の明確化を行っておくことが、失敗を避けるためには最も重要です。
-
自社に合ったツールを選ぶ
チャットボットは製品によって機能・性能・特性はさまざま。自社の目標達成・課題解決に適した製品を選ぶことも、成功確度を高めるためには非常に重要です。
-
無料トライアルを実施する
チャットボットは実際の現場で操作して検証を行ってみないと、良し悪しや適性の判断が難しいツールです。無料トライアルを実施することで、現場での導入効果を適切に判断することが可能となり、失敗のリスクを大幅に低減できます。
-
費用対効果をあらかじめ見積もる
現在問い合わせ対応に要しているコストとチャットボット導入・運用により削減できるコストを事前に試算しておくことで、導入後の費用対効果を見越した導入を行うことが可能。コスト面での失敗リスクを低減できます。
-
操作性、利便性、メンテナンス性を重視する
いくら機能が優れたチャットボットでも、社内のメンバーが使いこなせなければ意味がありません。利用者の誰もが扱いやすく、また運用担当者がメンテナンスを行いやすい製品を選ぶことも非常に重要です。
-
有人対応との併用が可能なチャットボットを導入する
チャットボットに全ての問い合わせを自動対応させることは困難です。導入効果を過信せず、ある程度の有人対応が必要となることを見越して、自動対応と有人対応との併用・切替が可能な製品を導入することも重要なポイントです。
運用時の失敗防止策
チャットボット導入を失敗させないために、運用時にできる失敗防止策には以下のようなものがあります。
-
現場のニーズを反映する
どれだけ優れた機能を有したチャットボットでも、現場のニーズに沿わない運用をしてしまえば導入は失敗に終わります。現場でチャットボットを使う社員がどのような事柄をチャットボットに求めているのかを把握することが重要です。
-
質問内容を想定して回答を入力する
回答内容だけに重きを置いてしまい、質問内容を想定できていないケースが少なくありません。質問内容に対して適切な回答ができるよう入力・調整するのがポイントとなります。
-
意図する回答を行っているか、定期的にチェックする
チャットボットが意図する回答を行っているかどうか定期的にチェックすることも大切です。回答文だけでなく、「自動回答できない場合に問い合わせフォームに案内を出す」といった動きができているかもチェックしましょう。
チャットボット導入の成功事例

チャットボットの導入で失敗しないためには、実際の成功事例を参考にして成功のエッセンスや成功要因を学ぶことが非常に効果的です。
ここでは、弊社製品であるチャットディーラーAIを導入して高い成果を実現した事例を3つご紹介します。
株式会社きらぼしコンサルティングの事例
東京きらぼしフィナンシャルグループの一員であるきらぼしコンサルティングでは、企業情報の提供・セミナー・講演会・コンサルティング等、企業の成長を支援する事業を展開。しかし、企業規模の急速な拡大により社内問い合わせ対応の件数が増加して、コア業務に時間を割けないという課題が発生していました。
そこで、弊社製品であるチャットディーラーAIの導入により、課題解決に着手。同製品の学習済みAI・プリセットされた社内用テンプレートを駆使して約1.5ヶ月の期間で公開することができました。
導入後は、全ての回答を用意していない状態であるにも関わらず、特定の分野での問い合わせ件数削減において劇的な効果を実感。また、問い合わせ担当者の業務負担・対応時間だけでなく心理的な負担を解消することにも成功しました。
運用改善を重ねるほどに社内での利用率も高まってきており、現在は同製品での対応範囲を増やすべくQ&Aの追加や改善施策に注力しています。
日本新薬株式会社の事例
日本新薬株式会社は創業から100年以上経つ新薬メーカーです。多くの従業員を抱えているため、制度の改定や異動のタイミングなどに多くの問い合わせが人事・総務部に寄せられ、担当者が対応に追われてしまいコア業務に十分な時間が割けないという課題がありました。
問い合わせの発生要因を調べたところ、同社では社内データベースに業務に関するさまざまな情報を格納しているものの、検索の精度が十分でなく探しても答えが見つけられない状況があることが判明しました。
この状況を改善するために、社内問い合わせ対応に特化した「チャットディーラーAI」を導入します。
同社ではチャットボットに「サクット」の愛称を付けるなど、親しみやすく利用しやすいようさまざまな工夫を凝らして展開を進めました。その結果、人事・総務部の合計で月に170時間もの問い合わせ対応時間の削減に成功します。
導入後は空いた時間を使って新しい業務に挑戦できるようになるなど、業務改善において大きな効果を発揮しています。
信州大学医学部附属病院の事例
信州大学医学部附属病院は、長野県唯一の大学病院で、地域医療の最後の砦として長野県民の健康と安全を守る高度医療の拠点です。同院では繁忙期に担当部署に対する問い合わせ件数が増加することで、さまざまな問題が発生していました。特に電話での問い合わせが多く、これは業務中PCを操作することが難しいなど病院ならではの事情もあったそうです。
そこで同院ではチャットディーラーAIを導入し、スマートフォンからでも簡単にアクセスして問い合わせができる環境の構築を進めました。
その結果、月平均で45時間もの問い合わせ対応の削減に成功。さらにチャットディーラーAIで解決できなかった問題の内容から「一言で解決できるようなもの」が減るなど、効果を実感しています。
まとめ
チャットディーラーAIは、社内ポータルやビジネスチャットなどに設置して、問い合わせ対応を行うことのできる社内向けAIチャットボットです。
チャットボットが失敗する理由と失敗防止策を知った上で、もし社内でチャットボットを活用したい!とお考えになりましたら、ぜひ詳細ページをご覧くださいませ。
▼チャットディーラーAIの詳細ページ
https://www.chatdealer.jp/
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。