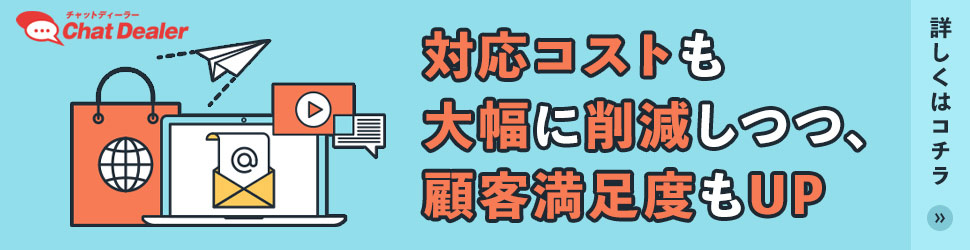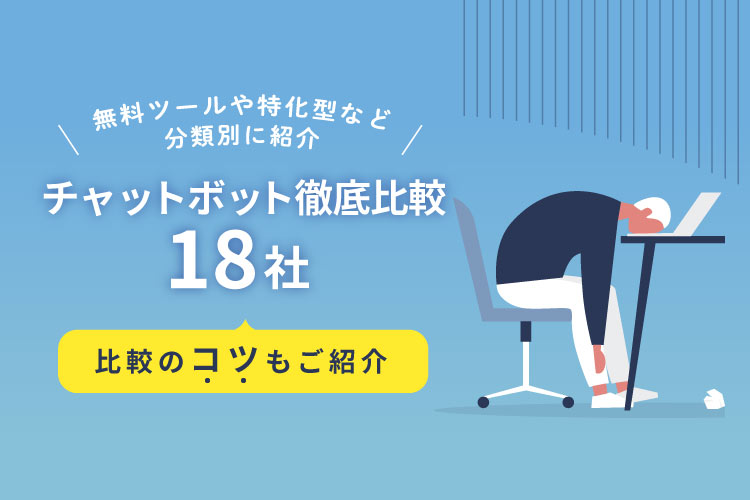チャットボットを導入する自治体が増加する理由とは?8つの事例もあわせてご紹介!

近年、ネットサーフィンをしていても見かけることが多くなった「チャットボット」。
「対話(chat)」と「ロボット(bot)」という2つの言葉を組み合わせた、新たなコミュニケーションツールとして、多くの企業から支持を集めています。
そんなチャットボットは、多様な業務を行う自治体でも広がりを見せています。
そこで今回は、チャットボットを導入する自治体が増加している背景や、実際の導入事例を具体的にご紹介します。
この記事を読めば、チャットボットを導入する自治体が増える理由が明らかになるので、ぜひ参考にしてみてください。
チャットボットが自治体に導入されている理由

ここでは、チャットボットが自治体に導入されている主な3つの理由について解説します。
人手不足の影響
少子高齢化の影響は社会全体に広がっていますが、自治体も例外ではありません。
特に15〜65歳の生産年齢人口の減少は無視できるものではなく、自治体によっては深刻な人手不足問題に発展しています。人々の暮らしを支える自治体の業務は多岐に渡るため、少子高齢化だからといって業務の負担が減るわけではありません。
そうした中で新たな働き手として、チャットボットには大きな期待が寄せられています。既存の業務をチャットボットが代行してくれれば、人手不足をカバーできます。残念ながら少子高齢化は現状改善に向かうことは難しいとされており、少子高齢化が進むにつれて、働き手のさらなる減少も予想されています。
そんな時代の変化に合わせて、さまざまなテクノロジーがビジネス現場にて採用されていますが、その中のひとつがチャットボットです。昔と比較すると自動化された業務は多くありますが、コミュニケーション部分を自動化はなかなか進んでいませんでした。
しかし、チャットボットの登場で窓口業務など、コミュニケーションが必要な場面でも業務が自動化できるようになりつつあります。
働き方改革の影響
生産年齢人口の減少に対処すべく、政府は「働き方改革」を推進しています。働き方改革とは、誰もがいきいきと社会で活躍できるように、働き方を見直すための改革です。働き方改革の具体的な取り組みとしては以下の3つの柱があります。
- 長時間労働の是正
- 正規・非正規の不合理な処遇差の解消
- 多様な働き方の実現
自治体は、こうした政策を中心となって推進する立場です。さまざまな先進的な取り組みを、企業のお手本となるように示さなくてはなりません。そうした観点からも、チャットボットは自治体に大きく注目されています。
自治体で導入効果が確認できれば、多くの企業でもチャットボットの導入が進み、働き方改革の一手となることが期待されているのです。
情報の多様化
インターネットが浸透し、近年ではスマホでありとあらゆる情報を調べられるようになりました。利便性は格段にアップしましたが、情報の多様化も進んでいます。
情報が多様化したことで、世の中にさまざまな情報が溢れ、どれが正確なのか判断することが難しいことが実情です。自治体に関する情報もインターネット上に溢れており、住民は正しい情報を集めるのに苦労したり、本当に正しい情報なのかと不安に感じたりします。
この解決策として、チャットボットを設置すると、住民は正しい情報を簡単・スピーディーに得ることができるようになります。住民が得られるメリットは大きいでしょう。
新型コロナウイルスの感染拡大
新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、さまざまな業界でチャットボットの導入が進んでいます。そして、それは自治体も例外ではありません。
現在、自治体では、新型コロナウイルスのワクチンや助成金に関する問い合わせが急増し、その対応が追いついていない状況です。
また、問い合わせ件数の急増だけでなく、それにともなうミスも多発。問い合わせしてきた人を待たせてしまうなどの悪循環に陥ってしまっているようです。
これら課題を解消するために、24時間365日対応可能なチャットボットが注目を集めています。
<事例あり>チャットボットは自治体にどのように導入されている?

続いて、チャットボットの自治体への導入事例を紹介します。
ここでは、紹介する事例を「問い合わせ窓口」「観光案内役」「ヘルプデスク」という、自治体ならではの3つの業務の切り口に分けてみました。
それでは早速、チャットボット導入でどのような効果があったのかみていきましょう。
自治体の住民からの問い合わせ窓口として
自治体と住民をつなぐ、最も一般的な業務といえば「問い合わせ窓口での対応」ではないでしょうか。問い合わせ窓口では、暮らしに関連するさまざまな疑問や悩みを解決、またさまざまな手続きを行うことができます。
そんな住民の暮らしには欠かせない業務ですが、人手不足の影響も大きく、問題の解決策を模索している自治体も多くあります。問い合わせ窓口業務にチャットボットが導入されると、どのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは、チャットボットを問い合わせ窓口業務で活用している「松山市役所」と「川崎市役所」の事例をご紹介します。
松山市役所×チャットボット
松山市の市民相談課は、日常生活で生じる疑問点や不明点、困りごとの解決のサポートが主な業務だそうです。書類の提出に関してから市内で起こるさまざまな問題など、相談内容もさまざまで、対応に時間がかかることも珍しくないそうです。
そのため、よく問い合わせのあるものはFAQページを用意して対応しようとしました。しかし、FAQページのユーザビリティが悪く、住民の方からの評判はいまいちで、また問い合わせ業務も減らないため、改善策が必要でした。
そんな松山市役所の課題を打開するために導入されたのが、チャットボットです。チャットボットであれば、使いにくいFAQページと異なり、必要な情報をすぐに見つけることができます。
チャットボットの導入により、繁忙期の問い合わせ数は大幅に削減され、職員の業務効率化に向けて大きく前進できました。
川崎市役所×チャットボット
川崎市役所ではより効率的な対応業務の実現と、子育てで悩む市民の利便性の向上が課題となっていました。
子育てに関連する質問は、市役所に数多く寄せられます。
そこで、チャットボットを導入し業務の効率化と市民の利便性向上を図りました。
川崎市役所では、今後は蓄積した問い合わせ情報の分析を行い、想定外の質問があった場合にどう答えるかなど、チャットボットが的確な答えを引き出す性能を高めていきます。
さらには英語や中国語など、複数の外国語にも対応していく予定です。
和気町役所×チャットボット
岡山県南東部に位置している和気町では、年々進んでいる深刻な人口減少を食い止めるためにさまざまな施策を行ってきました。その取り組みを通じて、移住に関する問い合わせが少しずつ増えていったそうです。
一方で、限られた人数の職員が対応していたこともあり、業務負荷がかかったり、対応漏れが生じたりする課題も発生。そこで、業務効率化のためにAIチャットボットを導入し、業務効率化を図りました。
導入したAIチャットボットで24時間の受付が可能になっただけでなく、移住希望者の声もログとして蓄積できるようになり、業務効率化とユーザビリティ向上に役立つデータ収集も可能になったそうです。
導入一か月後には問い合わせ件数が従来比の166倍にも達し、質問のおよそ2/3は開庁時間外に行っているという、新たな気づきも発見できました。
自治体の観光案内役として
自治体の大きな収入源といえば、観光収入です。
そんな観光に関する疑問点や不明点を解決するのが、観光案内役です。昨今では国内の観光客に加えて外国人への対応も求められ、職員への負担も高まっています。
観光案内役の業務をチャットボットに任せると、どのような効果が得られるのでしょうか。ここでは、「福井県永平寺町」が観光案内役としてチャットボットを導入した事例をご紹介します。
福井県永平寺町×チャットボット
永平寺町には年間で約100万人もの観光客が訪れます。観光案内所の整備が不十分だったことが課題でした。さらに永平寺町は、海外での禅文化の広がりから海外からの注目も集まっており、外国人観光客にも対応できる観光案内所を設置することが求められていました
そこで、永平寺町では観光案内に特化した多言語対応のチャットボットの導入に踏み切りました。日本語・英語・中国語・韓国語などで、永平寺町の観光案情報が簡単に得られるチャットボットを、観光案内所に設置しました。
このチャットボットの導入は、人件費と比べるとランニングコストを大幅に抑えられ、外国人からの満足度の向上にもつながっています。
明智光秀AI協議会×チャットボット
2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公である明智光秀のゆかりの地である、岐阜・滋賀・京都・福井をはじめとする14の自治体は、明智光秀に関する人物や地名に関する会話、観光案内、謎解きなどを楽しめるサービス「明智光秀AI協議会」の運営を開始しました。
サービス開始当初は約4,000パターンの会話が登録されていましたが、さまざまな問い合わせ・質問内容を学習することで、現在は10,000パターン以上の会話に対応できるそうです。特にLINEで楽しめる謎解きが人気で、明智光秀との知恵比べや光秀ゆかりの地に関するコンテンツなどが、多くの人に親しまれています。
自治体のヘルプデスクとして
社内の潤滑油のような役割を担うヘルプデスクの業務でも、チャットボットは導入されています。
ヘルプデスクでは、住民の方からの問い合わせに加えて、社内の関連部門から各種トラブル対応も行います。幅広い専門的な知識が必要で、担当者への負荷も高い業務です。そんな職場にチャットボットが導入されるとどんな効果があるのか、「大村市役所」の導入事例を見ていきましょう。
大村市役所×チャットボット
長崎県大村市役所では、職員が業務で膨大な情報を管理するとともに、住民への対応を迅速に行うことへの負担が、年々増加していました。財政部門や電算部門などでは他課からの問い合わせが多く、対応に時間を費やしていることが大きな課題とされていました。
そこで大村市役所では職員の知識面でのサポートや、他課からの問い合わせ対応時間の削減などを目的に、チャットボットを導入しました。まず真っ先に、各課の業務マニュアルや、よくある問い合わせなどをチャットボットに学習させました。
チャットボットの導入により、職員の知識サポートと他課からの問い合わせ対応時間を削減できるため、大幅な業務効率の改善が期待されています。
埼玉県庁×チャットボット
埼玉県庁では、システムやデバイス数の増加にともなう問い合わせ件数の急増、および対応リソースの不足に悩んでいました。特に、新規採用者の入庁や職員の異動がある年度初め、確定申告時期の年度末といった繁忙期には、業務系システムの操作方法や異動に関する入力作業に頭を悩まされ、対応する職員は一日中操作方法の説明に明け暮れることもあったそうです。
そこで、平成30年度の重点施策分野として「スマート社会へのシフト」をテーマに、県庁のあらゆる事業にチャットボットを導入しました。
その結果、電話による問い合わせへの対応稼働数を減少することに成功し、現在も積極的にシステムの導入を検討しています。
チャットボットを自治体に導入すると"ココ"がいい!

最後にチャットボットの特に優れた3つのポイントを紹介します。
すでに多くの自治体で大活躍中のチャットボットですが、自治体へのチャットボット導入で期待できる変化を改めて復習してみましょう。
24時間365日対応できる
チャットボットは、自動で動くプログラムです。そのため、人のような活動時間の制限はなく、24時間365日住民からの問い合わせに対応可能です。
早朝や深夜など、本来であれば受け答えが難しい時間帯でも、チャットボットがあれば人に代わって自動で対応してくれます。日中は忙しいサラリーマンの方も、時間に拘束されずに自治体に問い合わせできるようになります。そのため、チャットボットの導入によって住民の利便性が大きく向上するでしょう。
注意点としては、チャットボットの導入には、一定の準備や設定が必要だということです。急にチャットボットの対応範囲を広げようとしても限界があるため、ゆとりを持ってシナリオ設計や設定を行うようにしましょう。
人手不足の救世主になる
人手不足の影響でチャットボットが自治体に導入されていると、本記事の冒頭でお伝えしました。
チャットボットの活用に成功すれば、人手不足の解消も十分に期待できます。
問い合わせ対応業務は、時間も手間もかかりますが、人手不足の影響から他の業務と兼任している職員の方も多いでしょう。チャットボットを導入すれば、住民からの問い合わせを一定数削減することができるため、職員の方の負担を軽減することができます。
また、問い合わせの数が減ることで、一つ一つの対応をより丁寧に行えるようになるでしょう。
多言語に対応できる
自治体のホームページや施設を利用するのは、日本人ばかりとは限りません。チャットボットの導入事例でも紹介しましたが、近年は外国人旅行者も増えています。人気の観光スポットに行くと、外国人観光客数に驚いたこともあるはずです。さらには、外国からの移住者も年々増加しています。
そうした影響もあり、自治体では多言語で対応できる力が必要となっています。
多言語に対応したチャットボットを導入すれば、外国人観光客・外国人の住民の方の対応ができるようになります。多言語を使いこなせる職員を新たに採用する必要もなくなり、長期的に考えるとコストを削減できます。
英語・中国語・韓国語をはじめ、タイ語・イタリア語・ドイツ語・フランス語など20ヶ国以上の言語に対応できるチャットボットもあります。チャットボットがあれば、言葉の壁で悩まされることはもうないでしょう。
自治体でチャットボットを導入するときのポイント
ここからは、自治体でチャットボットを導入する際のポイントについて解説します。
現在導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
導入目的を明確にする
チャットボットを導入する際に、まず導入目的を明確化することが重要です。
現在、チャットボットツールは数多くリリースされていますが、ツールによって搭載されている機能がさまざまです。
例えば、よくある問い合わせ程度の、簡単な内容に対応できればいいのであれば、シナリオ型チャットボットを導入するといいでしょう。また、より複雑な質問にも対応したい、より自然な会話を実現し、話題を集めたいなどであれば、AI型チャットボットを選択する必要があります。
このように、導入する目的や改善したいものによって、チャットボットに求める機能も異なります。導入後にツールの効果を最大限発揮できるよう、まずは導入目的を明確に定めましょう。
ちなみに、導入目的を定めるのと同時に、ある程度の数値目標を定めておくことも大切です。導入後にどれだけの効果を得たいのか、そして実際の運用を経てどれだけの効果が得られたのか、振返って確認できるようにしておきましょう。
セキュリティを重視する
次におさえておきたいのが、セキュリティ性能です。
利用用途にもよりますが、問い合わせ業務では顧客情報の照会を経て、問題を特定するような場合も少なくありません。かりに対顧客ではなく、社内イントラなどにチャットボットを活用する場合であっても、社内情報を取り扱うこともあるでしょう。
こうした場合、チャットボットのセキュリティが脆弱だと、顧客情報・社内情報が流出してしまう可能性もあります。一度情報流出を起こしてしまうと、会社の信用力低下、ひいては売上の減少にも影響しかねません。万全を期すためにも、堅牢性の高いサービスを選びましょう。
必ず職員がテスト運用を行う
忘れてはいけないのがテスト運用です。チャットボットツールの中には、無料版や無料トライアル期間を設けているものもいくつかあります。
実際に導入してみて、運用の効果が出ているか否か、操作性などに問題がないかどうかなど、実運用に足るものであるかどうか、職員が事前に必ずチェックするようにしましょう。
まとめ
今回は、チャットボットを導入する自治体が増加している理由について詳しく紹介しました。
チャットボットへのニーズが高まっているのは、少子高齢化といった社会背景とも強くリンクしていると分かっていただけたのではないでしょうか。
また問い合わせ窓口・観光案内役・ヘルプデスクといった自治体のメイン業務にて実際のチャットボットの活用事例も紹介しました。
チャットボットは24時間365日の稼働が可能で、多様な言語にも対応することができます。チャットボットを有効活用することで、自治体の仕事の常識は大きく変わるはずです。
本記事が自治体のチャットボット導入のきっかけになれば幸いです。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。