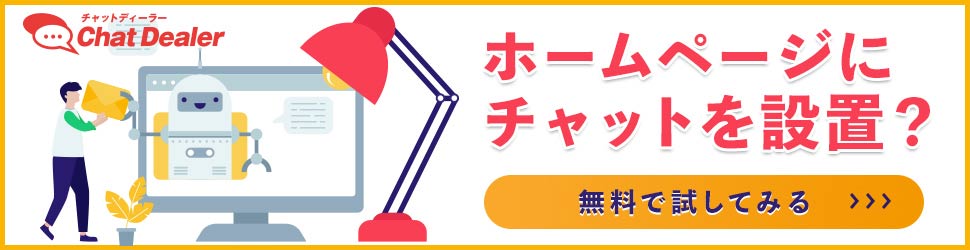チャットボットと医療の相性は?人材不足問題と患者にメリットあり!

深刻な超少子高齢化に突き進んでいる日本において、すぐ目の前の「2025年問題」は医療の現場にとても大きなインパクトを与えると考えられます。
医療の現場が圧迫されてしまうことに何か対策はないか、チャットボットが役に立つのでは、と調べてはいませんか?
医療現場を支える技術は多くありますし、組織内外の情報をうまく循環させる仕組みのうち、チャットボットが担うテリトリーは思いのほか広いものです。
今回は、
- チャットボットが院内業務効率化に役立つ事例
- 患者向けFAQ・予約に役立っている事例
- 医療現場で必要なチャットボットに関する考え方
について幅広くご紹介いたします。
ぜひ、少し時間を作ってでも最後までお読みください。
読み終える頃には、医療現場にチャットボットを導入する意義がおわかりいただけることでしょう。
チャットボットは医療現場でどう役立つ?
チャットボットは多くの業界・業種で導入が進んでいますが、近年では医療機関においても導入が進められています。
医療の分野とチャットボットは関連性が無い印象を受ける方もいるかもしれませんが、医療機関ではビジネスの分野と同じように予約・受付・問い合わせ対応といったさまざまな業務を行う必要があります。これらの業務をチャットボットに代替することで、医療機関においても大幅な業務改善が可能です。
多くの企業が業務効率化・業務自動化・業務負荷軽減・顧客利便性向上・顧客満足度向上といった目的でチャットボットを活用しているように、医療機関でも同等の効果を期待することができます。
多くの医療機関では人材確保の困難による人材不足や業務負担増が問題となっているため、むしろビジネスシーン以上にチャットボットが活躍する余地があると言っても良いでしょう。
チャットボットとは
IT・Webに馴染みの無い方は、チャットボットについて分からない方もいるのではないでしょうか。以下に、チャットボットについて簡単にご紹介します。
チャットボットとは、「チャット」と「ボット(ロボット)」を組み合わせたワードで、Webサイト・Webサービス・SNS等に設置することで、さまざまな質疑応答に自動で対応できるシステム・プログラムのことを言います。
PC・タブレット・スマホ等さまざまな端末上で動作させることが可能であり、近年では幅広い業種・業界で活用が進められています。
チャットボットの導入で改善できる医療現場の課題
チャットボットは多くの業界・業種で導入が進められていますが、医療現場においてもチャットボットを導入することでさまざまな課題を解決することができます。いくつか例をまとめました。
医療現場スタッフの人材不足
多くの医療機関では受付スタッフの人員不足に悩まされており、現在勤務しているスタッフは人員不足の影響で業務負担が増えたり対応の遅れが生じたりしています。
チャットボットは、予約・問診・問い合わせ対応といった受付業務の一部を代替させることができるため、慢性的な人手不足の解消に役立てることができます。業務量の低減・問い合わせ数の減少により、現在負担を抱えているスタッフの負担も軽減することが可能です。
また、業務効率化・業務負荷低減によりリソースを解放されたスタッフは、より重要な業務や人の手でしか行えない業務に集中することもできます。
ノンコア業務の肥大化
医療機関の受付スタッフが抱える業務は、受付業務・会計業務・処方箋発行といった医療機関運営に必須の業務だけでなく、対面や電話での問い合わせ・質問の対応まで多岐に渡ります。後者のようなノンコア業務は、必須では無いものの病院の信用や評判に関わるため、無視するわけにはいきません。
このような医療機関のノンコア業務の問題点は、いつのまにか肥大化して受付スタッフのリソースを圧迫してしまうため、本来行うべきコア業務を阻害する点にあります。
チャットボットは、受付スタッフのリソースを奪う問い合わせ・質問の対応の多くを代替することができるため、受付スタッフは必須の業務や重要度の高いコミュニケーションのみに集中することができます。
また、受付スタッフが重要な業務に集中することで、患者さん全体に対する対応品質も向上させることが可能です。
患者の待ち時間増大
上記でご紹介した受付スタッフの人員不足やノンコア業務の肥大化は、受付業務の停滞により患者さんの待ち時間を増大させる大きな原因となります。医療機関の予約時・受付時・会計時において、長い時間待たされて辟易した経験は誰もがあるのではないでしょうか。
また、患者さんの待ち時間が長い原因には、明確な症状・病状の患者さんだけでなく、少し体調が悪いといった患者さんや病気に対する不安や心配から来る患者さんが混じっていることも理由として挙げられます。医療機関としては、当然病気の可能性がある患者さんは診察・診断する必要があるため、対応を断ることはできません。
チャットボットであれば、上記のような患者さんの待ち時間増大の原因に対して、予約・事前問診票・順番待ちカードの発行等、状況に応じたさまざまな対策を講じることが可能です。受付スタッフの業務効率化・業務負荷軽減・予約の整理により、多くの医療機関が抱える待ち時間の課題を効率的に解決することができます。
チャットボット導入で院内業務を効率的に

チャットボットは、医療業界の人手不足や院内業務の効率化に大きく役立ってくれます。
ここでは、4つのツールがどういった役割を果たしているのかをご紹介します。
患者のフォローアップ【ドクターQ】
毎月同じ薬を出すような慢性期にある患者に関しては、「ドクターQ」というチャットボットが有効です。
ドクターQは「LINE」をベースに、次のようなことを行います。
- 患者の求めに応じ、電子カルテや処方薬の一覧を提示
- 医師はドクターQを通じ、患者の状態を知るためメッセージを送る
- 患者は病状や服薬に関しての自動問診に返信、問題があれば来院を促される
この仕組みは、持病が「当たり前」になりがちな慢性期の患者さんにとって、とても重要なものです。
医師としても、「決して良くなったとは思えない患者さんが来院しないことへの不安」「副作用など何かの問題があったのではないかという疑問」を解消できる一手となることでしょう。
医薬品データに素早くアクセス【CAIWA/アズトリート】
近年のジェネリック医薬品へのシフトに伴い、現在薬剤師の役に立つチャットボットが多く活用されています。
その中でも代表的なのが、「CAIWA(かいわ)」や「アズトリート」です。
いずれも次のような問題を解消してくれます。
- ジェネリック医薬品が多すぎて探しきれない/時間がかかる
- パッケージが現行品かどうか(使用期限内かどうか)がわかりづらい
- 製品FAQにたどり着けない
上のふたつはAI型チャットボットで、薬に関する情報を製薬メーカーのデータベースから直接ピックアップできたり、必要に応じて資料請求やMRへの連絡ができたりします。
高齢化により患者さん一人当たりの処方薬が多くなる傾向や、ジェネリック医薬品の増加に対応するため、このような工夫はなされて当然のことかもしれません。
問い合わせや予約の電話による時間ロスを予防【チャットディーラー】
医療現場の業務の中でも、患者さんからの問い合わせや予約といった「フロント業務」には意外にも多くの時間がとられてしまいますが、その面をカバーしているのが「チャットディーラー」です。
チャットディーラーは次のような問題を解決してくれます。
- 診療科や診察内容に関する問い合わせへの回答
- 診療時間や休診日など基本的な問い合わせへの回答
- 予約方法(電話番号)の提示
患者さんは24時間365日、いつでも診療にまつわる回答を得ることができます。
パソコンやスマートフォンを使いこなしている患者さんなら、電話を回避してくれるでしょう。
本当に人が対応しなければならない問い以外は、チャットディーラーに任せることができます。
代表番号の電話が鳴り続けるといった状況を回避できるのが大きなメリットです。
スタッフの悩みを可視化、相談しやすい体制に【emol work】
医療現場での情報共有の中で、できれば時間をかけずにさっと済ませたい、しかしながらとても重要なものに、メンタルヘルスケア(悩み事のピックアップ)があるでしょう。
それに対応しているのが「emol work」です。
emol workは、次のような課題解決に役立ちます。
- 匿名で悩みを相談できる(AIチャットボットによる簡易的カウンセリング)
- 職員のメンタルヘルス状況の把握
- 「悩みボード」に付箋を貼り付けるように悩みを投稿、他のメンバーはコメントを返せる
なかなか言い出せない人間関係の悩みを吐き出すことができますし、実際に公開してもいい悩み事に関してはヒントやアイディアを求めることもできます。
何らかの理由で現場がひっ迫しギスギスしてしまう、なかなか本音が言い出せない、チームワークが崩れていく、組織全体として個々人の状況を把握できない…。
そんな状況が見え隠れするのであれば、emol workの導入を早めに検討するとよいでしょう。
院内のさまざまな情報をひとつに【Bot MD】
医療従事者は限られた時間内で多くの業務をこなさなければならず、いかに無駄な時間を省いて時間効率を上げるかが重要です。BotMDは、医療従事者の時間節約を目的とした、AIチャットボットです。
BotMDでは、次のような課題を解決して忙しい医療従事者をサポートしてくれます。
- 医療機関内の情報を統合してアクセス時間を短縮
- 電話・イントラネット不要でスマホ一台で重要な情報へアクセス
- 24時間365日いつでも必要な情報へアクセスできる
情報が統合されていない従来の医療機関では、医療従事者は各方面の関係者に電話をかけたり、最寄りの端末を探してイントラネットにアクセスしたりといった方法で、必要な情報を集めることができます。
BotMDは、手元のスマホ一台で一元化した情報にアクセスできるだけでなく、AIによるアシスト機能も搭載。情報収集に要する時間を大幅に削減して、医療従事者にゆとりをもたらしてくれます。
歯科専門のチャットボット窓口【Dentabot】
Dentabotは、Webサイトに設置して会話を行うことで、閲覧者の利便性・満足度向上を図り、来院を促す歯科医院専用のチャットボット窓口です。
Dentabotでは、歯科医院の以下のような課題を解決に役立てることができます。
- Webサイト閲覧者と会話することで離脱防止・来院促進に繋げる
- Webサイト閲覧者の利便性・満足度向上
- 受付対応業務の負担軽減
Dentabotの特徴は、Webサイト閲覧者からのアクションを待つだけでなく、こちらから積極的に話しかける点にあります。蓄積した会話データを基に適切な案内を行うことで、閲覧者の離脱防止・来院促進に高い効果を発揮することが可能です。
また、Dentabotには受付スタッフが行う問い合わせ対応を行うことも可能で、質疑応答を登録しておくことで電話対応の回数・負担を軽減することもできます。
チャットボット導入で患者さんも安心

チャットボットの導入は、何も医療の現場の悩みを解消するだけではなく、患者さんの不安にも対応してくれます。
「今病院に行くべきか」「この症状は何を疑うべきか」はもちろんのこと、患者さんは審美歯科や美容外科といった自由診療に関しては多くの疑問を持っているからです。
事前にしっかりと情報を取得できる状況を作っておけば、不安感をぬぐえますし、病院(医院)のアピールにもつなげられます。
ここでは、患者さんの不安を払しょくするチャットボット導入事例やツールについてご紹介しましょう。
受診すべきか迷ったときに【LINEヘルスケア/埼玉県無料救急相談サービス】
休日や夜間に痛みや発熱といった状況に遭遇すると、患者さんはとても不安になります。
そのようなケースに対応している事例が「LINEヘルスケア」「埼玉県無料救急相談サービス」です。
いずれも、患者さんの次のような問題を解消する手助けをしてくれます。
- この症状はどの病院にかかるべきか
- 急いで病院に駆けつけるべきか
- 疑わしい病気は何か
- 今すぐ診てもらえる病院(医院)はどこか
特に一人暮らしの方、初めての子育てで不安な親御さんには、心強いサポートができるでしょう。
状態によっては救急車を呼ばなければならないことも想定されます。
「いつ・どこに相談すべきか」といった窓口案内ができれば、それだけで不安も軽くなるというものです。
診療時間の問い合わせや予約を入れたいときに【BOTCHAN EFO】
完全予約制の病院(医院)の場合、患者さんは予約そのものにハードルの高さを感じてしまうこともありますが、それを解消するのが「BOTCHAN EFO」です。
空き状況確認や予約のため、日中仕事の合間にオフィスから電話をかけること自体難しい患者さんもいるのが現状でしょう。
チャットボットは、その心理的障壁を解消する役割も担います。
- 予約すべき病院(医院)の空き状況を確認したい
- 電話なしでスマートフォンやパソコンから予約をしたい
- 人に知られず連絡をしたい
このような患者さんの悩みを解決するために、チャットボットを導入する必要があるかもしれません。
患者さんの心理的ストレスを取り除くのも、正しい医療に導く一つの方法です。
審美歯科/美容整形などの疑問解消に【チャットディーラー】
審美歯科や美容外科は自由診療ですので、患者さんにとって費用や治療内容がわかりづらいという点が大きな問題となりますが、「チャットディーラー」がその点をサポートします。
自由診療に対し、患者さんは多くの疑問を持っています。
- どういった治療ができるか知りたい
- 費用を知りたい
- 治療方法を詳しく知りたい
- 何回通院しなければならないのか知りたい
自由診療は、ときにデリケートな問題を含むことがあります。
ときにありがちな「電話しづらい」「他の人に知られたくない」という情報に、気軽にアクセスできる方法がチャットボットです。
また、心理的障壁を取り除くことがプロモーション活動となり、結果としてより具体的な問い合わせや予約が増えることも期待できます。
医療現場でのチャットボットに求められること

医療現場でチャットボットを活用する際には、医療分野特有の事情や業務特性を踏まえたうえで、チャットボットの導入・運用を行うことが重要です。特に、患者さんが利用するチャットボットを行う際には、医療へのリードで不備を無くすことはもちろん、分かりやすさや丁寧さも重視する必要があります。
ここでは、医療現場でチャットボットを導入・運用する際に求められること・留意しておくべきことをご紹介します。患者さんにとっても医療従事者にとってもメリットのあるチャットボット活用を行うためにも、ぜひ参考にしてみて下さい。
FAQ作成時に難しい言葉を使わない
医療現場で活用するチャットボットにおいてまず重要なポイントは、専門用語や難解な言葉による表現を用いずに、一般の患者さんでも理解できるような分かりやすい言葉でFAQを作成することです。
同じ症状・病状について表現する際にも、一般の患者さんと医療従事者では用いる言葉が異なることは周知の事実です。対面の問診・診察であれば、会話のなかで意図を汲み取ったり言葉の言い換えを行ったりできますが、チャットボットではそのような調整はできません。
もしチャットボットのFAQが専門用語や難解な言葉で作成されていると、患者さんは内容を理解できず伝えたいことも伝えられない、不親切なチャットボットができあがってしまうでしょう。
チャットボットのFAQは利便性や利用率にダイレクトに影響します。分かりやすい表現でFAQを作成することはもちろん、実際にテストやシミュレーションを行って、使用感についてもチェックしておくようにしましょう。
操作がわかりやすいシンプルなUIにする
チャットボットは、利用者層を想定して誰もが使いやすいUIを設計することが重要です。医療機関を利用する年齢層は高齢者層が非常に多くITツールに馴染みの無い方も多くいます。チャットボットを導入したものの、操作が難しく利用されなかったり操作方法の問い合わせが増えたりしては、何のために導入したのか分からなくなってしまうでしょう。
そのため、医療現場でのチャットボットは、特に分かりやすさ・使いやすさを重視したシンプルなUIを搭載することが非常に重要です。また、同時に利用者のニーズを満たす高度な機能を搭載するという、難易度の高い要件が求められます。
チャットボットは、ベンダーによってベースとなるUIが大きく異なります。医療現場での活用を想定する場合は、予めシンプルで使いやすいチャットボットを選定しておくと、UIの設計もスムーズに行えるためおすすめです。
時間軸を考慮に入れたシナリオ作り
医療機関を受診する患者さんは、例外を除くと一般的に、「予約>来院>受付>受診>会計・処方箋発行」といった流れを辿ります。そのため、チャットボットのシナリオを作成する際には、患者さんが辿る時間軸を考慮に入れることが非常に重要です。
医療機関を利用する流れに沿ったシナリオが提示されることにより、患者さんはよりスムーズに必要な情報を得ることができます。反対に、時間軸を無視して情報が詰め込まれていては、使い勝手の悪いチャットボットとなってしまうでしょう。
チャットボットは、利用者の視点に立って設計することが、利便性・満足度を向上させるポイントです。医療機関のチャットボットを作成する際には、時間軸については必ず意識しておきましょう。
セキュリティを万全に
医療現場で活用するチャットボットは、患者さんの病状・病歴といった極めてデリケートで重要な個人情報を取り扱います。万が一情報漏洩事故を起こしてしまうと、医療機関の信用・評判は失墜してしまうため、チャットボットの活用にあたっては万全のセキュリティを構築することが必要不可欠です。
ただし、セキュリティ強化ばかりを重視してしまうと、チャットボットの利便性を損ねてしまう場合があります。そのため、セキュリティを構築する際には、ユーザビリティを両立できる仕組みを模索することが重要です。
また、情報セキュリティに求められる要件は日々変化していくため、一度セキュリティを構築して終わりではなく、定期的なリスクアセスメントや必要に応じたアップデートを行うことも忘れないようにしましょう。
まとめ
今回は、医療現場においてのチャットボット活用例や、それによってもたらされるメリット、チャットボット導入においての注意点についてご説明しました。
チャットボットは、意外にも医療の現場で大きな役割を果たしてくれます。
チャットボットは、今後、組織内での情報共有はもちろんのこと、患者さんにとってのサポート役としても存在感を増していくでしょう。
もしもチャットボット導入にご関心がありましたら、「チャットディーラー」をご検討ください。
チャットディーラーは、運用開始までの時間が短くて済むという特徴があります。
また、導入するまで、そして導入してからも専任スタッフがサポートいたします。
安心してご利用いただける仕組みが揃っていますので、ぜひお問い合わせください。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。