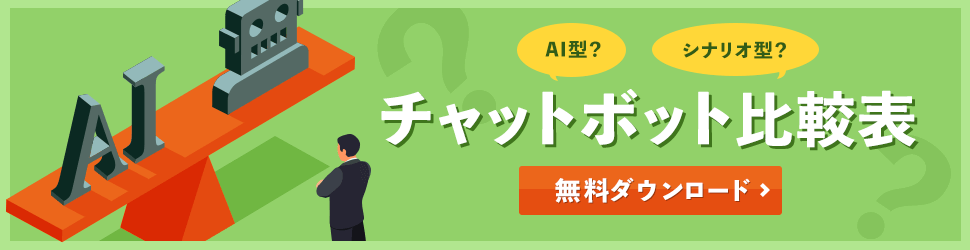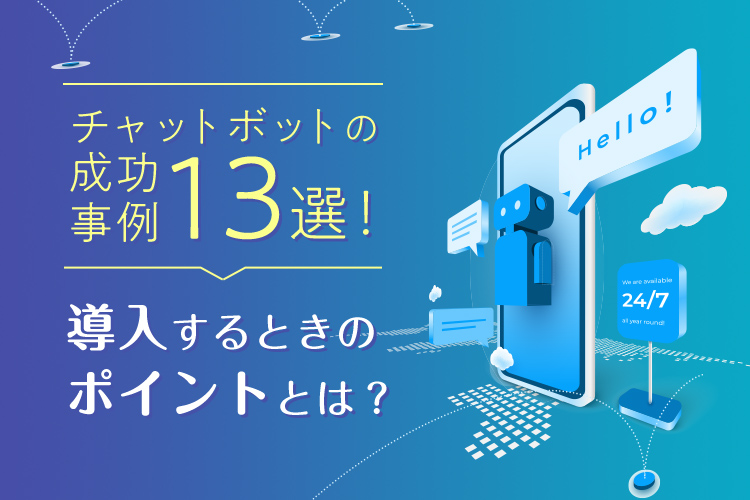注目の「チャットサービス」はどんな企業に導入されている?

業種を問わず、多くの企業で導入されている「チャットサービス」。さまざまな場面で見かけることも多くなってきました。
企業からの注目が高まっていることが分かりますが、「チャットサービス」は具体的にどのような企業に導入されているのでしょうか。また、どのようなシーンで活用されているのでしょうか。
気になる「チャットサービス」について、さまざまな企業の導入事例と共にご紹介します。
おすすめのチャットボットツールはこちら
簡単に導入できるおすすめチャットサービスの紹介はコチラ
そもそも「チャットサービス」とは?
チャットサービスとは、Webサイト・Webシステム・SNS等にチャットウィンドウを設置して、ユーザーと対話方式でリアルタイムのコミュニケーションを行なうことができるサービスです。社内ヘルプデスクとして社員からの問い合わせ対応に活用したり、Web接客ツールとして顧客対応を行なったりすることができます。
主な活用シーンには、以下が挙げられます。
■社内での活用シーン
- 社内用ヘルプデスク
- FAQのサポートツール
■社外での活用シーン
- ECサイトでのWeb接客
- 企業サイト等でのカスタマーサポート
- 問い合わせ・申し込みフォームの代替ツール
チャットサービスを導入することにより、業務効率化・業務負荷軽減・顧客満足度向上・ユーザー情報の蓄積や分析といったさまざまなメリットが得られるため、現在では多くの業界・業種で活用が進められています。
チャットサービスの仕組み
チャットサービスには大きく分けて、チャットボットのような自動対応を行うサービスと、オペレーターがチャットツールを用いて対応を行う有人対応のサービスの2種類があります。両者の併用・切替が可能なサービスもあります。
以下に、それぞれのチャットサービスの概要・特徴・仕組みについて解説します。
自動対応のチャットボット
チャットボットとは、Webサイト・Webサービス・社内ポータル等に設置して、社内外から寄せられる問い合わせ対応に自動で対応できるツールのことです。ユーザーから得た情報を基に、的確なメッセージを返す仕組みとなっています。具体的には、以下の2ステップを踏襲して返答を導き出します。
ステップ1:ユーザーが入力した情報からキーワードを抽出・分析する
チャットボットのシステムは、ユーザーが入力したテキスト・選択肢といった情報からキーワードを抽出して、適切な返答を行うための情報をデータベースから探し出します。
システムが抽出するキーワードの精度により返答の的確さも変わってくるため、キーワード抽出精度は非常に重要となります。
ステップ2:データベースの情報を判別してユーザーが求める返答を出力
抽出したキーワードをもとにデータベースに格納された情報を検索し、ユーザーが求める情報に対する返答をアウトプットします。
返答の精度を高めるためには、データベースの情報の質や検索の精度が重要となります。
チャットサービスにより性能や機能は異なりますが、高い効果性・有用性を得るためには、このようにシステムのスペックが重要となります。基本的には、AIが搭載された製品や自動学習機能が搭載された製品を選ぶことがおすすめです。
有人対応のチャットツール
有人対応のチャットツールは、顧客や社員からの問い合わせに対して、オペレーターがテキストでの対応を行うチャットのことです。
Webサイト・SNS等に設置されたチャットウィンドウから、以下の手順で対応が行われます。
- 顧客から問い合わせが発生
- オペレーターに自動で通知
- 通知を受けたオペレーターが対応
有人対応のチャットツールは、難しい問い合わせや人の感情を汲み取った問い合わせなど、チャットボットの自動対応ではカバーできないきめ細やかな対応が求められるシーンで活用されています。
ただし、専任のオペレーターを常駐させておく必要があるため、自動対応のチャットボットと比べて運用リソース・運用コストは高くなります。24時間有人対応を行うのは現実的では無いため、一般的には以下のような方法で運用されます。
- チャットボットで対応できない問い合わせのみ有人チャットに切り替える
- 営業時間内のみ有人対応を行い、営業時間外はチャットボットに切り替える
チャットボットが発達した現代においてもすべての問い合わせをカバーできるわけではないため、チャットサービスを導入する際には必要に応じて有人チャットの活用も検討する必要があります。
チャットサービスが注目されるようになった背景
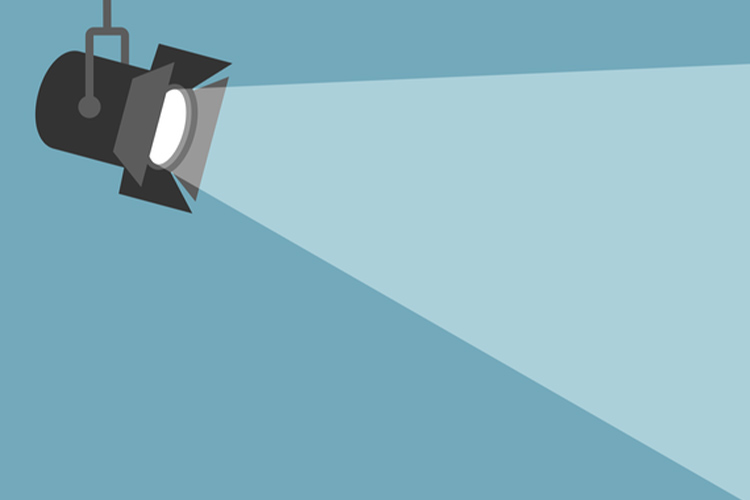
多くの企業から注目される「チャットサービス」。注目を集める理由はどこにあるのでしょうか。
その背景には、企業の抱えるさまざまな課題が関係しているのです。
人手不足の影響
近年、求人倍率が高くなり、売り手市場が続いていることはみなさんご存知でしょう。求人の数が求職者の数を上回っている状況のため、他企業との人材確保争いや、既存の人材の流出が企業にとっては大きな課題となっています。
慢性的に「人手が足りない」状況が続いている企業も少なくはありません。
企業の働き手に代わり、問い合わせ対応業務を行うチャットサービスが注目される背景には、このような状況が影響していると考えられるでしょう。
問い合わせ窓口が電話とメールの場合、すべての質問に対してスタッフが回答する必要があります。しかし、チャットボットを設置すれば、一定数の問い合わせに関してはユーザーに自己解決を促せるため、対応時間の削減につながります。
人手不足に悩む企業にとってチャットサービスは、業務の大きな手助けとなります。
業務効率化推進の影響
多くの企業が人材確保に悩まされている状況もありますが、「働き方改革」もまた、チャットサービスが注目される背景のひとつです。
長時間労働の解消を目指す「働き方改革」によって、多くの働く人々が短い時間で効率よく業務をこなすことが求められるようになりました。長時間に及ぶ業務への拘束が解消される分、働き手にとっての環境は改善されつつあるといえますが、企業側からすると「今まで誰かが行なっていた業務」をどうするのか、という課題も残されています。
一人ひとりの労働時間が短くなることによって、これまで少人数で対応していた業務をさらに細かく分解して、より多くの人材を確保する必要性も出てきます。
そこで「今まで誰かが行なっていた業務」をAIやチャットサービスが代わりに行うという解決策が注目されるようになったのです。
チャットコミュニケーション普及の影響
チャットサービスが注目されるようになった背景には、テクノロジーの発展や利便性の追求といったビジネス環境の変化が影響しているだけはなく、LINEをはじめとしたチャット系SNSが社会全体に普及したことにより、チャットコミュニケーションが一般化したことも大きな要因として挙げられます。
私生活においてチャットによる手軽でスピーディーなコミュニケーションを行うことが当たり前となり、メール・電話のようなレスポンスに時間がかかるコミュニケーションツールは徐々に利用率が低下していきました。
ビジネスシーンにおいてもレスポンスの良いチャットサービスが好まれるようになるのは自然な流れであり、企業がこのような状況・環境の変化に対応するためには、顧客対応においても社内でのコミュニケーションにおいてもチャットサービスの導入・活用を進める必要性が高まってきたと言えます。
AI技術発展による影響
AI技術はすでに世の中に多く浸透しています。少し前まで「AI」というと近未来的なイメージを持つ方が多かったかと思いますが、近年AI技術は身近なところでも活用されるようになってきました。AI技術が徐々に発展することによって、今まで人手を割いていた業務を代わりにAIが対応するシーンを見ることも多いのではないでしょうか。
「チャットサービス」でも、このAI技術が使われることが増えています。
全てのチャットサービスにAI技術を搭載しているわけではありませんが、一部ではAI技術を活用し、学習機能を搭載したチャットサービスも登場しています。
テレワークの浸透
新型コロナウイルスの感染拡大により、大規模なコールセンターを設置したりスタッフを集めて業務を行なうことが難しくなり、接触を避けてビジネスを行うためのテレワークが急速に浸透しました。しかし、テレワークには、「コミュニケーションロスの発生」「ナレッジ共有が困難」「マネジメントが行き届かない」といった特有の課題があるため、スムーズに業務を行うためにはインフラ整備が非常に重要です。
そこで多くの企業が注目したのが、チャットサービスの導入です。チャットサービスであれば、遠隔地同士のメンバーでもスムーズなコミュニケーション・ナレッジの共有・マネジメントが可能となります。社内メンバーから寄せられる問題・疑問に対する問い合わせに関しても、オンライン上でスマートに解決を図ることが可能、さらに自動化機能や業務支援機能により、業務効率化・業務負荷軽減にもつながります。
また、社内だけでなくECサイトやWebサービスを利用する顧客に対しても、新たな顧客対応窓口・顧客対応手段としてスムーズな対応やきめ細かな対応が可能となり、顧客満足度の向上に繋げることもできます。
このように、チャットサービスはコロナ禍により大きく変化したビジネス環境のインフラとして注目されており、今後もニーズは高まって行くでしょう。
働きやすさやCX(顧客体験)を重視する企業が増加
従業員満足度を向上させるために働きやすい職場環境を構築する企業や、顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)を重視する企業の増加も、チャットサービスが注目されるようになった背景のひとつです。
働きやすさを示す指標の一つに従業員満足度があります。従業員満足度は「ES」とも呼ばれており、職場環境・働き甲斐・福利厚生・マネジメント等について従業員がどのくらい満足しているかを示す指標です。ESが高いほど企業の生産性・業務効率・人材定着率が高まるなど好ましい影響が期待できるため、近年多くの企業がESの向上に取り組んでいます。チャットサービスを導入すれば、業務の利便性・効率性やコミュニケーションの円滑化を図ることが可能となるほか、業務上の疑問・課題もオンライン上でスムーズに解決することが可能となるため、ESの向上も期待することができます。
一方、顧客体験とは、商品やサービスの物質的や金銭的な価値だけでなく、購入前の販促から購入した後の付加価値までを含めた「顧客が体験する価値」のことを意味します。「Cumstomer Experience」を略し、「CX」とも呼ばれます。
チャットサービスを導入することによって、多くの企業で24時間のリアルタイムで問い合わせに対応できるようになりました。また、公式のキャラクターを作り、そのキャラクターが顧客との会話をしているような仕様にしたり、ゲームの相手をしたりすることで、顧客との新たなコミュニケーションチャネルとする企業も増えています。
サブスクリプション型のビジネスの台頭
昨今、SaaS業界を中心にサブスクリプション型ビジネスが広がりを見せています。サブスクリプション型ビジネスとは、商品やサービスを顧客が使用した量や期間に応じて料金を課す「課金提供型のビジネス」のことを指します。内容や価格の違う複数のプランを用意し、顧客の要望に沿って商品やサービスを提供し、使用した分や期間に応じて課金を行うタイプのビジネスモデルです。
サブスクリプション型のビジネスを拡大していく際には、これまでとは違ったプロダクト改善を意識する必要があります。解約率が高まってしまった場合であったり、商品の内容を変えたりする場合には、顧客の声を拾って改善につなげるカスタマーサクセス部門の存在がより重要になるでしょう。
サブスクリプション型ビジネスでは、解約されずに長期間に渡って利用し続けてもらうことが肝心なので、従来型のビジネスと比べて顧客の声を拾うことがはるかに重要です。顧客の声を拾って改善に活かしていくためには、こうしたチャットサービスを導入することは有効な手段といえます。
チャットサービス導入のメリット
チャットサービスを導入する企業が増えているのは、企業が抱えるさまざまな課題の解決に寄与することができるためです。
ここでは、チャットサービス導入により得られる主なメリットについて解説します。
業務負荷の軽減
有人による対応は、顧客向けの対応を行う場合においても社内向けの対応を行う場合においても、担当部署に大きな業務負荷が掛かります。精神的負担も大きいことから離職を招きやすく、リソース不足・人手不足に陥りやすいという問題もあります。
チャットサービスを導入すれば、チャットボットによる自動対応を行う場合においてもチャットツールによる有人対応を行う場合においても、以下の通り業務負荷を低減することが可能です。
■チャットボット
- 自動対応により有人対応の比率を大幅に低減できる
- 時間を問わずいつでもスピーディーに対応できる
- 常に安定した品質の対応を行うことができる
■有人チャット
- テキストによるコミュニケーションであるため精神的負担が少ない
- 複数の対応を同時に行えるため、業務効率を向上させることができる
- テンプレート等の支援機能を活用することで負担を軽減できる
チャットサービスは業務負荷の解消に最適なサービスであるのが大きなメリット。業務負荷の課題解決を目的に導入を進める事例は増え続けています。
従業員満足度・顧客満足度の向上
チャットサービスは、時間・場所を問わずいつでも素早い対応を行うことができるため、社内での利用においては従業員満足度、顧客対応での利用においては顧客満足度の向上にも貢献できることがメリットです。以下に、それぞれどのように満足度を向上できるのかをご紹介します。
従業員満足度の向上
社内ヘルプデスクの回答が遅れると、問い合わせを行った社員は自身の業務が滞ったり機会損失を招いたりすることから、不満やストレスを抱えてしまいます。
時間を問わずスピーディーな回答を得られるチャットサービスの導入により利便性・効率性を提供すれば、業務の停滞も無くなり働きやすさが増すため、従業員満足度の向上を図ることができます。
顧客満足度の向上
商品・サービスの利用者である顧客は、何か問題があった場合や疑問が生じた場合にはすぐにでも回答を得たいと考える傾向にあります。企業側が電話による対応しか受け付けていない場合、回答を得るのに手間と時間がかかることにフラストレーションを抱えがちです。
チャットサービスであれば、顧客を待たせることなくいつでも即座に回答を行えるため、不満・不安といったマイナスの感情を抱かせることなく、対応の質・レスポンスの良さにより満足度を向上させることができます。
チャットサービスを導入している企業の事例

チャットサービスは、既に多くの企業で社内問い合わせ対応の課題解決に活用されています。実際のどのようなシーンでどのように活用されているのでしょうか。
ここでは、社内問い合わせ対応にチャットサービスを導入・活用している企業の具体的事例をご紹介します。これから導入を考えている方は、ぜひご参考下さい。
社内ヘルプデスクとしてチャットサービスを導入した事例
大京グループは、ライオンズマンションシリーズを筆頭に、マンション開発・分譲・管理・仲介・賃貸と幅広い不動産事業を展開する企業です。グループ内では5.000人を超える従業員が勤務しており、社内ヘルプデスクには月間1,000件以上もの問い合わせが集中。慢性的な業務負荷の高さ・リソース不足といった課題に対処すべく、チャットサービスの導入を行いました。
導入するチャットサービスには、対応品質の高さ・対応の柔軟性といったパフォーマンスを考慮して、AIチャットボットを選定。導入後は約30%もの問い合わせを自動対応させることが可能となり、社内ヘルプデスクの負担は大幅に低減。社内からの対応に追われて社外の顧客対応に追いつかなかったという課題も解決することができました。
チャットサービスの有用性を実感した同社では、今後マンション購入者・入居者等の顧客向けのサポート窓口へのAIチャットボット導入を目指しています。
複数部署の問い合わせ対応にチャットサービスを導入した事例
大手メーカー企業であるB社では、全国各地に複数の支社・部署・部門が点在しており、社内の問い合わせ対応が膨大かつ煩雑であることから、情シス・人事・経理・経費精算等の複数部署にチャットサービスを導入して問い合わせ対応の効率化を目指しました。
特に企業規模が大きいことから業務負荷が高まっていた経費精算部門では、チャットサービスの導入により25,000件近い問い合わせのほとんどを自動対応することに成功。同部門において劇的な業務負荷軽減・業務効率化を実現しました。
また、各部署・各部門での問い合わせ対応の履歴を社内のナレッジ・ノウハウとして蓄積することで、チャットサービスのPDCAはもちろん、社内FAQの整備による情報の集約・業務フローの改善などにも活用。チャットサービス自体の効果だけでなく、ナレッジマネジメントによる企業全体の生産性向上も実現することができました。
現在では複数のチャットサービスを社内ポータルにまとめることで、問い合わせ対応・情報共有の一元化にも取り組んでおり、更なる環境改善・状況改善を目指しています。
よくある質問をチャットサービスで100%自動対応した事例
チャットサービスを活用して社内ヘルプデスクの業務負荷軽減・業務効率化を実現する事例は比較的多くありますが、なかには特定の分野に関する問い合わせを完全に自動対応させることに成功した事例もあります。
大手建設会社C社では、有人での社内ヘルプデスク対応をITツールで効率化しようとしたところ、人的リソースとコストの不足により実現が難しいという課題が発生。チャットサービスの導入により、対応を代替させる戦略へと方向転換しました。
現行のITツールにより稼働させている社内ヘルプデスクのFAQをベースにチャットボットを設定。また、現行のツールへの埋め込みにて稼働させる方式を採用しました。
このような取り組みにより、スピーディーに導入を進められただけでなく、問い合わせの中でもOutlookとTeamsに関するものの対応を全てチャットボットに代替させることに成功。チャットサービスの選定・利用するFAQデータ・稼働環境を工夫すれば、ヘルプデスク業務を完全に代替させることも不可能ではないことを証明した好例です。
社内問い合わせが急増する時期に週2,000件を自動対応した事例
機械・器具等を中心に取り扱う大手リース会社D社では、さまざまなビジネスを展開して多くの品目を扱っていることから、特に繁忙期に集中する社内問い合わせ対応の効率化と、従業員の働きやすさの向上を実現したいという課題を抱えていました。そこで課題解決のために、問い合わせ対応を自動化できるチャットボットを導入しました。
情報の網羅性を重視したチャットボットの導入と全社的な社内周知を行ったところ、平均月400件の問い合わせを自動対応させることに成功。繁忙期にはなんと週に2,000件以上もの問い合わせ対応を処理。問い合わせの件数に依らず常に高いパフォーマンスを発揮できるチャットサービスの有用性・効果性を実感した同社は、他の部門への導入・活用を進める取り組みを推進しています。
ECサイトにチャットサービスを導入した事例①
実店舗やオンラインでアパレルブランドを展開する株式会社オーセンティックでは、自社ECサイトにチャットサービスを設置することで、ユーザーからの問い合わせに「リアルタイムで回答する」ことができるようになりました。
ECサイトを運営していると、ユーザーから頻繁に問い合わせを受ける「送料」や「在庫」についてはチャットサービス上で回答したり、該当情報が記載されているFAQページのURLを送るなどして活用しています。
お客様が問い合わせしたいときに、「その場で」「すぐに」問い合わせできるので、電話よりもリアルタイムな対応を実現できています。
ECサイトにチャットサービスを導入した事例②
日用品やコスメ、家電、医薬品など幅広い品揃えを誇る通販サイト「LOHACO」での導入事例をご紹介します。
LOHACOでは、ECサイト上にAI機能搭載型のチャットサービスを設置し、ユーザーからの問い合わせに対応しています。
注文数の増加に伴い、増え続ける問い合わせの回答効率を改善するために導入しました。
AI機能を搭載しているチャットサービスを導入することで、スモールトークへの対応や時間帯によって回答を出し分けることも可能になりました。今では、チャットサービスで全体の問い合わせ約1/3に対応をしているので、社内での問い合わせ対応の負担軽減に大きく貢献しているといえるでしょう。
また、チャットサービスにキャラクターを加えることでユーザーも親しみやすく、より自然な受け答えを実現しています。
銀行のサイトにチャットサービスを導入した事例
東京スター銀行では、自社サイトにチャットサービスを導入しています。
「最寄の店舗の行き方って?」「取り引きに必要な書類って?」など、ちょっとしたことを気軽に、また夜間や休日でもユーザーが問い合わせをできるようになっています。
導入するまでは、サイト上で情報を探す必要があり、銀行のように情報の多いサイト上では、ユーザーが必要な情報にたどり着くのが難しいことが課題とされていました。そのため、ユーザーが早い段階で離脱してしまう、もしくは電話での問い合わせが増加することが多くありました。
チャットサービス設置後は、ユーザーはトップページからチャットサービスに質問をするだけで回答を得られるようになったため、サイト内で問い合わせ先を探したり、必要な情報が記載されているページを探したりする手間が省けるようになりました。
例えば、住宅ローンの相談をしたい場合は、チャットサービスから問い合わせ内容のカテゴリを選択して進めるだけで、住宅ローンの商品説明ページや相談会の予約などへ誘導してくれます。
宅配業者がLINEチャットサービスを導入した事例
ヤマト運輸では、LINEのチャットサービスを導入し、配達状況の確認や荷物受取日時の変更などができるようになっています。
ヤマト運輸のLINE公式アカウントを追加するだけで、普段利用しているLINE上でのやりとりで問い合わせが完結するので、ユーザーには使いやすく便利でしょう。
「いつ届く?」とトークに送るだけで返信があり、そのままトーク上で再配達の依頼や受取日時の変更までできてしまうのです。
これまでは、ドライバーに直接電話で問い合わせても配達中でつながらなかったり、不在届から荷物番号を確認してHPから再配達を依頼する必要があったことを考えると、とてもスムーズになりました。
問い合わせの際に、語尾に「にゃ」をつけて質問すると、クロネコが猫語で回答してくれるなど、遊び心のあるキャラクターもユーザーに親しみやすさを感じてもらえるポイントです。
チャットサービスの導入事例からわかること

多くの企業がチャットサービスを導入していること、さらにチャットサービスは、業種に関わらず幅広い業界で活躍していることがわかりました。
ここからは、導入事例から読み解くチャットサービスの特徴をご紹介します。
社内ヘルプデスクとしての活用には多くのメリットがある
チャットサービスは顧客向けのサービスが広く普及しているイメージがありますが、外部からは目立たないだけで実際には社内向けに活用されている事例も多くあります。
社内での主なチャットサービスの活用方法としては、情報システム部門がITシステムの問い合わせ対応に活用したり、総務・経理・人事等のバックオフィス部門での社内問い合わせ対応に活用したりといった使い方です。
社内ヘルプデスクでチャットサービスを活用することで、時間・場所を問わずスピーディーな対応が可能となるだけでなく、社員の自己解決を促進できるため、対応部署全体の問い合わせを大幅に代替させたり、特定分野への問い合わせをほぼ完全に自動対応させたりといったことも可能。担当部署が抱えがちな離職率の高さ・心身の不調・業務停滞・リソース不足といった課題を解決することも可能です。工夫次第では、社内ヘルプデスクの業務体制・業務フローを大幅に刷新できるほどのパフォーマンスを発揮できる可能性を秘めていると言えるでしょう。
このように社内ヘルプデスクとしての活用にも多くのメリットがあることから、現在では社内用途を想定したチャットサービスも数多くリリースされており、多くの企業がビジネス環境の改善のために導入・活用を進めています。
提供側とユーザーの双方にメリットがある
チャットサービスの導入事例からは、サービスの提供側・ユーザー側双方にメリットがあることが読み取れます。社内向けにチャットサービスを利用している場合は、同様に対応側・利用側の双方にメリットが確認できます。
提供側はツールに対応を任せることで業務効率化・コスト削減を図ることが可能となり、人手不足・リソース不足の課題を解決することが可能です。ユーザー側は問題・疑問が生じた時にいつでも手軽にサービスを利用することができるため、利便性・満足度の向上を図ることができます。
社内用途で導入している場合においては、対応側は業務効率化・負荷軽減・リソース配分の改善が可能となり、利用側は時間・場所に関わらずいつでも問題解決が可能。企業全体において心身のストレス低減・生産性向上・従業員満足度向上などのたくさんのメリットを得ることができます。
さまざまな業種のサイトに設置されている
チャットサービスの事例からは、通販サイト・銀行・宅配業など幅広い業界・業種で活用されていることが分かりました。Webサイト・ECサイト・SNS・社内ポータル・Webサービスなど、サービスを設置できる場所の自由度も高まってきています。このような事実から、さまざまなシーンでパフォーマンスを発揮できる高い機能性・汎用性を備えたサービスであることが分かります。
チャットサービスに対するニーズの高まりから、現在では各ベンダーから多種多様な製品がリリースされており、業界・業種・ビジネス環境に合わせたツールを導入することが可能となっています。環境・基盤は既に整っている状況下にあるため、これからチャットサービスを利用してみたいという方も、スムーズに導入・活用を進めることが可能です。
チャットサービスの導入に失敗した企業の共通点

チャットサービスを導入し、失敗してしまった企業の共通点とは何でしょうか。
そこには、「何となく、他の企業が導入していたから」といった安易な考えで導入してしまったり、具体的な目標を定めていなかったり、導入するだけで満足してしまったりといった、「チャットサービスに信頼を置きすぎて気持ちがゆるんでしまった」という共通点が見受けられます。
チャットサービスを導入したものの、失敗してしまった例と、その対策について見ていきましょう。
"何となく"導入してしまった
現在チャットサービスは多数の企業が導入しているツールです。しかし、「多くの企業が導入しているから導入する」といった安易な考えで導入することは、大きな失敗につながるでしょう。
チャットサービスの導入には、期待効果や活用方針などをきちんと設計することが欠かせません。まずは、「自社にどのような課題があるのか」「どんな課題を解決するために導入するのか」といった点を明確化する必要があります。また、導入した後に継続的にサービスを提供し続けられるかという点についても配慮する必要があります。
こうした導入前の準備を怠ってしまうと、ユーザーからのマイナス評価を招くリスクもあります。チャットサービスだけでなく、商品やサービスのブランド自体の満足度をも低下させてしまうことにもつながりかねないので、「なんとなく」という安易な考えで導入せず、導入する前に十分な検討を重ねるようにしましょう。
目標を決めないで導入してしまった
自社にどのような課題があるかを把握した上で、目標を立ててから導入をしないとチャットサービスの効果が具体的に把握できなくなってしまいます。また、目標自体を数値などで具体化することによって、チャットサービスの設定やメンテナンスを行う際に、目標に沿った改善を施すことができ、効果的な運用をすることができます。
目標は、課題解決に沿った設定することが望ましいです。例えば、営業時間外の問い合わせが多く、回答が翌日以降に遅れてしまうことを課題としている場合、営業時間外にはチャットサービスでの対応に切り替えることで、営業期間外の問い合わせにも迅速に対応できるようになります。
このように、課題に対して効果が期待できるのかという視点を忘れずに導入すれば、効果を出すことができるようになります。
導入して満足してしまった
チャットサービスを導入し、それで満足してしまったことで充分な活用ができないケースも少なくありません。導入後の定期的なメンテナンスを怠った結果、チャットサービスの精度が高まらず、顧客の期待する対応も取ることができずに失敗に至るというケースもあります。
導入した後には定期的なメンテナンスを行い、チャットの精度を高めていく必要があります。初めから完璧なデータが揃っているチャットサービスはなく、誰がどのような質問をしてくるかを予測し切ることも不可能であるからこそ、定期的なメンテナンスによってデータを補うことが重要なのです。
特に、顧客の要望を満たすことができなかったシナリオについては、監視を強め、改良を重ねていく必要があります。
社内で使いこなせない
業務効率化や顧客満足度向上のためにチャットサービスを導入したものの、操作や機能が難しく、社内メンバーで上手く使いこなせないといった事例は多くあります。
いくら優秀なチャットサービスを導入しても、使いこなせなければ効果を発揮することはできません。このような事態を避けるためには、導入前に以下のような工夫を行うことをおすすめします。
- デモ版や無料版を実際に使用して、操作感や運用の難易度を確認する
- 社内メンバーのITリテラシーに見合ったチャットサービスを選ぶ
- 分かりやすさ・使いやすさに定評のあるチャットサービスを選ぶ
- 導入後の運用サポートが充実したチャットサービスを選ぶ
使いこなせていないチャットサービスを社内メンバーが習熟することも不可能ではありませんが、多くの時間や労力が必要となります。そのため、必ず自社で使いこなせることを前提としたチャットサービスの導入を行うようにしましょう。
ユーザー目線のチャットサービスになっていない
チャットボットはデータベースに登録した質問にしか答えることができないため、ユーザーがどんなニーズを持っているかを常に考えて、適切な設定を行う必要があります。他にも、ユーザーによっては電話での問い合わせの方が慣れている場合もあり、そうしたユーザーに無機質・機械的といった印象を抱かせないように、ユーザーの目線に立った工夫をする必要があります。
チャットサポートの場合は、疑問点の解決に役立ちそうな資料を顧客に送信したり、説明動画のリンク先を掲示したりするなど、電話対応ではできないスムーズな情報提供もできます。図や動画を使った回答の方が伝わりやすい質問も、ユーザー目線で迅速に解決へと導くことができるのはチャットサービスならではの強みです。こうしたチャットならではの強みを理解し、ユーザーの課題解決に直結するような仕組み作りをしていきましょう。
また、チャットサポートは、顧客の生の声を聞く重要な場でもあります。チャットサポートの利便性が向上することは、ユーザーのニーズをひき出すチャンスが増えることにもつながります。企業にとって顧客の要望に応えられるような商品・サービスへとブラッシュアップすることは必要不可欠であるため、顧客との会話データをしっかりと分析して、有効に活用しましょう。
おすすめチャットサービス「チャットディーラーAI」

株式会社ラクスでは、企業の業務効率化・生産性向上に役立てることができるチャットボットサービス「チャットディーラーAI」を提供しています。
汎用性・利便性が高く、チャットサービスを活用して社内の課題を解決したい場合におすすめ。以下にツールの詳細についてご紹介していますので、チャットサービスの導入を検討している方はぜひチェックしてみて下さい。
チャットディーラーAIは社内ヘルプデスク用途に特化
社内ヘルプデスク向けタイプのチャットディーラーは、社内での利用に特化したAI搭載のチャットボットサービスです。
情報システム・総務・人事・経理・労務といった企業内のさまざまな部署での活用が可能であり、複数部署を跨いでまとめて利用することもできます。
社内ヘルプデスク向けタイプのチャットディーラーの主な特徴について、以下にご紹介します。
- 400種類を超える社内用テンプレートを搭載しており、最小限の負担ですぐに導入可能
- AIは学習済であるため、従来のチャットボットのように学習・調整が不要
- 社内特化型だからこそ、一般的なAIチャットボットよりも圧倒的な低価格を実現
- 社員数に関わらず固定料金で利用が可能
- 専属コンサルタントが導入から運用安定化まで徹底サポート
多くの社員を抱えるほど、業務が煩雑であるほど、企業内の各部署におけるヘルプデスク業務の重要性・必要性は高まります。チャットボット導入により、社内ヘルプデスク業務を改善して企業の業務効率化・生産性向上を図りたい方は、ぜひ社内ヘルプデスク向けタイプのチャットディーラーをご検討下さい。
まとめ
今回ご紹介したチャットサービスの概要・導入事例の通り、近年ではチャットサービスのニーズは高まっており、さまざまな業界・業種で活用されています。
また、新型コロナウイルス感染拡大によるビジネスのオンライン化や、それに伴う競争の激化といった環境の変化により、ITツールを活用して従来の業務を効率化・合理化することは、これからの企業にとって必須であると言えるでしょう。
現在自社の業務に課題や問題を感じていたり、効率化や負担軽減を図りたい場合は、自社に合ったチャットサービスを導入することで解決できる可能性が大いにあります。
チャットサービス導入により業務を自動化することで、人的リソース不足の保管はもちろん、リソースが解放されたメンバーがコア業務に集中することも可能です。
弊社では、チャットサービスの導入を検討している方に対して詳細な資料をプレゼントしています。導入から目標達成までのサポートも充実しているため、ぜひ導入をご検討下さい。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。