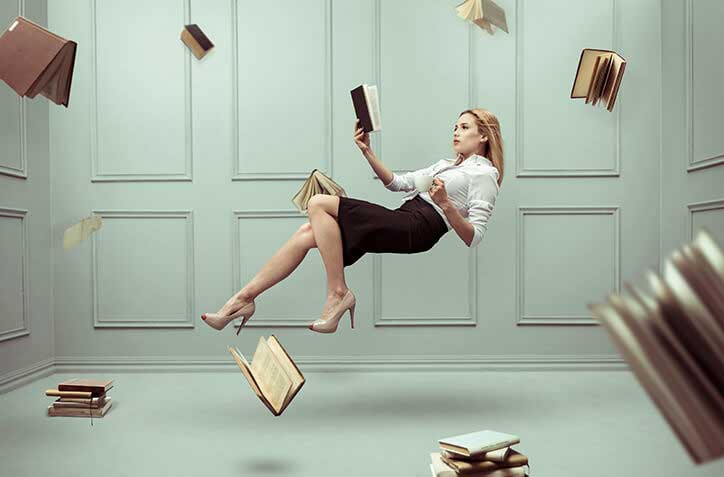採用活動を「チャットボット」がサポート!導入企業が増えているワケとは?

近年、企業から注目を集めている「チャットボット」を皆さんはご存知でしょうか。
チャットボットとはチャットとボットを組み合わせた言葉で、自動会話プログラムのことです。チャットはインターネット上でテキストのメッセージをやりとりする仕組みを指し、ボットはロボットの略で人間に代わって自動処理するプログラムを指します。
近年、チャットボットは企業の採用活動への導入が進んでいます。この記事では、採用活動にチャットボットを導入することで実現することや、具体的な活用方法、導入事例までご紹介していきます。
チャットボットとは?
チャットボットとは、事前に用意した設問・回答をもとに、自動でメッセージのやりとりや問い合わせ対応を行うことができるプログラムのことです。Webサイト・Webサービス・SNS等に設置してユーザーとの対応に活用します。
現行のチャットボットには、処理・回答の方式により以下2つのタイプがあります。
-
ルールベース型
あらかじめ用意したシナリオに従って回答するタイプのチャットボット。
-
AI型
AI搭載により人間に近い高度な対応ができるチャットボット。
また、チャットボットは利用目的・用途によっても次のように分類されます。
-
FAQ型
ユーザーが入力した質問に対して回答を返すタイプ。
-
処理代行型
入力された内容に対する事務的処理を実施できるタイプ。
-
配信型
状況に応じて事前に用意されたメッセージを配信するタイプ。
-
雑談型
ユーザーとの会話・雑談を主な目的としたタイプ
チャットボットは、社内外の問い合わせ業務の大幅な効率化や生産性向上に役立つことから、幅広い業界・業種でさまざまな用途に活用されています。
採用活動にチャットボットを導入すると◯◯が実現!
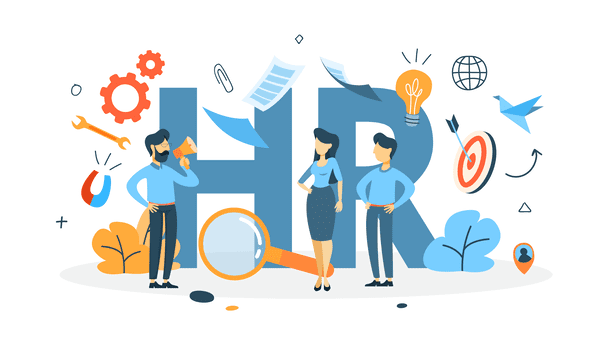
採用活動にチャットボットを導入すると、接点増加、人事の負担軽減、データの蓄積、企業と人材のミスマッチの防止が実現します。
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
接点増加
就職活動をしている人は、企業を調べる際、ポジティブな面とネガティブな面の両方を知りたいと考えます。仕事の内容や給与などの待遇に関することに加えて、残業時間や有給休暇取得率も応募前に把握しておきたい項目です。
しかし、人事担当者にネガティブなことを聞くのは求職者にとって少し勇気のいることで、億劫だと感じる人が多いでしょう。また、悪い印象を与えてしまうのではないかと考えて、質問することを躊躇しがちです。気軽に質問できない環境から応募を諦めてしまう人も多く、そういった場合、企業は採用機会を逃してしまいます。
対策として自社の求人サイトにチャットボットを設置すれば、求職者が遠慮することなく、自由に質問できる環境を構築できます。直接話すのが苦手な人も気軽にコミュニケーションがとれるようになるため、企業と求職者の接点増加に役立ちます。チャットボットで接点が増加すれば、応募数も増えることが見込まれるので、採用活動において有効な手段となります。
また、電話や面接などの面倒なプロセスを省き、チャットボットでいつでも求職者の質問に答えることで、求職者に対していいイメージを与えることができるでしょう。
人事の負担軽減
採用に関するよくある質問や、簡単な質問をチャットボットに対応させることで、これまで人事担当者が担っていた対応業務を一部自動化することができます。
人事担当者が担う業務は、求職者からの問い合わせ対応だけでなく、面接や教育、社員の部署配置・異動の管理など、多岐にわたります。日々、多くの業務をこなす中で、業務効率化を図ることができないかと考える方も多いはずです。
そこで、チャットボットを活用し、求職者からの問い合わせ対応にかかる時間を削減することは有効だといえます。
また、その分の人事担当者リソースを、より複雑で重要度の高い業務に回すことができるのです。結果として人事担当者の負担が軽減され、効率的な採用活動が実現するでしょう。
データの蓄積
チャットボットでやりとりされた質問は、全てデータとして保管されます。求職者が疑問に思っていることや、職を探すうえで注目している点などのデータを蓄積することができるのです。このデータを分析することで、人事担当者が次に取るべきアクションや求職者の新たなニーズが見えてきます。また、離脱した求職者のデータを得ることもでき、応募まで至らなかった求職者に対して、アクションを起こすことも可能です。
自社に応募してくれる求職者を獲得するには、ターゲットを絞ることが重要です。チャットボットで獲得したデータを元に採用活動を展開することでターゲットを絞り、適切なアプローチ方法を取ることができます。結果として求職者を自社の採用サイトにスムーズに誘導することができ、求める人材を採用することができるでしょう。
さらに、蓄積されたデータを分析してチャットボットにデータとして登録すれば、返答精度を向上させることもできます。
企業と人材のミスマッチを防ぐ
先述した通り、電話やメール、対面であると、求職者はどうしてもネガティブな内容の質問をすることを躊躇してしまいます。こういった点が、求職者の中で曖昧になったまま採用してしまうと、ミスマッチが起こり、早期退職につながってしまいます。早期退職は、求職者の経歴的にも、企業の採用コスト的にも絶対に避けたいものです。
求職者がフランクに質問できる環境を作っておくことで、こういった企業と求職者間のミスマッチを防ぐことができます。
そこで最適なのが、チャットボットです。チャットボットは、365日24時間、匿名で気軽に質問することができます。
求職者は、企業に聞きにくいネガティブな質問でも気を遣わずにできるようになります。また、企業にとっても、採用コストを最低限に抑えることができるため、両者にメリットがあることは確かです。
問い合わせに素早く対応できる
求職者は興味を持った企業に問い合わせを行う際に、なるべく早く回答を得たいと考えています。しかし、従来の応募フォームによる問い合わせの場合は、採用担当者が順次回答を行う必要があるため、他の業務で席を外しているとすぐに回答を行うことができません。
求職者は一般的に自社以外の複数社を含めて検討しているため、回答が遅いと応募への意欲も低下してしまいます。優秀な求職者を取り逃してしまうこともあるでしょう。
チャットボットであれば、採用担当者の都合に依らず、24時間いつでも求職者に対して瞬時に正確な回答を行うことができます。
求職者からの問い合わせに素早く回答することで、疑問点の解消だけでなく応募への意欲・熱量を維持することができるため、採用活動の効率も高めることができます。
採用でのチャットボット活用方法
採用の現場での基本的なチャットボット活用方法は、企業の公式採用ページに設置することです。具体的な活用方法としては、次のようなものがあります。
-
問い合わせ対応
求職者から企業に寄せられる問い合わせ対応をチャットボットに代替します。自動で多くの質問に即答できるため、求職者はすぐに回答を得ることができて、採用担当者は問い合わせ対応の負担を軽減することができます。
-
応募受付・面接の予約
一定の処理を行えるチャットボットであれば、採用活動における応募受付から面接の予約までを自動で処理することも可能です。応募受付から面接日の調整を行うことは大きな負担が掛かりますが、チャットボットに代替することで手間や時間を大幅に削減することができます。
-
就活・求人イベント等での活用
端末とWebサイトさえあればチャットボットは稼働させることができるため、求人関係のイベント時に端末を設置して、集まった求職者への情報提供や問い合わせ対応に活用することもできます。
採用活動においては有料の求人媒体を活用する企業が多いですが、当然ながら高額の媒体利用料ならびに自社内での採用コストが発生します。自社ホームページにチャットボットを設置すれば、求人媒体のコストだけでなく内部コストも削減できるため、大幅なコストダウンを図ることができます。
採用活動にチャットボットを活用する際には、より高い成果を得るために、ユーザーの利用データを定期的に分析して回答精度を高めていくことがポイントです。
採用活動にチャットボットを活用したケース
ここでは、実際に採用活動にチャットボットを活用したケースをご紹介します。
ケース①:データの蓄積に成功
熊本県に本社を置き、熊本・福岡・佐賀で不動産ビジネスを展開している株式会社リブワークでは、新卒採用イベントにチャットボットを設置し、応募者の対応をしました。
応募者から日々寄せられる質問にリアルタイムに自動で返答することができ、人事担当者の採用業務にかかわる工数を削減。チャットボットはパソコンの他、スマホやタブレットにも対応させることで、応募者は好きなときに好きな場所でいつでも質問をすることが可能となりました。
質問内容は全てログとしてデータが保存・蓄積され、そのデータから応募者の求めている情報やニーズを分析してリブワークはその後の採用活動に活用しています。
ケース②:24時間の対応が実現
大阪に本社を置き、グローバスに空調関連ビジネスを展開する専業企業のダイキン工業株式会社は、新卒学生の採用活動において、応募学生から寄せられる質問に24時間いつでも自動で回答するAI(人工知能)を活用したチャットボットを試験的に導入しました。無料コミュニケーションアプリのLINE上に公式アカウントを開設し、就職活動や会社に関する質問を受け付けています。
スマホやタブレットが普及して時間や場所を問わずに情報収集ができるようになった今日、就職活動でも知りたいことや、疑問を気軽にいつでも情報収集したいというニーズが高まっていることに応じて導入に踏み切りました。チャットボットの導入により24時間の対応を実現し、就活生とのコミュニケーションの場を提供することで、会社への理解を深めています。
また、ダイキンではチャットボットを活用した家庭用ルームエアコンの故障診断サービスを展開しており、サポートサイトでAI故障診断として運用しています。同社は今後もチャットボットの導入を広げていく方針です。
ケース③:採用ブランディングの強化に成功
東京に本社を置き、基幹業務アプリケーションシステムサービスなどを提供する株式会社ティービーケー・システムエンジニアリングは、企業としての知名度の低さがネックで、思い通りに採用が進まないという悩みを持っていました。採用のブランディングを強化する対策として、自社サイトのリニューアルを機会に採用にチャットボットを活用するという新たな試みを開始したのです。
同社の抱えていた課題は、地元以外の大学では知名度が低かったこと、会社の良さをアピールするための学生とのタッチポイントの機会を増やす必要があったこと、採用担当者が他に兼務している業務があって採用活動に十分な時間を割けなかったことです。
チャットボット導入後は学生の反応が良くなり、面と向かっては聞きづらいことをキャッチアップできています。また、対面のコミュニケーションに苦手意識を持っている学生にも有効な接点として機能しているといった効果を上げています。今後は、チャットボットを通してメッセージを発信する試みに取り組んでいく予定です。
ケース④:面接数・採用数の増加に貢献
飲食業を多店舗展開するI社では、応募者数に対して採用担当者が不足しており、応募者への連絡の不行き届きから面接数・採用数が伸びないことが大きな課題でした。そこでI社は、採用チャットボットを全国の店舗に導入することにより、採用活動の大幅な効率化と負担軽減を図ることを決意。
導入後は採用に関する業務を3割以上軽減、面接数も1割以上向上することに成功。採用効率を高めるだけでなく、チャットボットの活躍により応募者と自社のマッチング率も高まり、採用に係るコストも劇激に削減することに成功しています。
ケース⑤:多事業な自社の姿を正しく伝えるために
高い技術力と斬新なアイディアで世界的にも評価の高いソニーグループ株式会社は、採用活動において学生が思い描く自社のイメージと実際の自社の姿が大きく乖離していることに疑問を感じ、課題解決のために採用チャットボットの導入に踏み切りました。
起用したチャットボットは、多くの学生に利用されているLINEと連携するAI型チャットボット。親しみやすいキャラクター(同社の”aibo”)が採用担当者に代わって学生との会話を行う仕組みです。
数多くの学生が同社への質問や就活の悩みなどのたくさんの会話を行い、半年間の運用で学生からの反響は上々。実際の会話や雑談に近い自然な会話が可能であることや、マスコットキャラクターに自社製品を採用したことが利用者数を増やした要因だと考えらます。
同社が目指していた目標である、「多様な事業・多様な職種について伝える」という課題のクリアにも大きく貢献しており、採用チャットボットの活用事例としては大成功を収めています。
採用活動にチャットボットを導入するときのポイント

ここからは、採用活動にチャットボットを導入するときのポイントを2つ説明します。
求職者が求める情報を提供する
企業の採用サイトを訪れる求職者は、企業のホームページを見てからアクセスしてくることが多いため、サイトに書いてある内容は一通り読んでいる場合が多いです。したがって、求職者はサイトを見れば分かるような簡単な質問だけではなく、残業時間の程度や有給休暇の取得率など気になることを質問してきます。
採用サイトにチャットボットを設置する際は、そのような深い部分まで回答できるように設定しておく必要があります。情報があふれる現代では、採用サイトで求職者が求めている情報をピンポイントに提供することが求められているのです。
就職活動において、インターネットで企業の情報を収集するのが当たり前になった現在、求職者に興味を持ってもらう入口としての採用サイトは情報提供の場として重要な役割を持ちます。そのため、チャットボットが求職者とやりとりした質問と回答のログデータを基に求められている情報を解析し、PDCAを回してデータを更新し、効果的な回答を返せるようにしましょう。
新卒採用と中途採用で内容を分ける
新卒採用の求職者と中途採用の求職者では、質問内容が異なることが考えられるため、採用サイトに設置するチャットボットをそれぞれに対応できるように設定する必要があります。
特に中途採用の求職者は、給与、福利厚生、離職率など、前職と比較できるよう、より踏み込んだ質問をしてくることが予想されます。その際、具体的な標準年収額や月の平均残業時間、福利厚生の内容、女性の場合は産休や育休の取得実績など、面と向かっては聞きづらい質問や、社外には知られたくない質問も回答できるようにしておかなければいけません。
また、中途採用の場合は、入社後即戦力として会社の中枢で働きたいと考えている人が多いため、キャリアプランの例示をして入社後の具体的な仕事の内容をイメージできるようにするのもいいでしょう。
運用方法としては、新卒採用ページと中途採用ページで設置するチャットボットを分けたり、チャットボット内で新卒・中途を選べるようにしたりするといいでしょう。
おすすめのチャットボットツール「チャットディーラー」
採用活動に活用できるチャットボットをお探しの方は、弊社が提供する「チャットディーラー」がおすすめです。製品特徴とおすすめポイントは次の通りです。
- 有人チャット・無人チャット両方の運用が可能で幅広い問い合わせニーズに対応できる
- Webサイト・Webサービス・LP等さまざまな場所に設置が可能
- 会話形式で使いやすいため誰でもスムーズに回答を得られる
- 導入・設置・効果測定も簡単でスムーズに運用をスタートできる
- 導入・運用・ブラッシュアップまで手厚くサポート
チャットディーラーは、数多くの企業の問い合わせ業務効率化・生産性向上に活用されている実績を持つチャットボットツールです。あらゆるニーズに対応できる汎用性の高さ・充実した機能を有しています。
資料ダウンロード・トライアル利用も無料で提供していますので、採用活動にチャットボットを活用したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
まとめ
従来人事担当者が対応していた求職者とのコミュニケーションを、チャットボットが代行する時代になりました。今後、チャットボットは採用活動において、大きな変化をもたらす可能性があります。
チャットボットは広く一般に活用されるようになってから歴史はまだ浅いですが、技術の進歩と共に双方向でインタラクティブなコミュニケーションが可能になり、十分実用的なレベルになってきています。採用活動業務の効率化と生産性向上を図りたい、求職者とのタッチポイントを増やしたいと考えている方はチャットボットの導入を一考してみてはいかがでしょうか。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。