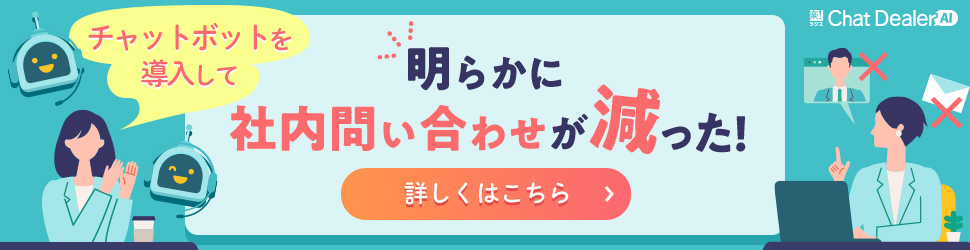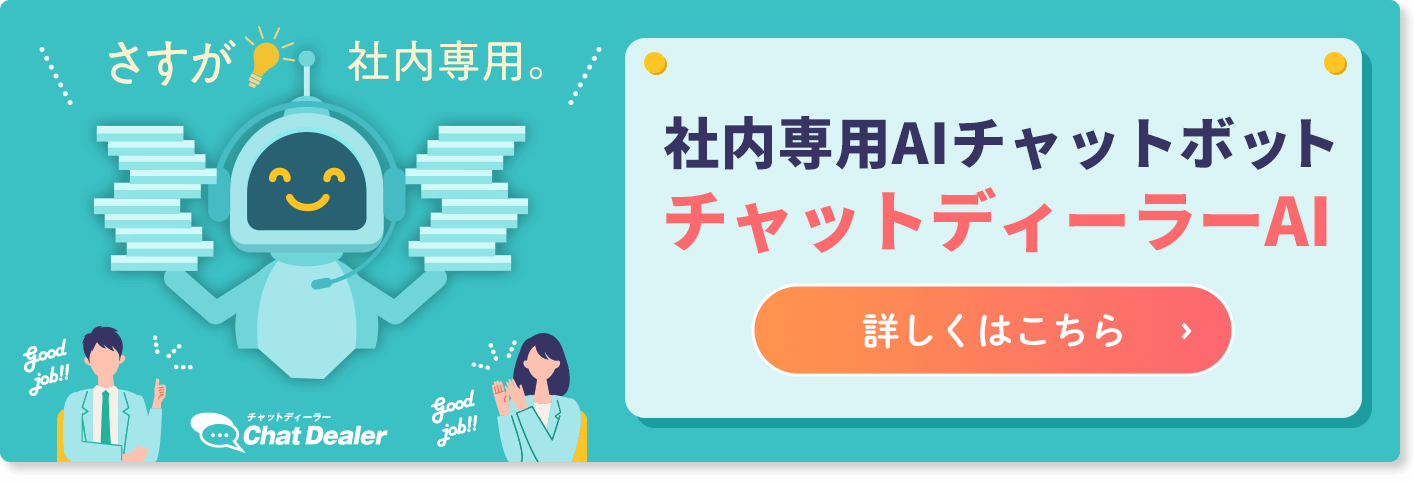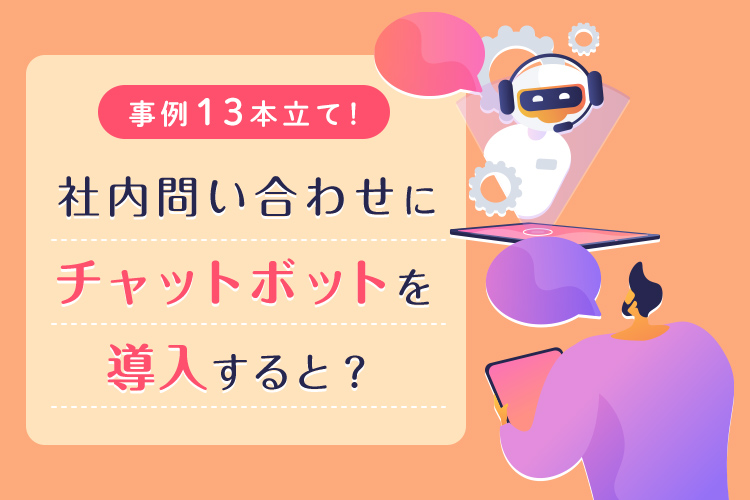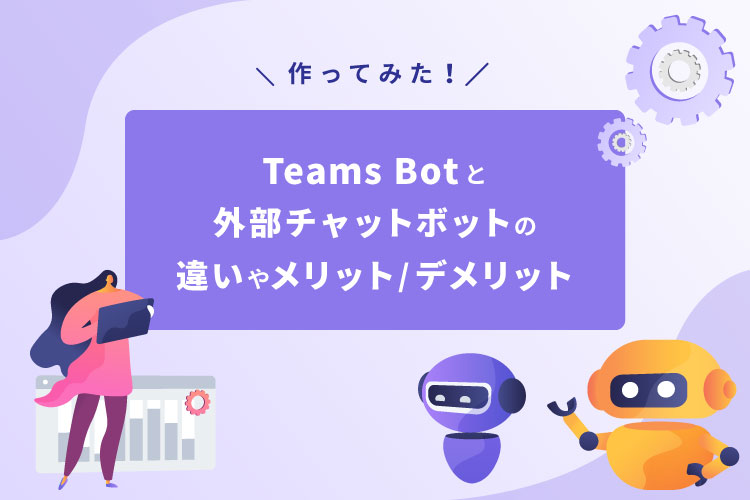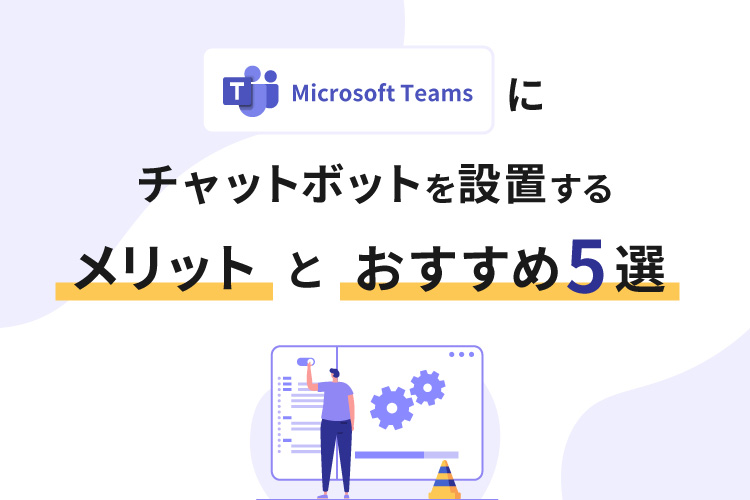社内向けチャットボットの利用率を改善する方法とは?
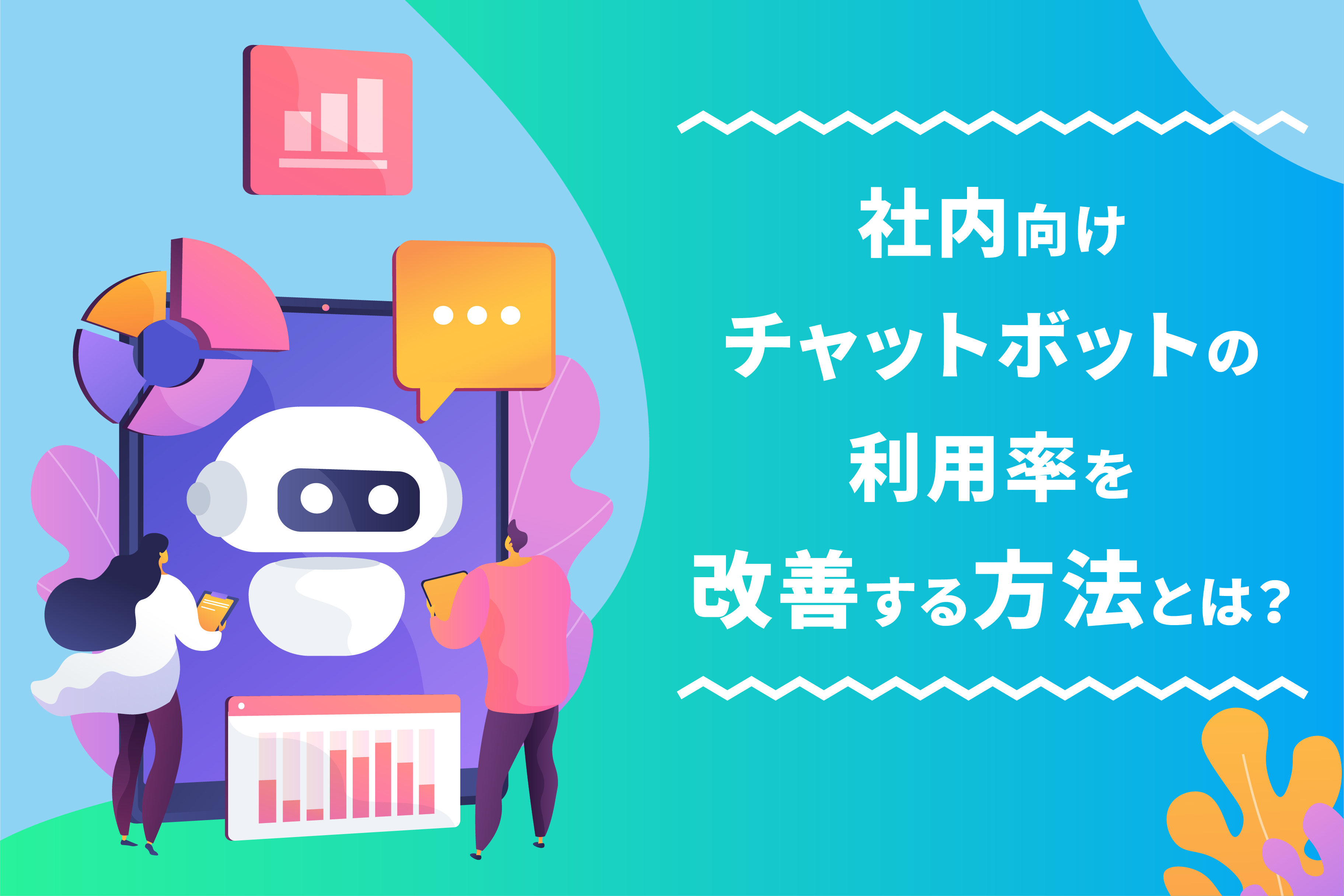
昨今、お問合せ対応を効率化するツールとしてチャットボットに注目が集まっています。
中でも、社内にチャットボットを導入して、情報システム部や総務部など管理部門のヘルプデスクへ届くお問合せの削減を目指す企業が増えています。
一方で、せっかく社内にチャットボットを導入したのに、「思ったようにチャットボットが使われず、問合せが減らない」「回答精度を上げているのに、利用率がなかなか上がらない」と困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、社内向けチャットボット導入後によくある課題や利用率が高いことで得られるメリット、利用率を上げる方法についてご紹介いたします。
実は弊社でもチャットディーラーAIというチャットボットを活用しているので、実際に弊社で試してみて効果的だった方法も掲載しています。
社内向けチャットボットの利用を促進する方法が知りたい方は、ぜひご参考にしてください。
社内向けチャットボット導入後によくある課題
チャットボット導入後によくある課題には、以下のようなものがあげられます。
- 回答精度が低く、社員の質問に答えられないことが多い
- チャットボットが社員に浸透しておらず、利用率が低い
- ヘルプデスクへの電話やメールでの問合せが減らない
- 改善を行いたいが、どこから手を付けてよいか分からない
特に「利用率が低い」という課題は、多くの会社で発生しています。
なぜなら、社員からするとわざわざ「チャットボット」という新しいシステムを使うよりも、従来の電話やメールという手段でヘルプデスクに問い合わせた方が早いと考えられるからです。
せっかくチャットボットを導入しても、社員の利用率が低く「使われないチャットボット」のままだとヘルプデスクの業務負担は軽減されません。
また、利用率が低いと導入によって得られた効果よりもチャットボットの導入にかかったコストの方が多くなり、費用対効果が出ないという状況に陥ってしまいます。
そのため、チャットボット導入後に利用率を上げるための取り組みは必須だといえるでしょう。
チャットボットの利用率が高いことで得られるメリット

続いて、チャットボットの利用率が高いとどんなメリットが得られるか確認しておきましょう。
ここでは三つのメリットを紹介します。
ヘルプデスクの生産性向上
一つ目のメリットはヘルプデスクの業務が効率化され、生産性が向上できることです。
社員のチャットボットの利用率が上がるということは、疑問が発生したときにまずチャットボットを利用してその場で自己解決を図ってくれるという状況です。
そのため、チャットボットがきちんと利用されていれば、ヘルプデスクへの問合せは削減されます。
社員からの問合せが削減されると、ヘルプデスクはこれまで問合せに対応していた時間をコア業務に充てることができるようになり、結果として生産性を上げられます。
社員満足度の向上
二つ目のメリットは疑問を解決するまでの時間が短縮され、社員の満足度が向上することです。
そもそもチャットボットは、社員の疑問にいつでもすぐに自動回答することができるので、「ヘルプデスクの回答待ちで業務が止まってしまう」といった不満を解消できます。
さらに、チャットボットでは解決しなかった疑問を社内ヘルプデスクに問い合わせたとしても、社内ヘルプデスク担当者の対応件数が減少したことで、回答までの待ち時間が短くなっているはずです。
チャットボットの効率的な改善ができる
三つ目のメリットは会話データを蓄積することで、チャットボットの効率的な改善ができることです。
利用率が上がると、チャットボットのレポート機能を使って、頻繁に検索されるキーワードやよく見られているマニュアルが分かるようになります。
社員のニーズを定量的なデータとして把握することができると、特によく使われているマニュアルの内容を拡充したり、よく聞かれている内容からFAQを追加したり、効率的に改善が行えるようになります。
チャットボットが社員のニーズをもとに改善されると、より幅広い質問に答えることができるようになり回答精度が高まります。
社内向けチャットボットの利用率を上げる方法

それでは、ここからは社内チャットボットの利用率をあげる方法を以下の3つのポイントに沿って紹介します。
- チャットボットの見せ方を工夫する
- チャットボットの設置先を増やす
- 周知方法を工夫する
チャットボットの見せ方を工夫する
まずは、チャットボット自体に手を加えることで、社員に「使ってみよう」と思わせる工夫が必要です。
具体的な方法を3つ紹介します。
チャットボットをキャラクター化する
チャットボットに思わずクリックしたくなるようなかわいいアイコンを設定し、名前を付けてキャラクター化してみましょう。
「お客様向けのチャットボットをキャラクターにするのは効果がありそうだけど、社内向けのチャットボットでアイコンを設置する意味なんてあるの?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は社内向けのチャットボットであっても「無機質なロボットに話しかける」よりも、「キャラクターと会話をしている」と思ってもらったほうが自然と親しみがわいてくるものです。
実際に弊社でもチャットボットを「ラク子さん」というオリジナルキャラクターにしていますが、名前を付けて社内共通の名前で呼び合うほうが、社員に浸透するスピードも格段に速くなるのでオススメです。
入力例や注意点を表示する
そもそもチャットボットに慣れていない社員の場合、どうやって質問をしていいのか分からずに離脱している可能性があるので、初回メッセージで簡単な操作方法や入力例を表示してあげましょう。
また、社内向けチャットボットの多くはAIが搭載されており、質問文の表現の揺らぎに対応できるようになっています。
しかし、「パソコン」「有給」など1単語のみの検索だとAIは社員が何を知りたいのか判別することができず、質問候補を表示できません。社員によってはチャットボットを使ってみようと思ったものの、1単語のみで質問をして回答が得られず諦めてしまった可能性もあります。
そのためAIチャットボットの場合には、「単語を組み合わせるor文章にするなど質問は具体的に記載してください」といった注意点を記載するのも離脱防止に効果的です。
<初回メッセージ文例>

よくある質問は最初のメッセージ内に表示する
チャットボットの離脱率を減らすためには、社員が回答を得るまでにすべき操作をできるだけ少なくしてあげるのも有効です。
例えば、よくある質問は最初から初期起動画面のメッセージ内に選択式で表示してあげると、ワンクリックで回答にたどりつくことができるので便利です。
日頃から多く使われるFAQを掲載する以外にも、「在宅勤務時時のシステムについて」「年末調整について」など時期によって一時的に増加する質問を最初のメッセージに載せるのも、チャットボットを使う機会の少ない社員にとって親切でしょう。
チャットボットで解決できないときの対処方法を示す
チャットボットが回答できる質問はあくまでもFAQの登録があるものに限定されます。
そのため、チャットボットでは解決できなかった際の対応方法も明示するようにしましょう。
例えば、せっかくチャットボットに質問をしたのに「その質問には回答できません」とだけ表示されていると、質問者はチャットボットに対して「使えないシステム」といったマイナスのイメージを抱きます。
一方で、「貸出機器についてご不明な点は○○へお問合せください」のように問合せ先を示す一言がある場合、質問者は「質問に対する回答は得られなかったけれど問合せ先は分かった!」とプラスにとらえる可能性があります。
さらにチャットボットによっては、そのまま問い合わせフォームに遷移させたり、担当部署の内線番号もチャットボット上で検索できるものもあるので確認してみましょう。
チャットボットの設置先を増やす
続いて、社員が利用しやすい環境にチャットボットを置くというのも重要です。
社内向けチャットボットの設置先として、オススメの場所を2つご紹介します。
社内ポータル
一つ目のオススメ設置場所は社内ポータルです。
社内ポータルとは、自社が保有する情報にアクセスするための入口となるサイトのことです。
社員のみがアクセスできるようになっており、社内の情報共有を目的として設置されています。
ワークフローの申請や社内掲示板など業務を進めるうえで必要な機能を兼ね備えていることが多く、日々たくさんの社員が社内ポータルにアクセスしている可能性が高いです。
そのため、社内ポータルの目立つ場所にチャットボットを設置することで、分からないことがあった時にすぐにチャットボットに質問できるようになり、積極的な活用を促すことができます。
ビジネスチャット
二つ目のオススメ設置場所はMicrosoft TeamsやSlack、Google Chatなどのビジネスチャットです。
ビジネスチャットはメールに比べて、短い文章で要点だけを伝えるなど気軽にやり取りができる特徴があります。そのため、リモートワークなど遠隔地にいる人とスピード感を持ってコミュニケーションする目的で近年導入を進めている企業が増えています。
もし普段から利用しているビジネスチャットがある場合は、ぜひチャットボットを設置しましょう。
ビジネスチャット上でチャットボットに直接アクセスできるようになることで、わざわざチャットボットのためにページを開く手間を削減できるので、利用回数の増加につながります。
ただし、チャットボットによって連携できるビジネスチャットは異なるので個別の確認が必要です。
周知方法を工夫する
社員にチャットボットを知ってもらう工夫も必要です。
ここでは「公開前の事前周知」と「公開後の継続周知」の方法について、それぞれ紹介します。
公開前の事前周知
社内掲示板
社内掲示板には企業の経営状況や社長からのメッセージだけでなく、社内FAQや社内ニュースが掲載されていることが多いかと思います。
そこで、まずは新着ニュースとしてチャットボットが開設されることを告知しましょう。
一般的に、社内掲示板は短い文章で要点だけを伝えることが多いため、チャットボットの設置先や開始時期などを5W1Hや箇条書きを使って簡潔に記載することをオススメします。
全社メール
会社によっては、社内掲示板はあまり活用されておらず、業務連絡はメールで行っているという方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、全社メールでもチャットボットが開設されることを告知しておきましょう。
なお、社内掲示板と比較してメールの方が内容を詳細に書けるため、「どうやって使うものなのか」「どんなメリットがあるのか」などの情報もあると、社員の利用イメージが湧きやすくなります。
社員連絡会
上二つの事前周知の方法は、きちんと伝達されるかは情報を受け取る側の社員にゆだねられているため、加えて口頭での連絡手段も併用することをオススメします。
社員連絡会といっても、わざわざそういった会を開くのではなく、部門長会議や各事業部内の月次会議等の一部を使ってチャットボットの説明を行うのでも十分有効だと考えられます。
社内連絡会で各部の役職者に伝達した内容を各部内のミーティングなどで一般社員にも共有してもらうことで、効率よく全社に告知をすることができます。
公開後の継続周知
一斉周知
公開後には、社員の意見を反映してチャットボットが便利になっていることのPRもかねて全社メールでの再周知をしてみましょう。
例えば、よくある質問をランキング形式で紹介したり、新規Q&A追加のお知らせをしてみるのも効果的です。
<周知メールの文面例>

また、新入社員研修など新たな社員が増えるタイミングで一斉にチャットボットのレクチャーをするのもおすすめです。
ただしここで重要なのは、あくまでもチャットボットの「使い方」のみを教えることです。
新入社員から聞かれた質問には、その場では答えずに「チャットボットで検索してみてください」と伝えるようにしましょう。
実際に弊社でも、パソコンのセットアップや有給休暇の申請方法など入社後に誰しもが必ず疑問に思うことは、あえて入社資料に掲載せずにチャットボットに誘導するようにしています。
その結果、「分からないことがあったらまずチャットボットに聞いてみる」という習慣が自然とついたので、ぜひ試してみてください。
個別周知
一斉周知の方法をすべて試してみても、残念ながらまだ、チャットボットに聞けば解決する疑問をヘルプデスクに直接聞いてくる社員がいる可能性があります。
そういった社員には、個別でチャットボットを周知しましょう。
例えば、メールでの問合せには署名欄にチャットボットのリンクを貼ってみたり、電話での問い合わせには「まず、チャットボットで検索してみましたか?」とヒアリングしてみるのが効果的です。
これまで「わざわざチャットボットを使うのが面倒」と思っている人でも、個別に直接お願いをされると「使わなければいけない」という意識に変わる可能性が高いです。
チャットディーラーAIなら改善提案もお任せ!

もしこれから、社内向けチャットボットを導入するならチャットディーラーAIがおすすめです。
チャットディーラーAIは、情シスや総務人事、経理、労務などの管理部門に特化したAIチャットボットです。管理部門のよくある質問について400種類以上のテンプレートを搭載し、AIの学習をかけた状態で提供しているため、回答を設定するだけですぐに使い始めることが可能です。
また、追加費用なしで専属担当がつき、導入前の設定から効果検証と改善提案までサポートしてくれます。正直、これまで説明してきたような利用促進の方法を自分で考えるのは難しいですが、チャットディーラーAIなら、成果が出るまで徹底的に支援してもらえるので安心です。
さらに、Microsoft TeamsやSlackなどのビジネスチャット連携や、通常のチャットボットに加えて社員の連絡先のみを回答する「内線表ボット」の作成など、利用促進のために必要な機能も十分備わっています。
まとめ
今回は、チャットボット導入後によくある課題や利用率を上げる方法についてご紹介してきました。
利用率が低いという課題は多くの会社が直面していることが分かりました。
その上で、チャットボットの利用率を上げるには、「チャットボットの見せ方を工夫する」「チャットボットの設置先を増やす」「周知方法を工夫する」という3つのポイントに沿って改善が必要です。
なお、チャットディーラーAIなら導入後の効果検証だけでなく、利用促進の方法まで専属のサポート担当が提案してくれるので高い利用率を目指すことができます。
ご興味を持たれた方は、以下から資料請求をご検討ください。
![執筆者:内山 七海]()
-
この記事を書いた人
内山 七海
2021年10月より法人向けクラウドサービスを提供する株式会社ラクスに入社し、チャットディーラーの製品プロモーションを担当。前職は旅行会社勤務で、一人旅もする旅行好き。