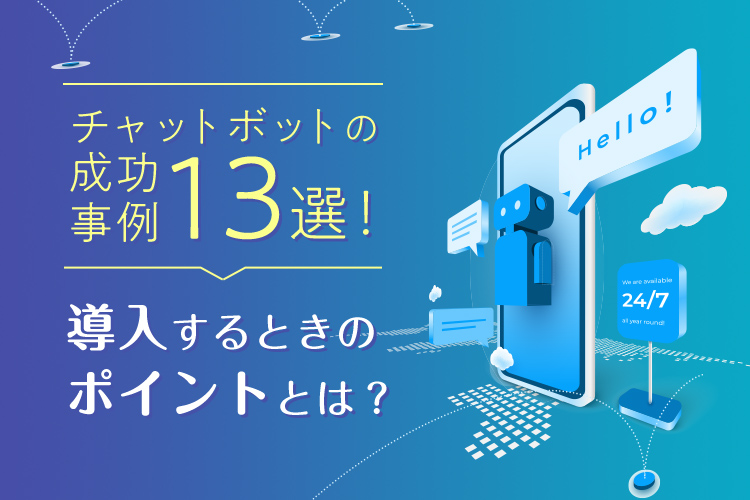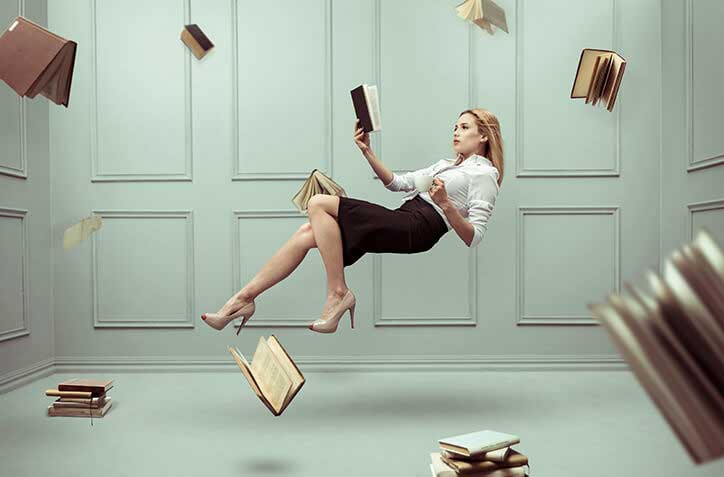CSへチャットボット導入する意義は?注意点2つもご紹介

カスタマーサポート部門では、毎日寄せられる問い合わせの効率化にどう対処すべきかお悩みでしょう。
顧客がいざというときに頼ってくれる部署が、CSです。
人手不足の世の中とはいえ、CSで適切な回答をえられないとき、顧客はあなたのビジネスを見放してしまうかもしれません。
そんな問題と対峙するとき、導入を検討すべきツールに「チャットボット」があがるでしょう。
- チャットボットを導入するとどんな効果があるの?
- チャットボットはどう選び、どう運用するべき?
あなたは今、こんな疑問を持ってこの記事を読んでいるのではないでしょうか?
今回は、
- チャットボットをCS部門に導入する意義
- チャットボットが果たす役割と運用方法
について、詳しくご説明しましょう。
最後まで読んでいただければ、「もっと早くにチャットボット導入を検討すべきだったかも…」という後悔を防ぐことができるでしょう。
CS部門が置かれている現状
2018年に公表されたある調査では、次のような結果が示されました。
- 日本は人手不足が深刻で「非常に苦労している」
- 特に人材不足を感じる職種6位は「カスタマーサポート」
多くの業種で人手不足が生じている原因は何なのでしょうか。そもそも応募者が少ないうえに、もしかすると企業側も闇雲に高い経験を求めているのかもしれません。人手不足の影響はカスタマーサポートにも及んでおり、上位に位置しています。
企業のCS部門は、人手不足以外にも業務効率・業務体制・対応品質など人材に関するさまざまな課題を抱えています。まず、この点を理解したうえで、今後のCS部門に必要なことを考えていきましょう。
「人材不足を解消する4つの戦略(89%の日本の雇用主が必要な人材を見つけられないと回答)│マンパワーグループ株式会社」
人手不足
CS部門は直接商品・サービスの販売に関わる部門ではありませんが、顧客からの問い合わせに適切な対応を行うことで、自社の信用を担保したり顧客満足度を高めたりといった重要な役割を担っています。
CS部門を十分に機能させるには常に人材を確保しておく必要がありますが、実際には人手不足に陥りやすい要因が多い部門でもあります。
- クレーム対応による負担やストレスが原因となっての離職
- 非正規中心の雇用形態に起因する人材の不定着
離脱が多いのに対して、採用・教育の難易度が高いことが人手不足に拍車をかけています。
人手不足の課題を解決するには、ITツールによる業務の代替を図ることが得策と言えます。業務効率化・業務負荷軽減を実現することにより、有人対応を担当する人材の業務環境も改善され、人材の定着・離脱防止の実現に繋がります。
業務の属人化
業務の属人化とは、特定のスタッフしか対応できない状況が発生することを言います。カスタマーサポートは、前回と同じスタッフに対応してもらいたいという顧客心理や、提供するサービスの複雑化といった要因により、属人化が発生しやすい状況下にあります。
属人化が発生すると、業務が特定のスタッフに集中することで負担が増したり、全体の業務効率が低下したりといった問題が発生します。
これからのCS部門は、業務効率化や業務負荷軽減のためにも、ナレッジやノウハウの共有などにより、いかに属人化を解消するかが重要となってくるでしょう。
対応品質のばらつき
CSの業務はオペレーターの経験・スキルにより対応できる内容・件数・解決までの時間といった対応品質にばらつきが生じることも、多くの企業のCS部門が抱えている課題です。
対応品質にばらつきが生じると、CS部門全体の業務効率が低下するだけでなく、対応するスタッフによって回答が異なったり顧客の不満やクレームに繋がったりする場合もあるため、できるだけ対応品質を一定に保つことがCS部門をスムーズに運用するポイントとなります。
経験・スキルの差は容易には埋められないため、業務のマニュアル化・情報共有・ITツールの活用等さまざまな手法を駆使して、いかに顧客に対応品質のばらつきを感じさせない体制を構築するかが重要となります。
CSにチャットボットを導入する意義

では、チャットボットは、カスタマーサポート部門にどのようなメリットをもたらしてくれるのでしょうか。
その意義を明確にしていきましょう。
顧客満足度向上
顧客が困ったときに問いを寄せるのがCSですので、24時間・365日答えを得られる仕組みは顧客満足度に直結します。
とはいえ、人材を途切れることなく配置することはできません。
この点で、チャットボットはいつでも顧客の問いに答えることができ、顧客満足度を上げることに寄与します。
業務効率化による人件費の削減
チャットボットを導入すれば業務を大きく効率化できます。
本来、「人」が行ってきたサポートの一部(ときにほとんどの部分)をチャットボットに振り分ければ、その分人件費を大いに抑制できるでしょう。
もちろん、チャットボットは人材不足という事態にも対応できる仕組みです。
よくある質問へはチャットボットが対応してくれますので、少ない人員でCSを運営できるようになるからです。
対応の質の均一化
チャットボットを導入すれば、適切な問いを顧客に返すことができ、対応の質を均一化できます。
オペレーターによる対応の場合、スタッフのスキル不足なら「たらい回し」が生じる可能性が高まります。
人の入れ替わりが激しい場合なら、オペレーションを習熟できていないスタッフが対応することとなり、適切な回答を返せないこともあるでしょう。
その点、チャットボットなら、事前に設定したルールに則って常に最適な回答を返せます。
対応品質を均一化するためにも、チャットボットは大いに役立ってくれるのです。
オペレーター負担軽減
チャットボットを導入すれば、オペレーターは「よくある質問」に対応せずにすみ、それ以外の複雑で高度な対応力が必要となる案件に注力できます。
また、チャットボットで対応しきれなかった問い合わせをオペレーターにエスカレーションする設定をしておけば、事前に一定の情報を得たうえで顧客対応ができます。
一から話を聞く必要がなくなるので、お客様への手間をかけることなく、オペレーターの負担を軽減することにつながります。
これは、企業が取り組むべき働き方改革への一手ともいえるでしょう。
今後、CSにチャットボットは不可欠となる

ある調査では、今後カスタマーサポート部門において「チャットボットは大きな存在感を示すものとなる」としています。
2016年には各種SNSやメッセージツールをベースに、各種チャットボットが開発されました。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいての「多言語対応接客」を目的として、対話型AIシステムの市場規模拡大が見込まれていました。
しかし、ご存じの通り新型コロナウイルスでオリンピックは延期となり、様々な業界では需要拡大どころではなくなりました。
感染症拡大を防止する目的で、業務を停止したり、範囲を縮小しなければならなくなった企業もあります。
ただ、どんな局面にあっても顧客からの問い合わせそのものが減るわけではありません。
商品/サービスによっては、「このようなときだからこそ問い合わせをしたい」「早期のトラブル解消が不可欠」というものもあります。
たとえ今回の新型コロナウイルス問題が早期に沈静化したとしても、次、いつ、何が起こるかわかりません。
CSのあり方が改めて問われた2020年、このタイミングでチャットボットへの理解を深め、一度は導入を検討しておくべきといえるでしょう。
CSに導入するチャットボットの選び方
チャットボットは、CSが抱える課題を解決して業務品質向上・業務効率化を図れる優秀なツールです。先にご紹介した通り多くのメリットがあることから、CSにチャットボットの導入を検討している方もいるでしょう。
ここでは、CSに導入するチャットボットの選び方について、5つのポイントに分けて解説しています。自社のCS業務に最適なチャットボットを選定するためにも、是非ご参考下さい。
AI型とシナリオ型
チャットボットには、大きく分けてAI型とシナリオ型の2つのタイプがあります。CSにはどちらのタイプも導入可能ですが、以下に説明する通り両者では特性が大きく異なります。
■AI型
- より人間の会話に近い高度な対応ができる
- 対応データが増えるほど回答精度を高めることができる
- 設定・メンテナンスの手間・時間が多くかかる
■シナリオ型
- 定型的な質問を得意とする
- 複雑な質問には不向き
- 導入・メンテナンスの手間・時間が少ない
速やかにCSにチャットボットを導入したい場合はシナリオ型の方が適していますが、長期的な視点で見ればAI型の方が高いパフォーマンスを発揮することができます。
チャットボットを選ぶ際には、自社のCSでどのように活用したいのかを考慮して、まずはどちらのタイプを選ぶのかを決める必要があります。
搭載された機能
チャットボットは、AI搭載型・シナリオ型といったタイプだけでなく、製品によって搭載されている機能も異なります。CSに役立つチャットボットの機能には、例えば次のようなものがあります。
- 聞き返し機能
- レコメンド機能
- レポート・分析機能
- 有人対応切替機能
- フォーム機能
- アンケート機能
- 評価コメント機能
- デザインカスタマイズ機能
- 外部連携機能
たくさんの機能が充実しているほど多くのことができますが、比例してコストも高くなるため、不必要な機能が搭載された製品を選ぶのは得策ではありません。
同じ価格帯の製品であれば搭載されている機能も類似しているため、自社が求める機能が揃った製品を複数比較検討して選ぶのがおすすめです。
各種ツールとの連携
チャットボットは、外部システムと連携させて顧客情報や業務連絡を行うことが可能です。CSにおいては、チャットボット単独で活用するよりも、FAQ・CRM・SFA・SNS等と連携させた方が効率的かつスムーズに業務を行うことができるため、できるだけ既存ツールとの連携を考えることがポイントとなります。
チャットボットは製品によって連携できるツールが異なるため、CSに導入する際には自社が利用する各種ツールとの連携が可能であるかの確認を行ったうえでツールを選ぶようにしましょう。
サポート体制
CSにチャットボットを導入しても、設定や運用が上手くいかなければパフォーマンスを発揮することができず、業務に役立てることもできません。チャットボットの設定・運用には専門的な知識やノウハウが必要となる機会が多いため、ベンダーのサポートを活用した方がスムーズであるケースもあります。
そのため、チャットボットを選ぶ際には、ベンダーのサポート体制について確認しておくことが重要です。ベンダーのサポートには、大きく分けてマニュアル・FAQの提供を行うタイプと、有人対応を行うタイプがあります。有人対応のサポートはコストも高くなりますが、きめ細やかなサポートを受けることが可能です。
チャットボットの導入・運用が初めてである場合や、社内に知識・スキルを持つ人材がいない場合は、安心材料として後者を選択しておくことをおすすめします。
費用
CSにチャットボットを導入するには、初期費用とランニングコストがかかるため、事前に確認しておく必要があります。どの程度の費用が必要であるかはチャットボットのグレードによって異なります。大まかな目安については次の通りです。
■ルールベース(シナリオ)型
- 初期費用:50,000円~200,000円
- ランニングコスト(月額):3,000円~50,000円
■AI搭載(機械学習)型
- 初期費用:200,000円~100,000円
- ランニングコスト(月額):100,000円~500,000円
基本的にスペックが高くなるほど、費用も比例して高くなる傾向にあります。
費用の安さを追求すると自社のCSに寄与できない場合があるため、自社が求める要件を満たせる最小限度の性能・機能を有する製品を選ぶのがポイントです。
【導入時の注意点】まずハイブリッド型を検討

チャットボットを選ぶときは、ボットによる自動応答と有人対応とを組み合わせたハイブリッド型を比較検討してみてください。
まず、質問はチャットボットが一時受けを行い、選択肢を提示することで回答へ導きます。
その回答が求めるものでないと意思表示した顧客については、「有人対応が必要なお客様」と判断し、オペレーターへとエスカレーションします。
ですが、1年中昼夜を問わずCSを稼働させることは現実的ではありません。
営業時間を定めているCSも多いことでしょう。
また、場合によっては営業時間を縮小したり、オペレーターの数を減らしたりしなければならない事態に遭遇することも考えられます。
チャットボットを導入することで、どのような状況下でも何割かは問い合わせに対応できる環境を整備することが可能になります。
ハイブリッド型チャットボットは、このような点で生産性向上にメリットがあるのです。
チャットボット導入の際には、使い分けができるようハイブリッド型を検討してください。
【導入時の注意点】チャットボット・FAQの管理はCSが行う

もしもチャットボットを導入したのなら、チャットボットそのもの、そしてFAQ(よくある質問とその答え)の管理はカスタマーサポート部門で行うようにしてください。
というのも、次の点でCSは社内でも能動的に動ける部門であるはずです。
- 顧客の生の声を一番多く聞く
- FAQで解決できなかった疑問を発見、FAQを増やせる
- 顧客の声を反映した最新のFAQを作れる
ここで一つ考えておきたいのは、「導入しようとしているチャットボットは、管理がしやすいものかどうか」というポイントです。
せっかくCSが顧客の生の声に触れても、問い合わせの数や質の変化に気づいても、自らの手で情報の更新ができなければ、スピードに欠けてしまいます。
また、新鮮な情報も時間の経過とともに劣化していきます。
この問題を回避するためには、「管理しやすいチャットボットの導入」をし、「チャットボットとFAQはCSが管理をする」というルールを定めることです。
まとめ
CS運営にあたり、チャットボットの導入は「一度は検討してみるべき」とおわかりいただけたでしょう。
チャットボットは、「ハイブリッド型」で「FAQ管理が容易」なものから、あなたのビジネスに合ったものを選びましょう。
弊社のご提供する「チャットディーラー」は、FAQ管理が容易なハイブリッド型チャットボットです。
導入時には、御社専属のスタッフが丁寧にサポートいたしますので、運用での心配も無用です。
もしもチャットボットに関心があるなら、ぜひチャットディーラーまでお気軽にお問合せください。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。