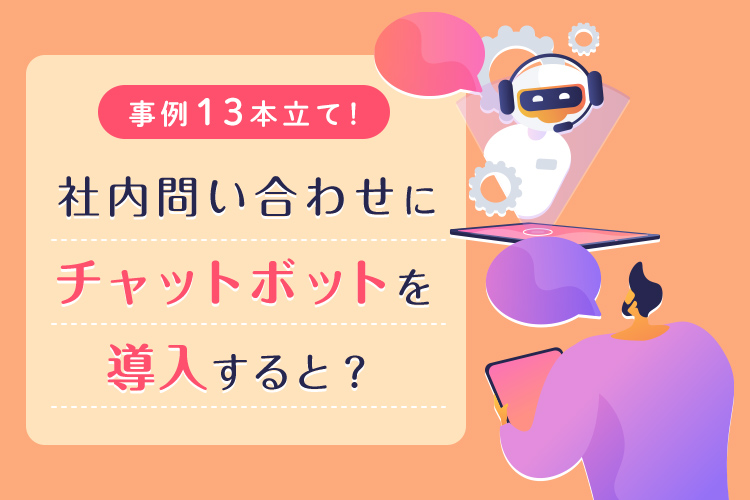ナレッジマネジメントツールとは?種類や選び方を徹底解説
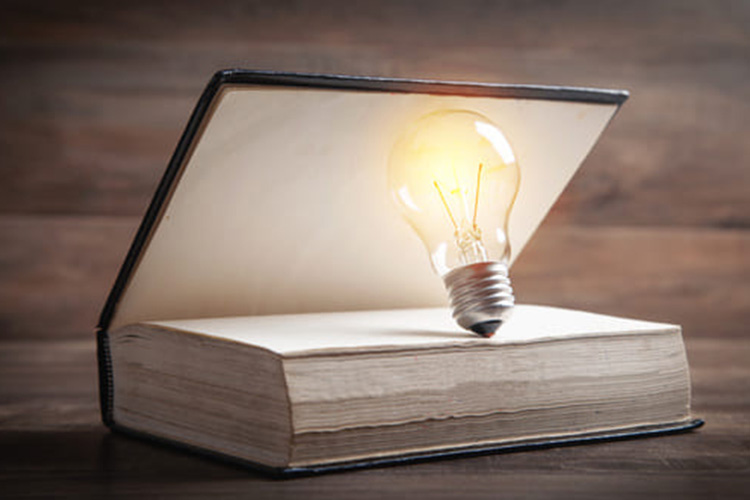
企業間競争の激化・コロナ禍の長期化・トレンドの移り変わりなど、現代のビジネスを取り巻く環境は非常に厳しいのが現状です。このような状況に対処すべく、企業はさまざまな戦略・施策・手法を駆使して生産性向上・ビジネスの成長を試みています。
組織が保有する情報の積極的な活用・有効活用を目指すナレッジマネジメントも、現在多くの企業が注目している取り組みのひとつです。
当記事では、ナレッジマネジメントの推進に役立つナレッジマネジメントツールについて、概要・メリット・種類・選び方・おすすめ製品を解説していきます。
ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、企業組織・各人材が蓄積している知識・経験を組織内で共有することで、積極的・効果的な活用を行っていくマネジメント手法のことです。知的資産を有効活用して企業の生産性向上・業務効率化・競争優位性の発揮といった成果を得ることを主な目的としています。
現代社会は、事業寿命の短命化・ビジネスのIT化・競争激化などさまざまな要因により、企業は的確でスピーディーな経営を行うことが求められている時代です。このような状況に対応する有効な手段として、ナレッジマネジメントに大きな注目が集まっています。
ナレッジ共有ツールとの違いは?
社内でのナレッジ活用を促進するためのツールには、主にナレッジ共有ツール・ナレッジマネジメントツールという2種類のツールがあります。基本的な機能や役割はどちらのツールでも大きな違いはありませんが、強いて挙げれば以下のような違いがあるため、ツールの導入を行うのであれば理解しておくことをおすすめします。
-
ナレッジ共有ツール
企業が業務を通じて蓄積した情報を社内で効率的に共有することを目的としたツール
-
ナレッジマネジメントツール
SECIモデル等のナレッジマネジメント理論の実践に基づき設計されたツール
取り扱う情報の範囲や種類は共通していますが、ナレッジマネジメントツールの方が、単に情報共有を行うだけでなく情報の分類・変換・取り扱いなど、より実践的な活用を視野に入れたツールであると解釈できます。
ナレッジマネジメントにおけるよくある課題点
ナレッジマネジメントは現代の企業に重要な施策であるものの、導入や実践にあたっては数多くの課題が伴うという事情があります。ここでは、ナレッジマネジメントによく見られる課題点について解説します。どのような課題があるのかを確認しておきましょう。
-
ナレッジの検索に時間がかかる
ナレッジ共有を行っているものの、情報が整理分類されておらず雑多な状態であると、必要な情報を探すのに時間がかかる。業務にナレッジやノウハウを活用することも難しくなる。
-
必要な情報や重要な情報が埋もれている
ナレッジの蓄積に注力しており、必要性や重要性の高い情報をプールしているものの、検索性が低いと埋もれてしまう。認知すらされていない場合もある。
-
ナレッジが投稿されない
ナレッジ投稿には手間や時間がかかることから、ナレッジマネジメントを導入したものの誰も投稿を行わず、ナレッジが蓄積されないケース。
-
ナレッジの共有が社内に浸透しない
ナレッジマネジメントを導入したものの、社内に実践する文化が浸透せず、いつまでたっても推進できないというケース。
ナレッジマネジメントにツールを活用するメリット
ナレッジマネジメントは、社内に仕組みを構築すれば専用のツールがなくとも導入することはできますが、効率性や利便性の観点から合理的ではありません。効率的に取り組むためには、ナレッジマネジメントツールの活用がおすすめです。
ここでは、ナレッジマネジメントにツールを活用する主なメリットについて解説します。なぜ、ナレッジマネジメントにはツールの活用が推奨されているのかを確認しておきましょう。
ナレッジの属人化を防ぐ
ナレッジマネジメントでは、業務に必要なナレッジ・ノウハウやトラブルシューティング等を共有することで、特定の人物に業務スキルや業務の進捗が偏る属人化を防ぐことも重要な目的のひとつです。
ナレッジマネジメントツールを活用すれば、スムーズに情報の共有と活用を行える体制を実現することが可能になります。ナレッジの属人化を防いで標準化を図れることも大きなメリットです。
ナレッジ登録の負荷を抑える
ナレッジマネジメントを推進するには、社員が積極的にナレッジの登録を行い、ナレッジやノウハウをできるだけたくさん蓄積していくことが重要となります。しかし、ナレッジの登録は手間と時間がかかるため、社員が通常業務を抱えながら登録を行うことは大きな負担となります。
ナレッジマネジメントツールであれば、テンプレート・エディタ等のナレッジ登録を支援する仕組みや機能が充実しているため、ナレッジ登録の負荷を軽減することが可能になります。ナレッジ登録の障壁をできるだけ取り払い、ナレッジ登録を推進できることも大きなメリットです。
ナレッジの検索性を向上させる
ナレッジマネジメントを上手く推進するには、ナレッジを活用するユーザー側の利便性を向上させることも検討する必要があります。ナレッジマネジメントツールには、ナレッジを集約して一元管理を行うだけでなく、必要なナレッジをスムーズに探し出すための検索機能も充実しています。
多角的な検索や高度な検索など、利用者に便利な機能が搭載されているため、ツールを導入することでナレッジの検索性を向上させられることもメリットです。
教育コストの削減
ナレッジマネジメントツールの導入により、ナレッジの共有や活用をスムーズに行える体制が実現すれば、人材育成や業務の引継ぎもスムーズに行うことが可能となります。
新人や新任担当者は自身で学習を行うことが可能となり、全て有人で教育や引き継ぎを対応する必要が無くなるため、教育にかかるコストやリソースを削減できることもメリットです。
ツール選びで知っておきたいナレッジマネジメントの基礎

ナレッジマネジメントにツールを活用するにあたっては、ツール任せにするだけではなくナレッジマネジメントの基礎を理解しておく必要があります。自社のナレッジマネジメントに適切なツールを選ぶためにも、基礎を知っておくことは重要です。
以下にて詳しく解説していますので、ぜひご参考下さい。
ナレッジマネジメントの4つの分類
ナレッジマネジメントは、その目的や手法によって以下4つのタイプに分類されます。これからナレッジマネジメントの実践を行う方は、まずはどのようなタイプがあるのかを把握しておきましょう。
-
専門知識型
組織内に存在する専門知識を集約してデータベース化することで、効率的なナレッジの共有・活用を実現する手法。業務効率化・業務標準化・人材育成などに役立てることができます。
-
ベストプラクティス共有型
成績優秀者・高能力者など模範・モデルとなる社員の行動・思考を形式知化して共有する手法。組織全体のマインドセット・スキル・パフォーマンスのベースアップに適しています。
-
顧客知識共有型
顧客対応・対応の方法・対応のプロセスに関する情報を蓄積・整理・共有して業務に役立てる手法。ナレッジを参照することで、顧客対応の品質向上・効率化・業務改善に繋げることができます。
-
経営資本・戦略策定型
組織内のさまざまな知識を収集・分析することで、経営戦略・事業戦略の策定に役立てる手法。膨大な情報を集めて多角的に分析するため、意思決定や判断の確度を高めることができます。
ナレッジマネジメントツールの種類
ナレッジマネジメントツールには大きく分けて以下5つの種類があるため、まずは全体の大枠としてどの種類のツールが自社に合っているのかを検討することが重要です。
-
データベース型
いつでも検索できるようにナレッジを蓄積・共有
-
データマイニング型
蓄積したデータを分析して新たなナレッを創出
-
社内wiki型
社内ナレッジをツール上で整理・編集して共有
-
グループウェア型
グルーウェア上でファイル共有・コミュニケーション・スケジュール管理等を行う
-
ヘルプデスク型
FAQツール・チャットボット等の一問一答形式のツール
どのようなナレッジマネジメント手法を実現したいのか、どのような課題を解決したいのかによって、最適なツールの種類も定まってきます。
まずは自社の現状を把握すると同時に多くの事例を参考にして、理想とするナレッジマネジメントのモデルを検討してみましょう。
ナレッジマネジメントツールを選ぶポイント

ナレッジマネジメントツールは、製品によって機能・操作性・連携性・セキュリティなどが異なるため、ツールを選ぶ際には自社の目的やニーズを満たせるものを選ぶことが重要です。
ここでは、ナレッジマネジメントツールを選ぶ際に見るべきポイントとチェック方法について解説します。
ツール選びで失敗しないためにも、ぜひご参考下さい。
求める機能が搭載されているか
ナレッジマネジメントツールに搭載されている機能は製品によって異なるため、自社が求める機能が搭載されている製品を選ぶことが重要です。
まずは先にご紹介したナレッジマネジメントツールのタイプを定めて候補となる製品のピックアップし、続いて自社の機能要件を満たせる製品を比較検討していく手順がおすすめです。
必要な機能が搭載されていないツールを導入すると、ナレッジマネジメントの課題解決や目標達成を実現することが難しくなるため、機能要件については慎重に精査するようにしましょう。
誰もが使いやすいか
ナレッジマネジメントツールは、機能・性能だけでなく使いやすさを重視して選ぶことが非常に重要。なぜなら、ツールの使いやすさは社内でのナレッジマネジメント推進・活性化に大きく影響するためです。
ツールの使いやすさを判断するポイントは、大きく分けて以下の2点。
- 簡単な操作でナレッジの登録・編集を行うことができるか
- 必要なナレッジを簡単に探して見つけることができるか
無料トライアルを活用して、社内メンバーのITリテラシーを考慮して誰もが容易に扱えるナレッジマネジメントツールを選びましょう。
他のシステムとの連携ができるか
ナレッジマネジメントツールは、単体で活用するよりも、顧客管理システム・販売管理システム・チャットボットといった他のシステムと連携させて情報を一元管理することで、ナレッジの共有・活用をさらに効率化・利便化することができます。
そのため、ツールを選ぶ際には他のシステムとの連携性に優れた製品を選ぶことも重要なポイントです。社内でナレッジマネジメントに活用できそうなツール・システムの洗い出しを行い、これらと連携可能なシステムを選ぶようにしましょう。
セキュリティ対策が十分か
ナレッジマネジメントツールで扱う情報は、ビジネスの成果やパフォーマンスに直結する非常に重要な情報です。いわば自社独自の情報資産であり、外部に漏洩してはならない機密情報です。
そのため、ナレッジマネジメントツールに実装されているセキュリティに関しては、特に重点的にチェックを行う必要があります。
製品ホームページに掲載されている情報だけでなく実績・評判等も加味して、安心して自社の情報を取り扱うことができるツールを選ぶことが重要です。
対応しているデバイス
ナレッジマネジメントツールを選ぶ際には、対応しているデバイスにも着目しておく必要があります。外出先や出張先でモバイル端末からもアクセスを行う必要がある場合は、マルチデバイスに対応している製品を選んでおく必要があります。
無料トライアルができるか
ナレッジマネジメントツールには優良な製品が数多く存在しますが、実際に使用してみないことには自社の状況や環境に適しているか判断するのは困難です。そこで重要となるのが、無料トライアルを実施してツールの使用感や操作性を確認しておくことです。
トライアルを実施して納得したうえで導入を行えば、ツールの導入に失敗する確率も大幅に低減することが可能となるため、製品選びの際には無料トライアルに対応した製品を選ぶことがポイントとなります。
おすすめのナレッジマネジメントツール6選

ナレッジマネジメントツールは数多くの製品がリリースされており、その機能や性能もさまざま。どのツールを選べばよいか分からない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、おすすめのナレッジマネジメントツールを厳選して6つご紹介していますので、ツール選びの際にはぜひご参考下さい。
チャットディーラーAI

チャットディーラーAIは、AI搭載型のチャットボットツールです。チャットディーラーAIに社内のナレッジを集約・登録しておくことで、ナレッジを蓄積するだけでなく、活用を促進することができます。従業員はチャット画面から会話形式で問い合わせ内容を入力するだけで回答が得られるため、業務効率の向上や、問い合わせ対応担当者の負荷軽減につながります。
また、チャットディーラーAIは問い合わせ内容の分析が可能で、分析内容をもとにナレッジを充実させたりといった対応が可能です。さらに、TeamsやLINEWORKSなどのビジネスツールとの連携もでき、使い慣れたプラットフォームの画面上から問い合わせが行えます。これにより利用率が向上すれば、さらなる効率化が実現できます。
チャットディーラーAIは豊富なテンプレートと学習済AIにより社内の情報をスムーズにナレッジ化することができるため、手間と時間を省いて短期間で実用化できることが大きなメリットです。社内ナレッジを活用した問題・課題の自己解決を促進したい場合におすすめのツールとなります。
NotePM
NotePMは、充実した機能と扱いやすさから、7,000社以上に導入されている社内wikiタイプのナレッジマネジメントツールです。
高機能エディタ・テンプレートが完備されており、社員誰もが気軽にwikiを書き込むことで、ナレッジを効率的に収集・蓄積。強力な検索機能や情報共有機能で、必要な情報をスムーズかつスピーディーに取り出すことが可能です。
情報やメンバーの管理に便利なアクセス制限・データ整理・外部連携といった機能も充実。
定番かつ実績のあるナレッジマネジメントツールを導入してみたい方は、ぜひNotePMを検討してみることをおすすめします。
Qast
Qastは、Q&A・wikiタイプのナレッジマネジメントツールです。誰でも扱いやすい共有の方式と、直感的に操作できるシンプルなUIが大きな特徴。ナレッジマネジメントのハードルを徹底的に引き下げることで、ナレッジの蓄積・共有・閲覧を加速することができます。
蓄積したナレッジを分かりやすく整理する機能や、欲しいナレッジをすぐに探せる検索機能も充実。社内のナレッジマネジメントをスムーズかつスピーディーに推進して組織のパフォーマンス向上につなげたい方は、ぜひQastを検討してみることをおすすめします。
DocBase
DocBaseは、10,000社以上に導入されている、特にテレワークにおける実績が豊富なナレッジマネジメントツールです。
テレワーク環境下で便利な外部メンバー共有機能・オンラインコミュニケ―ション機能などが充実しており、セキュリティ対策も非常に充実。セキュアな環境下で効率的な情報共有・情報活用を可能とすることができます。操作性・利便性にも優れており、情報共有や情報活用に要する時間や負担も大幅に削減することが可能です。
ITエンジニア等の専門職にも重宝されている本格的なナレッジマネジメントツールであるため、テレワーク環境下で高度なナレッジマネジメントを実践したい方にはおすすめです。
Qiita Team
Qiita Teamは、大企業を中心に5,000社以上の導入実績を持つ社内向けナレッジマネジメントツールです。
誰でも簡単・手軽に扱えるテキストベースのシンプルな情報共有・コミュニケーションを主軸としているのが大きな特徴で、組織内でのナレッジ共有・コミュニケーション活性化に非常に効果的。ナレッジの登録・共有・活用に伴う手間・時間・心理的障壁を取り除くことで、スムーズなナレッジマネジメントを実現することができます。
ツールの有用性・効果性は実績により証明されているため、初めてナレッジマネジメントツールを導入する方からナレッジマネジメントの成功率を高めたい方まで、幅広くおすすめできるツールです。
Kibela
Kibelaは、企業が求める高度な管理要件と柔軟な情報共有体制を満たすことができる、優れた機能・性能を持つナレッジマネジメントツールです。
あらゆる業務体制・業務フローに対応させやすく、企業規模・企業形態を問わず導入できることが大きな特徴。徹底的にムダを省いてシンプル化されているため、ITリテラシーの高低に左右されず高度で柔軟な情報共有・情報活用を行うことができます。
個人の意見・アイデア等を発信しやすいため、組織内での意見交換やコミュニケーションを活性化しやすいことも大きなポイント。
機能性と利便性を両立したナレッジマネジメントツールを導入したい方には非常におすすめです。
PKSHA FAQ(旧:OKBIZ. for FAQ)
PKSHA FAQは、800社以上に導入されており、平均40%以上の問い合わせ件数削減という実績を持つナレッジマネジメントツールです。
FAQの作成・公開・分析・運用・改善といった一連の作業を誰でも簡単に行えることが大きな特徴。高性能な検索システムにより、利用者は欲しいナレッジをスムーズに取り出して業務の遂行や課題解決に役立てることができます。
機能性や利便性に優れており、さまざまな業界・業種で活用されているため、初めてナレッジマネジメントツールを導入する方から自社に合った運用を行いたい方まで、幅広くおすすめできるツールです。
esa
esaは、3,000以上企業・団体で利用されている、チームでの情報共有だけでなく情報を育成していくことを重視して開発されたナレッジマネジメントツールです。
esaは最初から完璧を目指さずに不完全でも公開を行い、公開後の情報を何度も更新して整理していくための機能が充実。ユーザーが情報の共有や情報の育成を楽しみながら実施していけるような仕組みや配慮が施されているのもポイントです。
実務におけるナレッジマネジメントは、何度も追加や改善を重ねてこそ有用性を発揮できるのが一般的です。より実践的で実用的なナレッジマネジメントを実現したい方は、ぜひesaを検討してみることをおすすめします。
ナレッジマネジメントツールを導入する際の注意点
ナレッジマネジメントツールは有用性の高いツールですが、導入の際にはいくつか注意すべき点があります。
以下に解説していますので、これからツールの導入を考えている方は、ぜひご参考下さい。
導入の目的や理念を周知しておく
ナレッジマネジメントツールの導入を行う際には、導入の目的や導入の意義について社内で周知を行い、社員からの理解を得ておくことが重要です。なぜなら、通常の業務を抱えながら新たな取り組みを行うにあたって、コンセンサスを得ないまま経営陣の意向のみで推進を行っても、社員から受け入れられず導入が上手くいかないためです。自身のナレッジを他社に共有するのに抵抗があるベテラン社員も多くいます。
このような障壁を解消してスムーズに導入を行い、社内でのナレッジマネジメントを定着させるためにも、導入により目指すゴールやナレッジ共有を実施する意義やベネフィット等を、社内メンバーが納得する形で周知しておく必要があります。
ナレッジを登録しやすい工夫
ナレッジマネジメントを推進するにあたっては、いかに社員に積極的なナレッジ登録を行ってもらうかが成否を分けるポイントとなります。必要十分なナレッジが蓄積されないことには、ナレッジの共有はもちろんナレッジの有効活用も実現できないためです。
しかし、ナレッジの登録には時間や労力が多く必要となるため、社内で周知しただけではなかなか積極的な登録は望めないものです。そのため、扱いやすいツールの導入・テンプレートの作成・登録者への評価・リーダーが率先して登録を啓蒙するなど、仕組み・評価・社内文化など多方面から積極的なナレッジ登録が行われるような状況を作り出すことが重要なポイントとなります。
まとめ
ナレッジマネジメントツールは、ナレッジマネジメントの推進に伴う負担を軽減して、効率的でスムーズなナレッジ共有をサポートしてくれる優れたツールです。アナログな手法で実践するナレッジマネジメントと比べると、大幅な成果の向上を期待することができます。
導入にあたっては、複数の製品を比較検討して自社の目標達成や課題解決に適したツールを選ぶことが重要なポイント。これからナレッジマネジメントを推進する方は、ぜひ当記事を参考にして、最適なツールの導入・活用してプロジェクト推進に役立てて下さい。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。