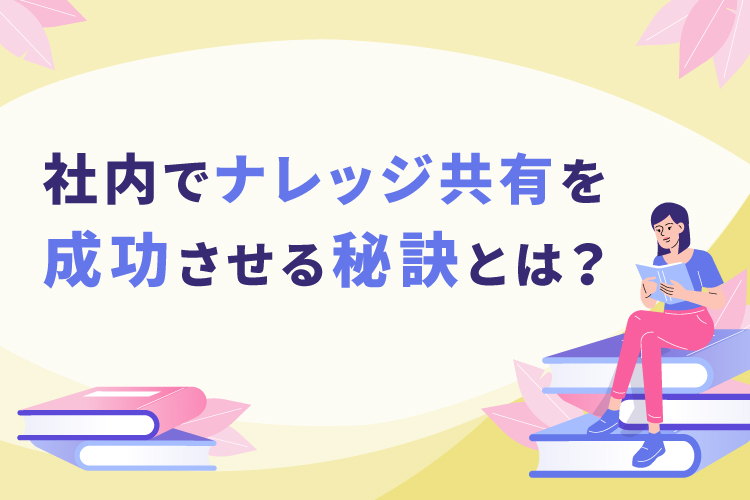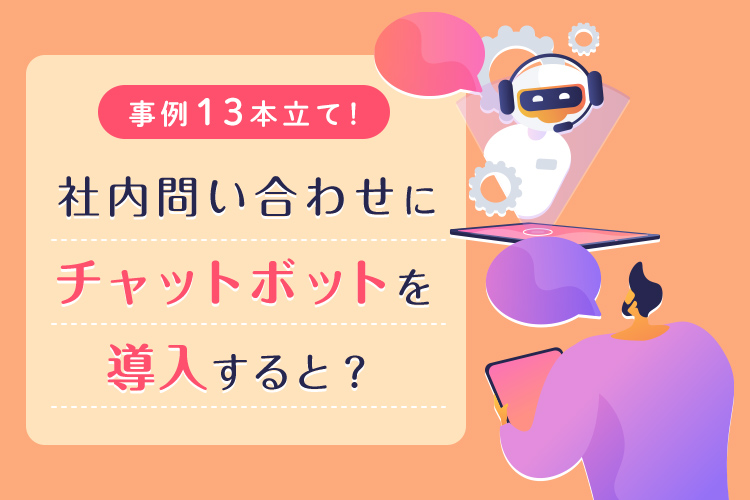ナレッジマネジメントとは?知っておきたい基礎理論から詳しく解説

現代のビジネスを取り巻く環境は競争や変化が激しく、生き残るために企業は自社が保有する情報を有効活用・徹底活用していくことが求められています。そのためのマネジメント手法が、今回ご紹介するナレッジマネジメントです。
当記事では、ナレッジマネジメントの概要・必要性・考え方・基礎的な理論・メリット・導入方法・主な手法について解説していきます。
これからナレッジマネジメントを実践していきたい方が知識の土台を構築するのに役立つ情報を提供していますので、ぜひご参考下さい。
ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、企業やそこで働く社員が培ってきた知識・技術・経験等を組織全体で共有することで、企業の生産性向上やイノベーション促進を目指していくマネジメント手法のことです。
分かりやすく解説すると、特定の部署・個人のみが保有している情報や組織内に埋もれて活用されていない情報などを洗い出し、組織全体で共有できるように仕組みや環境を整えていくという活動となります。
ナレッジマネジメントを実践して成功を収めた企業の事例も目立ち始めたことから、現在では多くの企業が導入・推進に尽力しています。
ナレッジマネジメントが注目を集める理由
ナレッジマネジメントが近年大きく注目されるようになった理由には、社会や企業の在り方が変化したことが挙げられます。
ビジネスモデルの進化・業務のデジタル化により、企業内で行われている各種業務が高度化しています。一方で個人の業務範囲や裁量も拡がりつつあり、一人ひとりの社員がナレッジ・ノウハウを蓄積したまま共有されにくいという状況となりつつあります。このような状況は、組織内に存在する知識資産の活用という観点からすると非効率です。
企業がより高い生産性を発揮して業績を伸ばすには、高度化しつつも個人に偏ったナレッジ・ノウハウと、企業全体が有する情報を組織内で共有して活かしていくことが重要です。
そのための具体的な方法・手段として、ナレッジマネジメントの概念・理論が注目を集めています。
ナレッジマネジメントの目的
ナレッジマネジメントを学んでこれから実践していきたいのであれば、同マネジメント手法を実践する目的についても理解しておく必要があります。
ナレッジマネジメントは汎用性が高くさまざまな目的が設定されますが、具体的な例としては以下のような目的があります。
-
業務効率化
既存ナレッジをチーム・組織全体で活用することで、業務効率の向上や業務フローの改善を図る。
-
人材育成
組織ならびに在籍する人材が培ってきたナレッジ・経験・ノウハウを活用できる体制を構築することで、効率的・効果的な人材育成を目指す。
-
サービス・サポート品質の向上
セールス部門やカスタマーサポート部門での優れた対応ノウハウ・成功事例・失敗事例を収集・共有することで、部門全体のパフォーマンス強化を図る。
-
リスクマネジメント
社内でのあらゆるリスク事例やトラブル対処法を共有しておくことで、万が一の際の早急な対応や事業の継続が可能。
ナレッジマネジメントを実施する際には、漠然と同マネジメント手法を実施すること自体が目的とならないように、上記のように具体的な目標を設定しておくことがポイントとなります。
ナレッジマネジメントに必要な考え方

ナレッジマネジメントを実践するには、暗黙知・形式知と呼ばれる保有する2種類の知識が必要不可欠です。
これらは、いわば組織が持つ知識の分類です。それぞれ異なる性質を持つため、それぞれの特徴と違い、ナレッジマネジメントにおける活用方法を理解しておく必要があります。
以下に解説していきますので、ぜひご参考下さい。
暗黙知と形式知
ナレッジマネジメントの考え方では、組織が持つ知識を暗黙知・形式知という2つの種類に分類しています。まずは、これら2種類の知識の概要について理解しておきましょう。
-
暗黙知
個人が持つ、経験により蓄積された知識・ノウハウ・勘といった知識。そのままでは知識として共有が難しいことが特徴。
-
形式知
言葉・文章・図表等を用いて表現された知識。実際に資料として共有しやすいことが特徴。
暗黙知を形式知へ変える
個人が培った勘やコツといった暗黙知は、そのままでは他者に伝えることが難しいため、組織内で活用されずに属人化してしまいやすい傾向があります。そのため、言葉・文章・図表といった客観的に情報を伝達できる手段を用いて暗黙知を形式知へ変換していくことが、ナレッジマネジメントの基本的な考え方となります。
暗黙知を形式知へ変換することで、知識の共有・活用・ブラッシュアップといったことがスムーズに行えるようになり、組織的にナレッジを活用することが可能となります。
ナレッジマネジメントの基礎「組織的知識創造理論」とは

組織的知識創造理論とは、上記の暗黙知・形式知を相互に変換・作用させることで、知識的な組織経営・組織運営を可能にする理論のことです。
そこで重要となるのが、以下のような知識変換を行うための方法・理論です。
- SECIモデル
- 場(ba)
- 知識資産
- ナレッジリーダーシップ
ここでは、上記の知識変換に必要となる4つの方法・理論についてそれぞれ解説していきます。
知識変換の4モード(SECIモデル)
SECIモデルとは、個人が有する暗黙知を形式知に変換してビジネス・組織経営に活かすことを目的としたモデルです。同モデルにおいては、以下4つのモードを経て知識変換と知識の活用を具体化していきます。
-
Socialization:共同化
各個人が持つ暗黙知を、共通の体験等を通じて他の個人に伝達・移転する。
-
Externalization:表出化
共通の暗黙知を言葉・文章・図で表現された形式知へと変換。
-
Combination:連結化
既存の形式知と新しい形式知を組み合わせることで、新たな形式知を生み出す。
-
Internalization:内面化
形式知を何度も繰り返して体得することで、形式知を暗黙知として落とし込む。
SECIモデルは、ナレッジマネジメントの基本であり中核でもある知識変換を行うために欠かせないモデルです。ナレッジマネジメントを実践していくうえでベースとなる概念であるため、必ず理解しておく必要があります。
場(ba)
場(ba)とは、ナレッジマネジメントの実践における、実際にナレッジが共有されるための場所のことです。
会議室・休憩室・喫煙所といった実在の場だけでなく、ミーティングツール・コミュニケーションツールといったオンライン上の仮想空間も場に該当します。
ナレッジマネジメントを推進・活性化するには、社員がナレッジの共有や獲得した知識の理解が促進されるような場を積極的に作り出していくことが重要となります。
知識資産
知識資産とは、企業が保有する人材・技術・組織力・ブランドといった目に見えない資産のことです。従業員レベルで考えると、個人が培ってきた知識・スキル・ノウハウ・経験などが該当します。
さまざまな種類の知識資産がありますが、大きく分けると以下3つのタイプに分けられます。
-
人的資産
人材が有する知識・能力・経験・ノウハウ。離職・退職等で失われる資産。
-
構造資産
企業が活用しているシステム・データベース・組織力等。人材の離脱が起こっても企業に残る資産。
-
関係資産
企業イメージ・ロイヤリティ・取引先との関係といった企業と外部の関わりややりとり全て。
ナレッジマネジメントの実践にあたっては、ナレッジを分類したり有効活用したりするために、知識資産についての把握・理解を深めておくことが必要となります。
ナレッジリーダーシップ
ナレッジリーダーシップとは、ナレッジマネジメントを推進するリーダーが取るべき行動を示した概念です。
ナレッジマネジメントのプロジェクトは、仕組みを構築して周知するだけで成功できるほど簡単ではないため、リーダーが積極的に組織を牽引していくことが成否を分けるポイント。社内の誰よりもナレッジマネジメントを理解した人物をリーダーに抜擢して、積極的なナレッジの共有・目標達成・課題解決を実行させていく必要があります。
ナレッジマネジメントのメリット

続いて、ナレッジマネジメントを導入することで得られる主なメリットについて解説します。
業務効率化
ナレッジマネジメントを推進すれば、社内の誰もが必要な時に必要な情報をすぐに参照することができるため、業務効率化を実現できることが最大のメリットです。業務のノウハウから問題解決まで、あらゆる情報をナレッジマネジメントツール上で把握できるため、不要なコミュニケーションコストを削減して時間や労力のロスを低減することも可能となります。
業務効率化を実現するためには、ナレッジマネジメントを業務プロセスに上手く組み込むことや、細かく改善を重ねて常に必要な情報を網羅しておくことがポイントです。
属人化の防止
属人化とは、業務を行う方法や進捗が、特定の担当者に依存して共有されていない状態を指します。この属人化が生じると、特定の人物に業務が集中したり、業務がブラックボックス化したりするなど、企業の生産性や業務効率を大きく阻害する原因となります。
ナレッジマネジメントを推進すれば、業務に必要なナレッジ・ノウハウを常時共有することが可能となるため、属人化の解消には最適です。誰もが状況を把握して同じ品質の業務を行える状況が実現するため、企業の生産性・チーム全体のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
人材育成に活かせる
ナレッジマネジメントは人材育成にも活用することができます。人材の育成に必要となるナレッジを集約・共有することで、自社の商品・サービスに関する知識・業務のノウハウ・問題解決など、さまざまなナレッジを新人社員が自身で習得することができます。これにより新人社員の早期戦力化・研修に要する工数・コスト削減につながります。
従来のアナログな手法による人材育成は企業にとっても負担が大きいものです。このような課題を解決してスムーズに人材を成長させられることは、企業にとって大きなメリットとなります。
ナレッジマネジメントのポイント
ナレッジマネジメントをスムーズに推進して成功確度を高めるためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
ここでは、ナレッジマネジメントに取り組む際に意識すべきポイントについてご紹介します。
必要な情報を探しやすい仕組みをつくる
ナレッジマネジメントの実施にあたっては、ナレッジが積極的に活用されるように、利用者が必要とする情報を探しやすい仕組みを構築しておくことが重要なポイントです。
まずはオンライン上から時間・場所に関わらずナレッジを参照できるように、ナレッジマネジメントツールの導入を行っておきましょう。
ツールの導入によりナレッジ活用の利便性・効率性は高まりますが、より高いパフォーマンスを得るためには、高性能な検索機能を備えたツールを選び、情報の検索性を高めておくのが効果的です。
利用者がスムーズに情報を探すことができなければ、社内でのナレッジマネジメント推進も上手くいかないため、情報を探しやすい仕組み作りには徹底的に注力することをおすすめします。
積極的に情報を登録できる仕組みを作る
ナレッジマネジメントを活性化するには、ツール上にたくさんのナレッジが蓄積されている必要があります。そのため、社内のメンバーが積極的に情報の登録を行うような仕組み作りを行っておくことも重要なポイントです。
単にナレッジの登録を促すだけでは、以下のような理由からナレッジの登録が進まないという事情があります。
- ナレッジの登録に時間と手間がかかる
- 通常業務が阻害される
- 自身が持つノウハウや経験を公開したくない
そのため、以下のような仕組み作りを行うことで、ナレッジ登録の負担軽減ならびに心理的障壁の除去を行うことが効果的となります。
- スムーズにナレッジの登録が行えるテンプレートを完備
- 会社側がナレッジ登録のための時間を捻出する
- ナレッジ登録者にはインセンティブや評価を提供
ナレッジの登録が進まずにナレッジマネジメントが失敗してしまうケースは多く見られるため、積極的に情報が登録されるように万全の仕組みを構築しておきましょう。
ナレッジマネジメントの導入手順

ナレッジマネジメントは、さまざまな知識・手法を駆使して企業の目的・状況に合わせた導入を行う必要がありますが、基本的な導入手順の型はある程度決まっています。
ここでは、一般的なナレッジマネジメント導入の手順について解説します。
-
1. ナレッジの発見
最初のステップは、ナレッジマネジメントに活用するためのナレッジの発見です。調査・観察・インタビュー・アンケート等のさまざまな方法を駆使して、有益なナレッジの発見を試みます。
-
2. ナレッジの収集
発見した組織内のナレッジを収集。暗黙知の状態で集めたナレッジを文書化・言語化して形式知化していきます。
-
3. ナレッジの共有
形式知化したナレッジを、必要とする人々が実際に共有して活用できるようにするプロセス。データベース・ツール・マニュアル等を駆使して仕組みや環境を整えます。
-
4. ナレッジの適用
実際に共有しているナレッジを業務に活用するプロセス。目標達成・課題解決・業務改善・意思決定などにナレッジの適用を行い具体化を図ります。同時に、ナレッジ共有・活用を社内に浸透させていきます。
ナレッジマネジメントのタイプ
ナレッジマネジメントの導入を成功させるには、自社に適した情報資産の活用目的・活用方法を検討することが最も重要なポイントとなります。そこで必要となるのが、ナレッジマネジメントの4つのタイプを把握しておくことです。
ナレッジマネジメントは、以下の図のように、知識資産活用目的・知識資産活用手段の性質によって、4つのタイプに分類することができます。
| 改善 ← 知識資産活用目的 → 増価 | ||
|---|---|---|
| 集約 ↑ 知識資産活用手段 ↓ 連携 |
||
| ベストプラクティス共有型 ・成功事例の移転 ・過去事例の再活用 ・知識レポジトリ共有と知識採掘 |
知的資本型 ・知識資産と企業価値の直結 ・潜在的知識資産からIPまで包括的な知識戦略 |
|
| 専門知ネット型 ・グローバルな専門家の知のネットワークによる問題解決 |
顧客知共有型 ・顧客との知識共有 ・顧客への継続的知識提供 顧客関係マネジメント、ワン・トゥ・ワンマーケティング |
|
出典:書籍「知識経営のすすめ」野中郁次郎・紺野昇 著
上記4つのタイプの概要についてそれぞれ解説します。
ベストプラクティス共有型(改善×集約)
ベストプラクティス共有型とは、成績優秀者・高能力者といった組織内で模範となる社員の行動・思考を集約・共有するタイプのナレッジマネジメント手法です。模範的社員の行動・思考パターンをもとに導き出した「ベストプラクティス」を共有することで、組織・チーム全体のスキルやパフォーマンスを向上させることを目的としています。
非常に実践的な手法であるため、実務に対する有用性・効果性が高いことが大きな特徴です。より有益にベストプラクティスを活用するためには、いつでもナレッジを参照・活用できる仕組みを用意しておくことがポイントとなります。
専門知ネット型(改善×連携)
専門知ネット型とは、組織内の専門知識を持つ人材をネットワークで結び、課題解決や意思決定に役立てるタイプのナレッジマネジメント手法です。
現場レベルにおいても、専門知識をデータベース化することで、業務品質や業務スピードの向上など、組織全体のパフォーマンスの底上げを期待することが可能です。
情報の共有には、グループウェア・FAQツール・チャット・電子メールなど、日常的な情報共有ツールやコミュニケーションツールが活用されます。
知的資本型(増価×集約)
知的資本型とは、特許・著作権を有するブランド・制作物・プログラムから、社員が有する潜在的に存在する知識まで、組織内のあらゆる知的資本を分析・活用していくナレッジマネジメントのタイプです。
さまざまな知識を包括的・多面的に分析・活用することが大きな特徴。詳細な分析結果が得られることや的確な見直し・改善のポイントを見いだせることから、主に経営戦略・事業戦略の策定を行う際に活用される手法となります。
顧客知共有型(増価×連携)
顧客知共有型とは、顧客対応に関する知識の共有を実施するナレッジマネジメントのタイプです。
セールス部門やカスタマーサポート部門の業務を通じて、顧客対応の事例・対応ノウハウや対応方法・顧客からの意見や感想といった情報をナレッジとして集約・共有。これらの情報をスムーズに参照できる体制を整えることで、提案・対応の質・スピードを高めることができます。
近年注目されているワン・トゥ・ワンマーケティングの実現には欠かせない手法です。
導入時の注意点
ナレッジマネジメントの導入にあたっては、より良いパフォーマンスを発揮するためにも、失敗のリスクを回避するためにも、注意しておくべき点があります。
-
PDCAを継続的に実施
ナレッジマネジメントは、一度仕組みを構築して終わりではありません。ビジネスの状況は変化し続けるため、常に最適なパフォーマンスを発揮できるように、常にPDCAを繰り返してブラッシュアップし続けることが重要です。
-
建設的でポジティブなナレッジを共有する
ナレッジマネジメントの導入にあたっては、より多くの情報を蓄積・共有することが重要となりますが、取り扱う情報の質も重要。情報の鮮度や表現技法にも気を配り、企業の生産性向上に繋がる建設的でポジティブなナレッジを共有するようにしましょう。
-
社内体制を整える
ナレッジマネジメントは、実際に社内で機能してこそパフォーマンスの発揮が可能。ナレッジを充実させるだけでなく、スムーズに運用・活用できるような体制や環境の構築にも注力することが重要です。
蓄積したナレッジを扱いやすくする「チャットボット」
ナレッジマネジメントを実現するには、いかに社内に散在する情報を蓄積・集約・整理して、スムーズに共有・活用できる仕組みを構築するかが重要なポイントとなります。ITツールを活用して情報管理・活用の効率化を図るのが一般的ですが、なかでもおすすめとなるのがチャットボットです。
チャットボットとは、事前に学習させておいた情報をもとに、ユーザーからの問い合わせに対して自動で対応することができる自動会話プログラムのことです。社内のナレッジをFAQとして登録しておくことで、利用者のITリテラシーに関わらずスムーズに必要な情報を提示することができます。社内でのナレッジマネジメントの活性化を図りたい場合においては特におすすめです。

弊社が提供する社内用AIチャットボット「チャットディーラーAI」であれば、充実したテンプレートと学習済みAIを利用することで、短期間で質の高いFAQを整備して運用をスタートすることが可能です。ナレッジマネジメントにチャットボットの活用を検討している方は、ぜひチャットディーラーAIをご検討下さい。
まとめ
ナレッジマネジメントの概要・基礎知識・種類・メリット・導入方法・注意点まで幅広くご紹介してきました。
企業の生産性向上が重要視される現代においては、社内に散在しているナレッジを有効活用することが重要です。ナレッジマネジメントを実現すれば、社員が培ってきたナレッジ・ノウハウを貴重な自社の資産とすることが可能となり、ビジネスの成長・加速に繋げることができるでしょう。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。