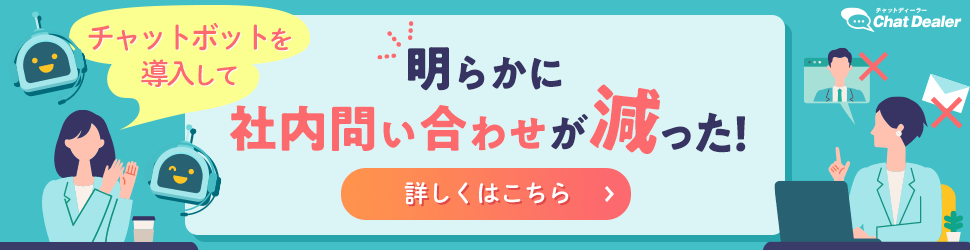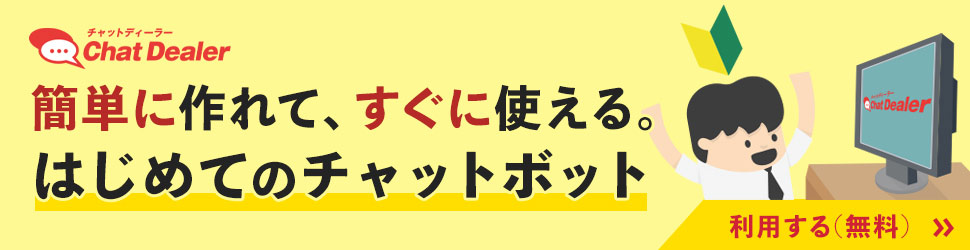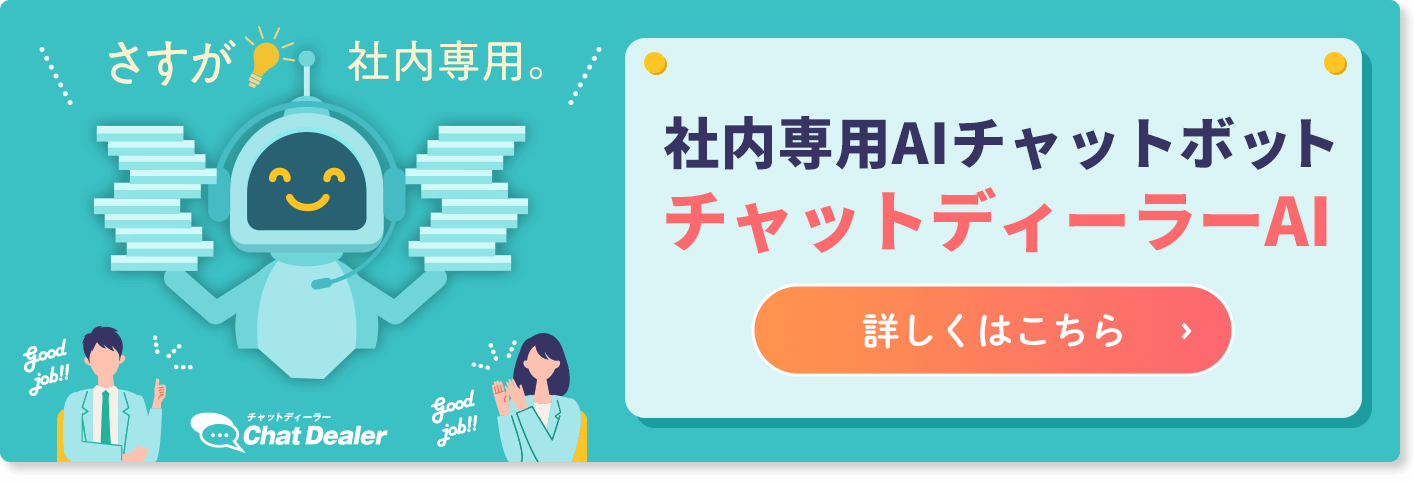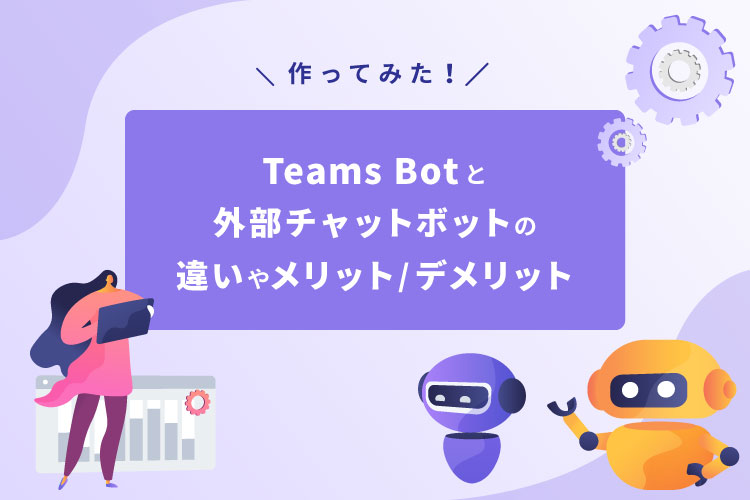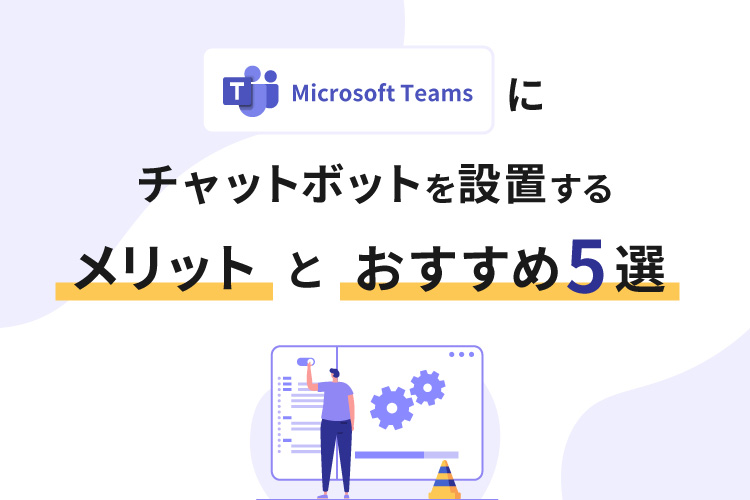チャットボットを外部連携させるメリットとは?選び方やおすすめ4選

カスタマーサポートや社内ヘルプデスク対応に、チャットボットの導入を検討する企業が増えてきました。チャットボットを導入すると、顧客満足度の向上や業務効率化が期待できます。
そんなチャットボットは単体でも役立つツールですが、外部連携させることでさらに機能性や利便性を向上させることが可能です。コストをかけて導入するのであれば、外部連携できるチャットボットを選ぶのがおすすめです。
今回は、チャットボットを外部連携させるメリットと選び方、そしておすすめしたい4つのチャットボットをご紹介します。
チャットボットとは?

チャットボットとは、会話を意味するチャット(chat)とロボット(robot)を組み合わせた造語で、チャット形式で質問への回答を返す自動応答システムを指します。
チャットボットには、「シナリオ型」と「AI型」の2種類があります。
<シナリオ型>
チャット画面に表示された選択肢をユーザーが選ぶと、あらかじめ設定されたシナリオに沿って分岐し、それを繰り返すことで回答へと導くタイプ。テキスト入力による分岐に対応したものもあり、FAQなど一問一答形式の問い合わせ対応に向いています。
<AI型>
ユーザーが自由に入力した文章から質問内容を自動的に判断し、適切な回答を返すタイプ。自然な会話のような形式で質問できるうえ、シナリオ型よりも複雑な質問にも対応できます。AIの学習によって回答精度が上がっていく点もAI型ならではの特徴です。
チャットボットを連携させるメリット

チャットボットを外部連携させるメリットは、以下の4つです。
- 社内問い合わせが削減できる
- 顧客対応データが共有できる
- サブスクリプションサービスと連携できる
順番に解説します。
社内問い合わせが削減できる
ビジネスチャットとチャットボットを連携すれば、社員はさまざまな疑問をその場で解決できるようになるので、社内問い合わせを削減できるのもメリットです。
社内ヘルプデスクや総務など、社内問い合わせを受ける部署には日々さまざまな質問が寄せられます。なかにはマニュアルを見れば分かるようなものも多く含まれ、そのような問い合わせへの対応に時間を取られて自分たちの業務が進まないことに、悩みや不満を抱えているケースも多いでしょう。
チャットボットを外部ツールと連携し、よくある質問に回答できる仕組みを構築すれば、社員は自力で疑問を解消できるようになります。社内問い合わせが減ることにより、問い合わせ対応している部署の業務効率が上がることもメリットです。
顧客対応データが共有できる
チャットボットをSFAやCRMなどの外部ツールと連携すれば、顧客データを共有できるのもメリットです。
顧客から問い合わせがあったときに、過去の対応履歴を確認できるかは重要なポイントです。過去にトラブルがあった顧客には慎重に対応する必要がありますし、お得意様には「〇〇様、いつもありがとうございます」とお声掛けすると喜ばれます。有人対応にエスカレーションするときも、都度お客さまに内容を説明してもらう必要がなくなるのもメリットです。
顧客一人ひとりの情報を踏まえて顧客対応できるようになるため、対応品質はもちろん顧客満足度の向上にもつながります。
サブスクリプションサービスと連携できる
チャットボットのなかには、各種サブスクリプションサービスと連携できるものも少なくありません。
たとえばTeamsやOffice 365などと連携できるチャットボットを導入すれば、社員のスケジュールや会議室の空室管理もチャットボット上でできるようになります。ミーティングのスケジュール調整から会議室の予約までワンストップで終えられるうえ、設定したスケジュールをカレンダーに反映し、メールで通知するのも簡単です。
このように複数のサブスクリプションサービスで管理されている内容を、チャットボットで一元管理すれば、業務効率を上げることができるでしょう。
チャットボットの選び方

チャットボットを選ぶときのポイントは4つあります。
- AIが搭載されているか
- 連携できる外部サービスが豊富か
- サポート体制が充実しているか
- 初期コストとランニングコストを確認する
順番に解説します。
AIが搭載されているか
1章でご説明したとおり、チャットボットにはAIが搭載された「AI型」と非搭載の「シナリオ型」の2種類があります。一般的にはシナリオ型は一問一答など単純な応答に適しており、複雑な質問にはAI型が向いているとされています。
どちらが適切かは、チャットボットの利用目的により異なるため、一概にはいえません。問い合わせ対応にかかる人的リソース削減が目的であるならAI型が適していますが、マニュアルの内容を返すだけであるならシナリオ型でも十分対応が可能です。
AI型とシナリオ型で迷ったときには、まずは導入によりどのような課題を解決したいのかを考えて選ぶことが大切です。
連携できる外部サービスが豊富か
チャットボットを選ぶときには、連携できる外部サービスがどの程度あるのかも必ずチェックしておきましょう。
現在すでに導入している外部サービスがある場合には、連携サービスにそれらが含まれているかを確認しましょう。さらに今後新たなツールを導入するときには、連携できるサービスのなかから選ぶことになります。その際の選択肢を狭めないためには、できるだけ多くのサービスと連携できるチャットボットを選んでおくことが大切です。
サポート体制が充実しているか
チャットボットを導入するときには、充実したサポートを提供しているサービスを選ぶこともポイントです。
チャットボットを導入するときには、通常の業務と並行して準備を進めるのが一般的です。そのため担当者の負担は重くなる傾向があり、いつまでたっても運用を開始できないケースも見られます。さらになんとか運用を始めても、チャットボットを適切に運用するには定期的な見直しが必要です。データの分析と改善を繰り返さなくては、チャットボットの精度は向上していかないためです。
そんなときでもサポートが充実したサービスであれば、担当者が過剰な負担を負うことなく、導入運用が可能です。導入時や導入後にどのようなサポートを受けられるのかは、必ず確認しておきましょう。
初期コストとランニングコストを確認する
チャットボットを導入する際には、多くの場合初期コストとランニングコストが必要となります。初期コストは導入時に支払う費用を指し、ランニングコストは月々の利用料を指します。
初期コストとランニングコストはサービスによって異なり、またシナリオ型かAI型かによっても違います。一般的にはシナリオ型よりもAI型のほうが、初期コストもランニングコストも高いのが特徴です。
チャットボットには高機能なものもありますが、そのぶんかかるコストも高くなります。チャットボットを選ぶときには、自社に必要な機能を洗い出し、必要最低限の機能が備わったタイプを選ぶと費用対効果の高い運用が可能です。
外部連携ができるおすすめのチャットボット4選
ここからは、外部連携できるおすすめのチャットボットを4つご紹介します。
チャットディーラーAI

チャットディーラーAIは、社内利用を想定して開発されたAI型のチャットボットです。400種類以上もの社内用テンプレートと学習済みAIが搭載されているため、導入コストをかけることなくすぐに運用を開始できるのが特徴です。
チャットディーラーAIは、以下のようなプラットフォームと外部連携が可能です。
SharePoint、Googleサイト、WordPress、FAQサイト、kintone、Garoon、サイボウズOffice10、POWER EGG3.0、楽々精算、楽々明細、Microsoft Teams、Google Chat、slack、LINE WORKSなど
このようにチャットディーラーAIは、普段利用している多くの外部ツールと連携できます。ビジネスチャットと連携すれば、導入時に違和感なく使い始められるのがメリットです。わざわざチャットボットを立ち上げる必要がないので、業務効率が下がる心配もありません。
AI型のチャットボットでありながら、低コストで導入できるのもチャットディーラーAIのポイントです。
SupportChabot
SupportChabotは、独自AIによる高精度な回答が強みのチャットボットツールです。クラウドサービスならではの低価格を実現しており、初めてのチャットボットでも導入しやすいといえるでしょう。
チャットボットだけでは解決できない場合、有人対応に切り替えることも可能です。
SupportChabotは以下のサービスとの連携が可能です。
SharePiont、Googleサイト、Kintone、Garoon、desknet’s NEO、Microsoft Teams、Google Chat、Slack、LINE WORKS、Chatwork、LINE、Facebook Messenger など
sinclo
sincloは、専用アプリやソフト不要で、自社サイトにタグを1行追加するだけで導入できる、ノーコード型のチャットボットです。よくある質問や資料請求などはチャットボットで対応を自動化し、高度な問い合わせには有人で対応するなどハイブリッドでの運用も可能です。
sincloでは、以下のようなプラットフォームと連携できます。
Salesforce、Marketo、楽テル、kintone、G Suite、desknets NEO、Google Analytics、slack、Chatwork、WordPress、WIX、EC CUBE、shopify、Google広告 など
導入済みの外部サービスとシームレスに連携すれば、業務効率化を実現できるでしょう。
ObotAI 365Biz
ObotAI 365Bizは、Microsoft 365を快適に活用するための、ユーザーサポートの負担を軽減するために開発されたチャットボットです。AIによる自動応答で、Microsoft 365の社内での活用レベルを標準化できます。
ObotAI 365Bizは、SharePonitと連携して起動が可能。今後Microsoft Teamsとの連携機能実装が予定されています。ビジネスにMicrosoft 365を活用しているものの、操作方法や機能、仕様に関する社内問い合わせが多く寄せられている場合にはおすすめのチャットボットです。
まとめ
チャットボットを外部サービスと連携すると、社員の知識の標準化を図れる、社内問い合わせ数を削減できるなどのメリットがあります。またサービスの内容によっては、顧客情報を参照したりサブスクリプションサービスと連携したりすることで、業務効率や顧客満足度向上にも役立ちます。
チャットボットを導入する際には、自社で導入済みの既存のサービスと連携できるかを確認するのはもちろん、今後の展開も踏まえて連携できる外部サービスが多いものを選ぶことをおすすめします。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。