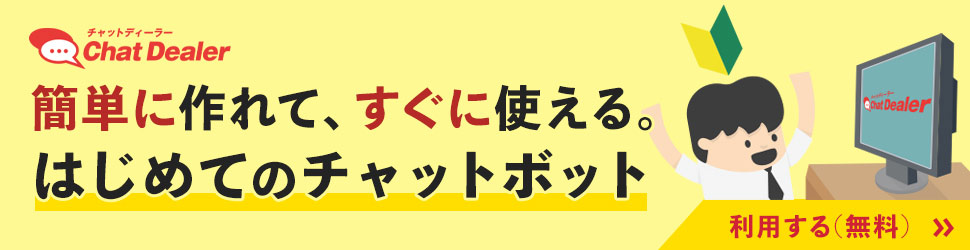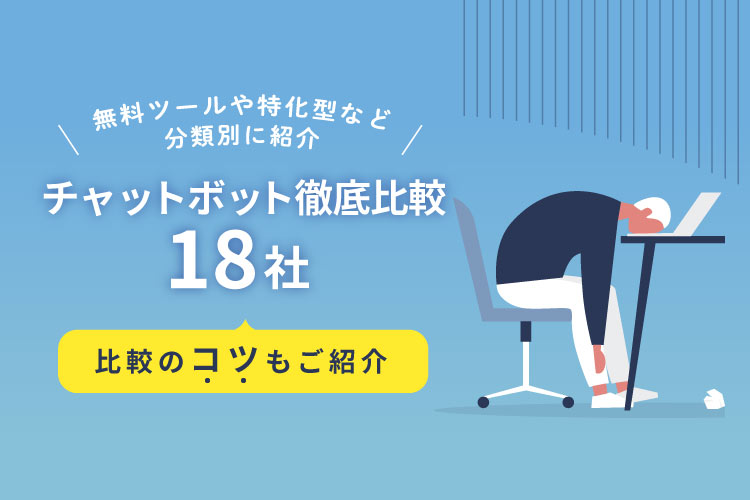チャットボットをリモートワーク企業が導入するメリットと注意点をご紹介!

あなたは今、「働き方改革」を実現する方法としてリモートワーク(テレワーク/在宅勤務)を検討していませんか?
そしてリモートワーク(テレワーク/在宅勤務)を円滑に進めるためのツールとして、チャットボットを導入したいと思ってはいませんか?
- チャットボットは知っているけど、具体的にどういうメリットがあるの?
- リモートワークを実施したいけど、チャットボットを導入しても大丈夫?
このような疑問をおもちかもしれませんね。
単に働き方改革への対応だけでなく、突然起こる社会情勢の変化にも対応するため、事業継続計画(BCP)の一環としてリモートワーク(テレワーク/在宅勤務)を計画している企業もあるでしょう。
今回は、
- チャットボットを顧客向け/社内向けに用意するメリット
- チャットボットの運用方法
- チャットボットサービスの選び方
についてご説明します。
最後までお読みいただければ、リモートワークとチャットボットの相性の良さがお分かりいただけるでしょう。
ぜひ5分ほど割いてご覧ください。
チャットボット導入でカスタマーサポート業務が劇的にラクに

企業業務の中にはカスタマーサポートも含まれますが、リモートワーク・テレワークを実施していてもチャットボットを利用すれば業務負荷が大きく軽減されます。
チャットボットは、既に作成しているFAQページに顧客を素早く誘導します。たとえば、カテゴリから選ぶ、キーワードを入力するというエンドユーザーのアクションに自動的に対応し、顧客の知りたいことを提示できるのです。
よくある質問は、御社でも既にFAQ化しているのではないでしょうか。そのFAQを有効活用してもらうためにも、チャットボット導入はとても有利です。
電話対応ができないとき、既存FAQへの誘導ではこと足りないこともあるでしょう。そのときは、チャットをオペレーターによる有人チャットサポートに切り替えるようにしておけば、リアルタイムで問題解決ができるはずです。
この有人チャットサポートにあたるのは、在宅オペレーターです。できれば、経験値の高いオペレーターに繋げるようにしておくと、問題解決のスピードも高まり顧客満足度を損なうこともないでしょう。
この仕組みを用意しておけば、次のようなメリットが得られます。
【顧客側】
- カンタンな疑問は、自らの手で24時間いつでも解決できる
- いつでも、どこからでも問い合わせできる安心感を得られる
- 問い合わせを行うよりもスピーディーに回答を得ることができる
【企業側】
- よくある質問にはチャットボットによるFAQ誘導だけで済む
- 有人対応は、FAQで解決できないものだけになるので工数が圧倒的に減る
- 営業時間外の問い合わせは、チャット画面の問い合わせフォームで対応できる
- 疑問を解決できる機会が増えカスタマーサポート品質を向上させることができる
- 顧客満足度向上や販売促進に繋がる
顧客側と企業側それぞれのメリットについて、以下に詳しくご紹介していきます。
顧客側のメリット
チャットボット導入による顧客側のメリットは、一言で表現すると問い合わせの利便性が高まることです。チャットボットは時間・場所に関わらずいつでもスピーディーに回答を得ることができるため、従来のフォーム・メール・電話での問い合わせのような煩わしさがありません。
顧客側には、商品・サービスに関する疑問は企業側の都合に依らずすぐにでも解決したい心理があるため、このようなニーズを満たせるチャットボットは顧客側にとっても非常に有益でしょう。企業側がリモートワーク・テレワーク環境下であっても変わらないサポートを受けられる点も、顧客側にとってはメリットとなります。
企業側のメリット
カスタマーサポートを提供する企業側のメリットとしては、業務効率化・対応工数削減・コスト削減・対応品質の向上が挙げられます。
チャットボットはWebサイト等に設置しておけば顧客からの問い合わせに対して24時間365日自動で対応を行ってくれるため、有人で対応しなければならない業務を大幅に削減することができます。工数削減と同時に、対応を行う人的コストも大幅に削減することが可能です。
カスタマーサポートの担当者は、1件の問い合わせに対して余力を持って対応できるようになり、有人でなければできないより重要な業務にリソースを割くことができます。周囲との連携が難しいリモートワーク・テレワーク環境下においては、大きなメリットとなるでしょう。
また、チャットボットと有人対応の併用によりカスタマーサポートの品質向上を図れるため、顧客満足度向上・販売促進といった売上に繋がるメリットを得ることもできます。
チャットボットは社内問い合わせにも活用できる

リモートワーク・テレワークを実施するうえで最も重要なポイントが、オンラインでのコミュニケーションの課題をクリアすることです。コロナ禍によりリモートワーク・テレワークを実践したものの、コミュニケーションの課題を抱えている企業は多くあります。
内閣府が行ったリモートワーク・テレワークに関する調査においても、上位を占めるのはいずれもコミュニケーションに関する課題となっています。
- 社内での気軽な相談・報告が困難:38.4%
- 取引先等とのやりとりが困難:31.6%
- 画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレス:28.2%
出典:内閣府「第2回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
多くの企業ではオンラインでのコミュニケーションにビジネスチャットを導入して課題解決や業務推進に取り組んでいます。しかし、働き方に関するルールを定めてビジネスチャットを利用しても、社内での細かい疑問の解決・気軽な相談等が難しくストレスを抱えるケースは少なくありません。
特に、何かしらの都合で急遽リモートワーク・テレワークを実施しなければならなくなった場合、社内から寄せられる多くの問い合わせへの返答が必要となるでしょう。総務部や人事部は対応に追われ、結果的にパンクしてしまうかもしれません。
このような社内問い合わせ・社内コミュニケーションの課題解決にもチャットボットは有効です。よくある質問・問い合わせにいつでも対応できるチャットボットを用意することで、社員は自宅にいながらにして、いつでも疑問を自己解決することができます。
リモートワーク・テレワーク環境下の社員の、疑問が解決できないことによる業務の停滞やストレスも低減され、また社内問い合わせ対応を行う部署・担当者にも余裕が生まれ、社内全体のコミュニケーションコストの削減や業務効率化を図ることができます。
【リモートワークに関する問い合わせ例】
- 残業はどのように申請すればよいですか
- 在宅勤務中の休憩はどのようにカウントすればよいですか
- 体調を崩したときは、どう対応してもらえますか
- 有給休暇はどうすれば使えますか
リモートワーク・テレワークにチャットボットを活用するときの注意点

では、リモートワーク・テレワークでチャットボットを活用するときにどのような点に注意すべきか、そしてチャットボットの選び方はどうか、というところについてご説明しましょう。
これらの点について理解したうえでチャットボットを選ばなければ、せっかく実施するリモートワーク・テレワークもその効果を最大限に発揮できないかもしれません。
セキュリティ面で強固なものを選ぶ
リモートワーク・テレワークでチャットボットを活用する場合、セキュリティ面で強固なサービスを選ばなければなりません。
社員のパソコンにウイルス対策ソフトをインストールさせなければならないのと同様、リモートワーク・テレワークに必要な各種サービスもセキュリティレベルの高いものを選ぶべきです。
チャットボットも同じで、社員が自宅で使うものは、IPアドレスでアクセスを管理できるものなど、セキュリティレベルが高いものを選びましょう。
この面で管理ができない場合、「誰が・いつログインしたか」が追えなくなり、何かしらの問題が起きるかもしれませんし、実際に問題になったときの原因究明が難しくなります。
顧客用シナリオをしっかり作成
リモートワーク・テレワークでの顧客対応にチャットボットを活用するときは、「シナリオ」をしっかりと練らなければなりません。
シナリオとは、問いに対しての回答スタイルのひとつです。フローチャートにより会話内容を分岐させ、的確にユーザーの求める答え(FAQ)にたどり着くように作りましょう。
顧客は、あなたが思うよりも「セルフサービスでの問題解決」を好みます。ただ、FAQページが複雑すぎると自分で答えを探し出すのに苛立ってしまい、途中であきらめ、それを不満に思うかもしれません。
その問題を解消するために、チャットボットでのシナリオ作り(FAQへの誘導)は重要です。
チャットボットを使い、顧客が自分で答えを見つけられるようになれば、有人チャットに求められる人員も削減できます。これは、リモートワーク・テレワークを実現するにあたり、とても重要な側面です。
社内用シナリオを作成、必要に応じて更新する
リモートワーク・テレワークを実施するにあたり、社内用チャットボットを導入するときも、シナリオ作りに注力して、必要に応じ適宜更新しなければなりません。
特に、何らかの理由で急遽リモートワーク・テレワークに切り替えなければならなくなった場合、問い合わせの数や内容は刻々と変化するはずです。
リモートワーク開始初期は基本的な問い合わせが多いはずですし、ある程度の期間が経過すれば、イレギュラーな質問も増えていくことが想定されるでしょう。
この変化にシナリオがしっかりと対応していなければ、せっかく作成したFAQも活用しづらくなり、結果的にチャットボットも活用されなくなるかもしれません。
そして、社員は最終的に「自宅から担当者に電話をする」という解決方法を選ばざるを得なくなるかもしれないのです。
総務部など、答えを用意しているはずの部署に属する社員のもとに電話が殺到し、収拾がつかなくなることも充分に考えられます。
分析機能をもっているものを選ぶ
チャットボットを選ぶときは、チャットボットが対応した内容、有人チャットで対応した内容を記録し、分析できる機能をもっているかを調べましょう。
リモートワーク・テレワークでない通常業務の場合、顧客対応内容はエクセルやデータベースに蓄積し、問い合わせ内容の傾向や数を分析に活用していることでしょう。ですが、突然全社リモートワーク・テレワーク環境となってしまえば、データの蓄積や分析は難しくなるかもしれません。
この点、データの分析機能をもったチャットボットなら、後処理に悩まずに済みます。
【チャットボットに必要な分析項目】
- シナリオのどこで離脱しているか
- シナリオのどのルートをたどって顧客の求める答えにたどり着いているか
- 顧客は提示した答えに満足しているか
- 訪問者数/受信メッセージ数/送信メッセージ数/有人チャット開始数
顧客にとって、問い合わせをする会社が現在通常業務か、リモートワーク・テレワーク中であるかはわからないものです。全社リモートワーク・テレワークであっても通常業務と同等の環境とし、機会損失を防ぐこともチャットボットの役割といえるでしょう。
スピーディーに運用開始できるものを選ぶ
通常業務かリモートワーク・テレワークであるかを問わず、チャットボットを導入するのであれば、できるだけ早く運用開始が可能なシステムを選ぶことが大事です。
通常業務から本格的にリモートワーク・テレワーク可、とする場合、通常業務中にチャットボット活用(チャットボットから有人チャットへの切り替え)に社員自身が慣れておく必要があります。
また、上でも触れた通り、顧客は思いのほかセルフサービスによる問題解決を好みます。
その点から見ても、チャットボット導入を決めたら、すぐにでも活用できるものであることが好ましいでしょう。24時間・365日、いつでも問い合わせができる環境は、顧客満足度も高まるはずです。
いちはやくセルフサービスを実現できれば、その分機会損失を防ぐことができるのではないでしょうか。
誰もが使いやすいデザインのものを選ぶ
リモートワーク・テレワーク環境下でチャットボットを活用する場合は、利用率を高めるためにもメンバーの誰もが使いやすいデザインのチャットボットを選ぶことがポイントです。扱いにくく分かり難いチャットボットは次第に利用されなくなり、リモートワーク・テレワークの業務効率化・利便性向上に寄与できないためです。
ここで言うデザインとは、チャットボットのビジュアルだけでなく、操作性・利便性に関わるUI(ユーザーインターフェース)も含まれます。
また、使いやすいデザインのチャットボットを選定するだけでなく、導入後は会話デザイン(コピーライティング×UX)にも注力して回答率・解決率を高めていくことも、社内でのチャットボット利用を促進するためには重要です。
提供企業のサポート体制は要チェック
チャットボットは、導入時に設定を行って終わりではなく、運用データを基に継続的なチューニング・改善を施してこそ高いパフォーマンスを発揮することができます。しかし、初めてチャットボットを運用する企業や必要に迫られてリモートワーク・テレワーク実施に踏み切った企業では、自社内でチャットボットのPDCAを繰り返すことが難しい場合もあります。
そこで重要となるのが、多数の事例やノウハウを有したベンダーのサポートを活用することです。手厚いサポートを提供しているベンダーであれば、自社の状況に合わせた導入・運用コンサルティングや施策の代行を任せることができるため、スムーズに成果へ繋げることが可能です。
チャットボットの導入・運用はベンダーのサポート次第で結果が大きく変わるケースも少なくないため、ベンダーのサポート体制・サポート品質については導入前に入念にチェックしておきましょう。
まとめ
今回は、リモートワークにおいてチャットボットが担う役割や導入のメリット、チャットボットの選び方、運用の仕方をご説明しました。
ここまでお読みいただけた方は、チャットボットとリモートワークは相性が良いこと、通常業務であっても効率化に大きく役立ってくれることにお気づきになったことでしょう。
もしもチャットボットに関心を持たれたのなら、ぜひチャットディーラー も検討してみてください。
運用までのリードタイムが短くて済む、各種レポートを確認できる、導入に際しては専任スタッフによるサポートが受けられるという点で、チャットディーラーは御社のお役に立てるはずです。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。