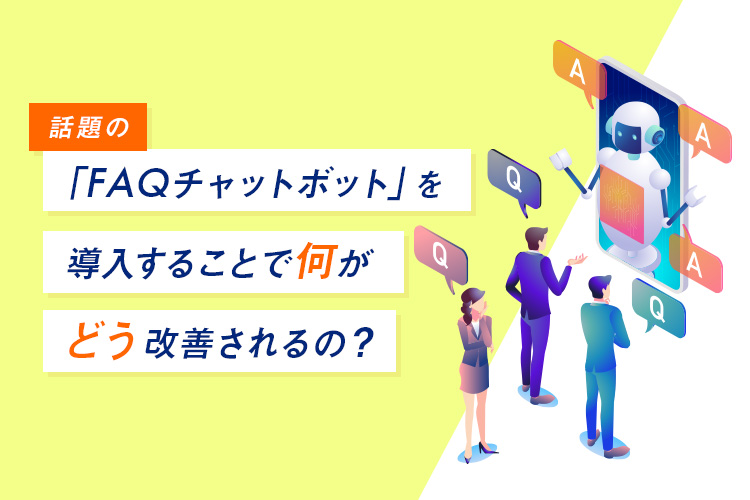【FAQサイトの構築ステップ】より"使われる"ページを作成するためには?

FAQは、「Frequently Asked Questions」の略です。寄せられる頻度の高い質問とその回答のことを指し、これをまとめたものを「FAQサイト」と呼びます。
企業のホームページなどでよく見かけるFAQサイトですが、実はただ設置しただけでは、うまくユーザーに使われないことも多いといえます。サイトの見やすさや検索のしやすさ、的確な回答が得られるかどうかによって、ユーザーの利用率は大きく左右されるのです。
そこで本記事では、ユーザーに使われるFAQサイトを構築するためのステップを解説していきます。また、FAQサイトの利用率を高めるのに有効な「チャットボット」というシステムについてもご紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。
FAQサイト(ページ)構築の必要性

ここでは、なぜFAQサイトを構築することが当たり前になりつつあるのか、その背景を解説します。
人手不足の影響
昨今の日本は、労働人口の減少が深刻化しており、中でもカスタマーサポート業務は人手不足が顕著な領域です。そして、クレーム対応などによって、ストレスがかかりやすい業務の特性から離職率が高く、人材が定着しにくい傾向があります。しかし人手不足が影響し、カスタマーサポートの対応品質が悪化してしまうと、顧客満足度の低下につながる恐れがあるのです。長期的にみると、企業にとって不利益となる重大な課題といえるでしょう。
カスタマーサポートの人手不足の対応策として注目を集めているのが、FAQサイトの構築です。カスタマーサポートによく寄せられる質問を掲載しておくことで、顧客に自己解決を促すことができます。
FAQサイトを構築することで、問い合わせ件数の削減が実現し、注力すべき複雑な問い合わせ対応に集中できるようになります。顧客にとっても、オペレーターにつながるまで待ち時間が発生することも少なくなり、ストレスなく問題を解決できるのです。これは、顧客満足度の改善が期待できるでしょう。
さらに、顧客がスムーズに問題解決が行えることは、深刻なクレームに発展することを未然に防げるため、スタッフの負担を減らして人材の定着率を高める効果も期待できます。
ナレッジの共有
FAQサイトは顧客に対してだけでなく、スタッフ間のナレッジ共有としても活用可能です。人事異動や新入社員の入社時など、あらかじめ業務内容のFAQサイトにまとめておけば、業務の引継ぎやレクチャーがスムーズに行えます。
また、特定の担当者しか対応できないといった業務の属人化が防止できるため、作業効率の改善も見込めるでしょう。さらに、優秀な社員やベテランの社員の技術をFAQサイトで共有しておけば、部署全体のスキル向上が見込めます。
現在、紙媒体のマニュアルやPDF・Word・Excel・PowerPointなどでデータを管理している企業も多いかと思います。しかしこの方法だと、有益なナレッジを掲載できていたとしても、必要な情報の入手に時間と手間がかかります。しかし、FAQサイトで情報を展開すれば、検索機能によって容易に必要な情報にアクセスできるのです。
テレワークの浸透
テレワークの浸透によって、FAQページを構築する必要性がさらに高まっています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、日本国内の企業でもテレワーク化が一気に推進されました。そして、この流れは今後も継続していくでしょう。しかしながら、テレワークは社員同士が離れた場所で業務を遂行するため、何か不明点が発生しても質問がしづらかったり、回答をもらうまでに時間を要したりなど、情報共有に関する問題点を抱えています。
このような課題を解決するために、役立つのがFAQサイトです。社内向けFAQサイトを構築し、ナレッジを共有しておくことで、マニュアルとして活用することができます。困ったときの対応はもちろん、テレワーク下での新人教育などにも役立つでしょう。
FAQサイト(ページ)の構築ステップ

ここでは、実際にFAQサイトを構築するための5つのステップを説明していきます。
FAQサイト(ページ)の担当者を決める
FAQサイトは構築したら終わりではなく、より高い解決率を目指すために、掲載内容見直しや追加といった更新作業が必要となります。しかし、利益に直結する活動ではないため、後回しになりがちな業務だといえるでしょう。
コンテンツの更新作業を後回しにしないためには、FAQサイトを管理する担当者を決めておくと効果的です。担当者を決めておくことで、計画的に更新作業を行うことができます。
また、FAQサイトの回答内容の見直しや、追加項目を検討するタイミングを事前に設定しておいたり、不十分な項目を発見した場合は即時担当者が更新したりするなど、運用のルールも決めておくこともおすすめです。運用ルールは、担当者全員が同一の認識を持って同様の対応を取るための大切な判断基準となります。
いつまでも解決率の低いFAQサイトだと、企業イメージの悪化につながる恐れもあるため、運用ルールに基づいて定期的にPDCAサイクルを回すようにしましょう。
FAQサイト(ページ)構築の目標を決める
FAQサイト構築の目的は、社員や顧客による問題の自己解決の補助、社員や顧客の不安の解消、見込み顧客の育成などが挙げられます。
これらの目的達成のために必要となるのが、数値目標の設定です。社員や顧客の閲覧数、解決率、解約率の改善率、CVの向上率、業務効率の改善率など、より具体的な数値に落とし込みます。
また、数値目標を設定したら、いつまでに達成するか期限も設定しましょう。例えば、期限も設定せずに「解決率を30%向上する」という目標を設定したとします。この状態では、時間軸が抜けてしまっているため、1ヶ月後に5%向上していれば達成できるのか、10%向上させる必要があるのかが判断できず、FAQサイトの見直しもどこから手を付けるべきか分かりづらくなってしまいます。数値目標とセットで期限を設定することで、目標達成に向けて段階的にクリアしていく仕組みを作り、着実にFAQサイトの改善が図れるようにしましょう。
過去の問い合わせ内容を調べる
社員や顧客、見込み顧客などのユーザーの問い合わせ履歴とそれに対する回答を参考にして、FAQサイトに掲載するコンテンツを抽出していきます。
ただし、あらゆる問い合わせに対応しようと情報量を増やし過ぎてしまうと、ユーザーが必要な情報へアクセスしづらくなってしまいます。離脱率が高くなり、使いづらいFAQサイトというイメージがユーザーに定着してしまえば、活用されなくなってしまうでしょう。
ユーザーが使いやすいFAQサイトを構築するには、FAQに掲載する情報の整理が必須です。まずは問い合わせ件数が多く、ユーザーが比較的に自己解決しやすいFAQを抽出します。次に、収集したFAQをカテゴリごとに分類しましょう。提供している商品やサービスのFAQに分類し、次に契約手続きや操作、請求方法などの項目に段階的に分類していきます。
よりスピーディーに情報へアクセス可能にするには、アンカーリンクやタグなどによって、目的情報が掲載されている箇所にジャンプするようにするといいでしょう。
FAQサイト(ページ)を構築する
FAQサイトは、イチから構築することも可能ですが、社内にノウハウを持った社員がいなければ難しく、外注するにしても高額な費用が発生します。そこでおすすめなのがFAQシステムの活用です。
FAQシステムはHTMLの知識がなくても、FAQページの管理と作成ができるツールで、優れた検索機能や分析機能を有しています。また、システムによってはユーザーの検索キーワードや閲覧履歴から効果的なFAQサイトを構築できる機能なども搭載していることもあります。
分析する
FAQサイトを改善するには、ユーザーのサイト上での動きを把握して適切な改善を行う必要があります。ここでは、着目すべきユーザーの行動や指標についてご紹介し、その改善方法も解説していきます。
・検索キーワードに対して回答がヒットしない
ユーザーが必要としている情報を見つけられていない状態を表し、そもそも関連するFAQがない、またはFAQは存在しているもののキーワードが一致せず情報にアクセスできない、といった2パターンの原因が考えられます。新しくページを作成するか、既存のページにキーワードを追加することで対処可能です。
・CTR(クリックスルー率)
CTRは、検索結果の表示回数をクリック率で割ることで算出でき、CTRが低い場合は掲載されている質問の内容が分かりづらい、キーワードに対して欲しい情報が掲載されていないことが考えられます。質問の文章を見直すか、ページの追加かキーワードの追加で対応しましょう。
使われるFAQサイト(ページ)を構築するには?

続いて、実際にユーザーによく利用してもらえるFAQサイトを構築するためのコツをご紹介します。
一体、どのような点に注意すべきなのでしょうか。ポイント毎に、確認していきましょう。
検索性を高める
まずは、解決策を探しているユーザーのことを第一に考えて、検索性を高めることが重要です。検索性を高めるためにはいくつかの方法が考えられますが、大別すると「分類すること」「関連するコンテンツを表示させること」が挙げられます。
以下では、具体的な方法をご説明します。
カテゴリごとに表示する
数多くのFAQをただ並べただけでは、アクセスしてきたユーザーは目的の情報にたどり着けずに迷ってしまう恐れがあります。そうなると、そのユーザーは不明点を抱えたままページから離脱してしまうことになるでしょう。また、「使いにくいサイト」として、ユーザーは再度FAQサイトを活用しなくなってしまう可能性があります。
こうした悪循環を招いてしまわないよう、FAQはカテゴリ別に表示するなど、整理整頓する必要があるのです。
ある銀行サイトのFAQでは、「カテゴリから探す」機能が設けられ、「店舗」「口座開設」「住宅ローン」「保険」など分類されています。また、これらのカテゴリ配下には、さらにサブカテゴリが設けられており、例えば「ATM・店舗」は、「ATM」「国内支店」「インターネット支店」「LINEのATM・店舗検索」などに分類。目的の情報にアクセスしやすい工夫がされています。
このように、FAQごとに細かくカテゴライズすることで、大幅な検索性向上が見込めるのです。
よく検索されるキーワードを表示する
カテゴライズするのとあわせて、「よく検索されるキーワード」を表示しておくと、より利便性が高まります。
先ほど例に挙げたような銀行会社のFAQページでは、よく検索されるキーワードとして「振込」「ATM」「手数料」「暗証番号」などが考えられます。これらのキーワードを、FAQサイトのトップに表示しておくことで、ユーザーはスムーズに該当の情報に辿り着けるようになります。
分かりやすい説明
幅広いユーザーに利用してもらうためには、リテラシーに関係なく、解決できるようなFAQサイトを構築することが理想的です。そのため、FAQサイトでは可能な限り分かりやすい説明を心がけましょう。
多くの場合、そもそもユーザーがその事項に関する詳しい知識がないため、FAQサイトにアクセスしています。そのため、難解な表現や専門用語の過度な使用は極力避け、分かりやすく丁寧な表現を心がけてください。
数字やデータもシンプルにして、必要ならば図や画像を積極的に活用するとさらに効果的でしょう。さらに、重要な部分は太字や下線で目立たせるといった工夫も考えられます。
関連FAQを表示
ユーザーの疑問が曖昧な場合、FAQにアクセスしても、求めていた答えと多少異なると感じられることもあるかもしれません。そのようなユーザーにも満足してもらえるためには、関連するFAQや類似するコンテンツを表示する方法が効果的です。同一カテゴリの質問にアクセスしやすいようにリンクを表示させたり、親和性の高い項目を表示させたりして、より親切な作りになるよう改善を重ねてみましょう。
またどの質問を見ているユーザーが、どのようなページに遷移している割合が多いのか、分析できるようあらかじめ準備しておくことが大切です。むやみやたらに質問を列挙してしまうと、逆にユーザーの検索体験を阻害してしまう可能性もあるので、まずは分析をしっかりと行い、確度の高い関連ページだけを載せるよう厳選してみましょう。
ユーザーからのフィードバック
「問題は解決しましたか?」など、FAQサイト上にアンケートを表示させたり、フォームを設けたりするなどして、ユーザーからのフィードバックを受けることも効果的です。
ユーザーの持つ疑問は多岐にわたっているケースも多く、部分的に解決できたとしても、問題全体が解決できていない可能性もあります。そのようなときに、ちょっとした疑問の受け皿となるフィードバック窓口を作っておくことが大切です。
収集したユーザー声をしっかりと確認し、FAQの内容見直し、さらには製品やサービスの改善に活かしましょう。
FAQサイト(ページ)内に◯◯を設ける?

FAQサイトでユーザーの問題が必ずしも全て解決するとは限りません。そのため、問い合わせフォームへのリンクや問い合わせ用電話番号など他の問い合わせ窓口を記載しておきましょう。
実際に、多くのFAQサイトは、「お探しの情報が無い場合は、こちらからお問い合わせください」と、フォームやメールアドレス、電話番号などが表示されていることが多いです。
注意点としては、問い合わせ項目をあまり目立つ位置に配置しないということです。ユーザーによっては、FAQを自分で検索する労力を省いて、直接電話をかけてしまうかもしれません。これでは、カスタマーサービスの負荷軽減というFAQ設置の目的を阻害してしまいます。
問い合わせ項目の設置にあたっては、適切な導線設計を意識しましょう。
FAQサイト(ページ)にあわせて設置したい「チャットボット」

問い合わせ件数を減らすには、FAQとあわせてチャットボットを導入するのも有効な手段です。ここでは、チャットボットの概要やメリットなどについてご紹介します。
チャットボットとは?
チャットボットは、ユーザーから投げかけられた質問に自動で応答するプログラムのことです。まるで、人が対応しているようにユーザーとやりとりが行われ、企業とユーザーをつなぐ新しいツールとして注目を集めています。
チャットボットは、ルールベース型とAI型の2種類に分けられます。
ルールベース型は、あらかじめ作成したシナリオにしたがって自動で回答するチャットボットです。シナリオは、ユーザーから寄せられる質問を予測して用意しておき、エクセルデータのインポートや、フローチャートによる記述で作成します。シナリオ以外の質問には対応ができないものの、コストがAI型に比べて低く抑えられるため、導入が容易であることが特徴です。
AI型は入力データやユーザーの利用データなどを収集・解析し、統計的に最も適切な回答を導き出します。比較的コストが高く、導入のハードルが高い点があるものの、多様な質問に回答できるメリットがあります。
チャットボットのメリット
ここでは、チャットボットのメリットについて2点説明します。
検索性の向上
FAQサイトのみの場合、カテゴリページを辿ったり、検索機能を活用したりすることで、該当のFAQを探し出す必要があります。しかしチャットボットなら、ボット上で会話を進めることで、求める情報に辿り着くことができるのです。
チャットボットの補助によってFAQサイトの検索性を高めておけば、ある程度FAQの数が増えた場合でも、ユーザーに与える負担を軽減することができるでしょう。
より気軽に利用してもらえる
FAQサイトの見やすさや検索性を高めることで、ユーザーの利用率向上は期待できますが、やはり一定数は「FAQサイトで、わざわざ情報を探すことが面倒だ」と感じるユーザーもいるでしょう。チャットボットは、そのようなユーザーに対しても訴求することができるのです。
近年、スマホの普及により、チャットコミュニケーションが活発化しています。そのため、普段から見慣れたチャット画面がサイトに設置してあれば、「使ってみよう」と感じるユーザーは多いでしょう。
おすすめチャットボット「チャットディーラー」!
チャットディーラーは、ユーザー対応と社内FAQの両方で活用できる汎用性の高い、シナリオ型チャットボットです。1契約で5サイトまで設置できるため、自社サイトやランディングページ、FAQサイト、各種Webシステムなどあらゆる場所で活用できます。
また、事前に用意しておいたシナリオをもとに自動回答する無人チャットと、リアルタイムでオペレーターが対応する有人チャットの2種類の運用が可能で、2つを組み合わせて運用することもできます。さらに、選択肢が選ばれた件数や離脱数などのレポートや、アンケート機能も有しているため、シナリオ内容のブラッシュアップも簡単に行うことができるのです。
運用に不安のある方も、チャットディーラーでは、初期設定から運用開始後のPDCAサイクルまでサポートする体制が整っているため、安心して利用を開始できるでしょう。
チャットディーラーについて詳しく知りたい方は、下記リンクより資料請求ができるので、お気軽にお申込みください。
まとめ
この記事では、FAQサイト構築の必要性について説明し、構築のステップとポイントを解説しました。構築する場合は、本コラムでご紹介したポイントなどを参考に、「ユーザーに使われるFAQサイト」を目指してみてください。
また、今回ご紹介したように、FAQサイトとチャットボットを組み合わせて活用することで、問い合わせ件数のさらなる低減が図れます。ぜひ、チャットボットの導入もあわせてご検討ください。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。