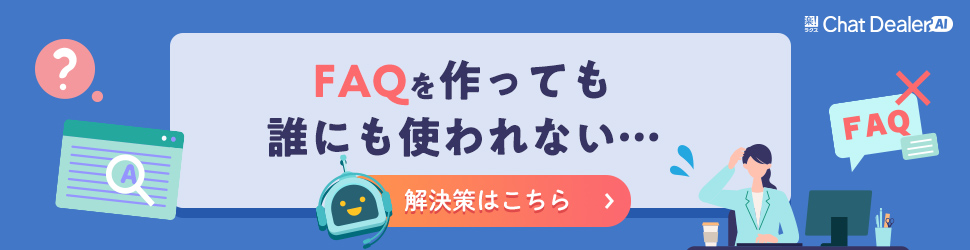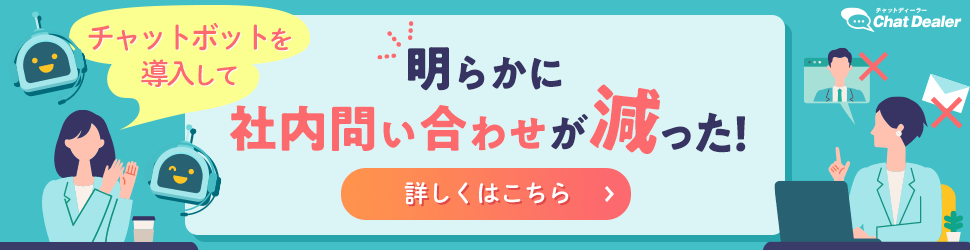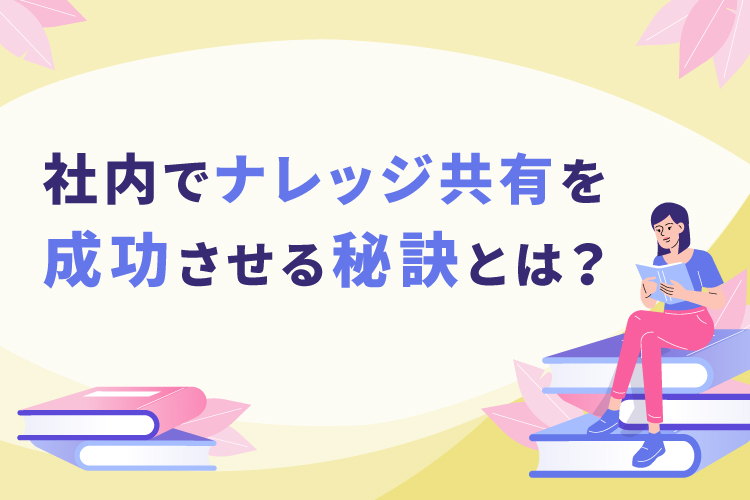従業員エクスペリエンスとは?向上のメリットと具体的な施策例

生産性の向上や離職防止に欠かせない従業員エクスペリエンス。働き方の多様性が広まり、転職や副業が当たり前になりつつある現代において、企業が優秀な人材を確保するためには従業員エクスペリエンスを高める必要があります。
本記事では、従業員エクスペリエンスの概要から注目される背景、エクスペリエンス向上によるメリット、施策のポイントなどを解説します。従業員エクスペリエンス向上に役立つツール「チャットディーラーAI」もあわせて紹介しますので、ぜひ実施の参考にしてください。
従業員エクスペリエンスとは

従業員エクスペリエンスは、英語ではEmployee Experienceといい、通称「EX」とも呼ばれています。これは従業員が企業内で働くことで得られるすべての体験や経験価値のことを指しており、特に満足度や幸福度を高めるような体験を指しています。
体験そのものだけではなく、従業員が経験を通して考えたことや感じたことなどの心理的・感覚的な要素も含まれます。たとえば、個人のスキルアップはもちろん、健康状態や満足度、福利厚生、報酬などの項目も従業員エクスペリエンスです。
従業員エンゲージメントとの違い
従業員エクスペリエンスと類似したワードには、従業員エンゲージメントがあります。どちらも従業員に関するワードとなりますが、意味は全く異なるため、違いを理解しておく必要があります。
-
従業員エクスペリエンス
従業員が会社で働くことで得られる体験全般を指す。満足度・エンゲージメントを高めることを目的とした概念。
-
従業員エンゲージメント
会社・仕事・人間関係等に対してどの程度満足しているかを指す指標。
広義では、従業員エンゲージメントは従業員エクスペリエンスに包括されると考えることもできます。
従業員エクスペリエンスの5段階
従業員エクスペリエンスは、人材が求人広告等で企業を認知してから退職するまでのライフサイクルに合わせて、5つの段階に分けることができます。
ここでは、従業員エクスペリエンスの各段階について解説します。
-
人材募集段階
人材と企業が最初に接触するところから採用に至るまでの段階。採用に要した時間・コスト・承諾率・採用率・人材の質が検討すべきポイント。
白紙の状態の人材にポジティブな従業員エクスペリエンスを持たせる良い機会でもある。 -
オンボーディング段階
採用した人材が企業の業務や利用するシステム等に慣れるための立ち上げ段階。入社直後の人材の特性や状況を把握して、高い熱量を自社のブランドや自社の業務への意欲へと変換することがポイント。
-
能力開発段階
人材が業務に必要な能力を獲得して独り立ちを始める段階。キャリアパスの構築や専門的スキルの獲得を始める段階であるため、自己研鑽を継続するように奨励することがポイント。モチベーションを維持し続けるために、ネガティブな洗い出しやケアを行っておくことも重要。
-
定着促進段階
従業員が専門性を身に付け自身のポジションを確立してくる段階。従業員ライフサイクルの定着段階であるため、より長く自社で活躍してもらうために、意義ややりがいを持たせることが重要なポイント。価値のあるフィードバックを得られるため、積極的なコミュニケーションを図ることが重要。
-
退職段階
従業員のエクスペリエンスが終了する段階。そのまま人材のライフサイクルの終了を見送るのではなく、フィードバックを得て退職要因の解消や離職率低下に役立てることがポイント。企業の今後を考えるうえで重要な段階であるため、機会を逃さず意見を聞き出すことが重要。
従業員エクスペリエンスが注目される背景
近年、従業員エクスペリエンスが注目され始めた背景を紹介します。背景を知ることで、従業員エクスペリエンスがなぜ必要とされているかを把握し、企業内での改善に役立てましょう。
人材獲得競争の激化
現在の日本は、少子高齢化社会の影響で労働人口が減少しており、企業が優秀な人材を確保することが難しくなってきています。人材を確保できなければ、今いる従業員の業務負担が大きくなってしまい、業務負担が増え残業や休日出勤が発生すれば離職率の上昇を招いてしまいます。離職率が上がれば、さらにひとりひとりの労働環境が悪化する悪循環に陥ってしまうでしょう。
このような状況を防ぐためにも、従業員エクスペリエンスを向上させ、雇用数を確保するとともに、職場環境の整備によって従業員の定着を図る必要があります。
また、戦後の日本では長らく、定年まで同じ会社で働き続ける終身雇用制度が一般的でしたが、現在では終身雇用制度が成り立たなくなってきており、転職を繰り返す人も増えています。条件のよい企業への優秀な従業員の流出を防ぐためにも、従業員エクスペリエンスの向上は大切です。
働き方改革の浸透
近年、日本では働き方改革が推進され、その中で従業員エクスペリエンスも注目され始めました。働き方改革では、少子高齢化問題や働き方の多様性化に対応し、従業員の働きやすい環境づくりが求められています。
従業員が働きやすい環境にするために欠かせないのが生産性の向上です。労働人口が減少する中で従業員の負担を増やさないためにデジタル技術やシステム、ツールを利用して業務の効率化を図る企業が増えています。
このように働き方改革に適した環境づくりは従業員エクスペリエンスの向上にもつながるため、あわせて注目を集めています。また、働き方改革では業務効率の面だけではなく、職場環境や福利厚生などを整備し、従業員エクスペリエンスを向上させることで従業員が働きがいを感じ、結果的に生産性向上につなげる狙いもあるでしょう。
企業の口コミ・評判の可視化
近年、IT技術が急速に発達したことがきっかけで、スマホひとつあればなんでも調べられる時代になりました。それは企業の情報も同様です。企業の情報や口コミ・評判を掲載するサイトが増えたことで、転職活動でもよく利用されるようになりました。
口コミサイトに記載されている職場の雰囲気や、実際の残業状況を参考にする転職者も多いことでしょう。求職情報でいくら条件のよい内容を掲載していても、実際には労働環境が悪くて福利厚生を利用できないといったブラック企業であれば、口コミサイトにそのような実態が書かれてしまうこともあります。
口コミサイトのリアルな悪評を見た転職者は、いくら求人サイトで好条件が掲載されていても、応募をためらい他の企業を探すのではないでしょうか。このような機会損失を避けるためにも、従業員エクスペリエンスを向上させ、よい評判が掲載されるよう努めることが大切です。
従業員エクスペリエンス向上のメリット

従業員エクスペリエンスの向上は、企業が成長し続けていくためには欠かせません。ここでは、具体的なメリットを2つ紹介します。このメリットを目的に、従業員エクスペリエンスの向上を図ることを理解しておきましょう。
人材の定着率アップ
従業員エクスペリエンスの向上による企業のメリットのひとつとして、人材の定着率アップがあります。これまで、終身雇用制度によりあった帰属意識が転職や副業が一般的になりつつある現在では薄まってきています。帰属意識が低いということは、人材の流出が頻繁に起こる可能性があるでしょう。
労働環境や給与、福利厚生など企業の環境を整備することで従業員エクスペリエンスが向上できれば、企業に対する不満も減少し、人材が定着しやすくなると考えられます。離職率を下げるためには、従業員が働きやすい環境づくりが大切です。
従業員エクスペリエンスの向上は人材の定着率をアップさせ、さらに人材が確保できることでひとりひとりの労働負担も減るという、好循環を作れるでしょう。
収益性の向上
従業員エクスペリエンスが向上すれば、従業員の働きがいやモチベーションアップにもつながり、事業の生産性向上をもたらすでしょう。
たとえば、デジタル技術を活用したシステムを導入すると、時間がかかる単純作業をツールに任せられます。従業員はこれまで単純作業にかけていた時間を別のコア業務にあてることが可能です。
コア業務に集中できれば従業員もやりがいを感じられ、従業員エクスペリエンスの向上にもつながるでしょう。また、企業としてもコア業務に割く時間が増えれば、事業の成長が期待でき、収益性の向上につなげられる可能性があります。
他にも従業員エクスペリエンスを向上させる手段には、育休制度や時短勤務、テレワーク、家賃補助などの制度もあります。これらにより従業員の労働環境が改善されれば、生産性が向上し、収益性アップにもつながるでしょう。
従業員エクスペリエンスを向上させるための施策例

従業員エクスペリエンスを向上させて、人材の定着や生産性の向上を図るためにどのような取り組みが必要なのでしょうか。ここではいくつか施策例を紹介します。離職率が高い企業や生産性に伸び悩んでいる企業はぜひ参考にしてください。
アンケートを通じて従業員の声を聞く
働く環境を整えて従業員エクスペリエンスを向上させるためには、実際に従業員が現場で感じていることを把握することが大切です。現状を把握しないまま従業員エクスペリエンス向上に向けて職場環境を整備しようとしても、何に取り組めばよいかわかりません。アンケートを利用して、現場で働く従業員の意見を聞くことで、課題が見えてくるでしょう。
たとえば、生産性の意識が低い職場環境であれば、従業員一人一人の意識を変える改革が必要です。残業をして長時間仕事することが当たり前になってしまっている場合は、ノー残業デイを作ることや、上司が率先して定時に帰宅するなどの意識改革が必要でしょう。
また、業務がプロセス化・マニュアル化されていない場合、特定の従業員がいないと業務が進められません。このような属人的な業務体制では生産性が停滞してしまうでしょう。システムを導入して情報を共有できる体制をつくれば、業務の属人化を防げます。多くの従業員が同じレベルで業務をこなせるようになれば生産性も向上するでしょう。
このように、アンケートは具体的な現場の悩みを知るために欠かせない手段です。
ストレスチェックを実施する
従業員エクスペリエンスを評価する方法のひとつにストレスチェックがあります。従業員エクスペリエンスは体験だけではなく、健康状態や精神状態も含まれています。ストレスチェックを行うことで、従業員の健康・精神状態を把握しましょう。
ストレスチェックは、従業員が職場環境や業務に感じている不満や悩みを知るきっかけにできます。高ストレス者に対しては速やかに面接指導を実施しましょう。ストレス状態の悪化は健康状態の悪化や離職につながる恐れがあります。まずは個人の不満や課題解決が重要です。そのうえで、職場全体にどのような問題が発生しているか把握する必要があります。
高ストレス者に個別対応しただけで職場環境の改善をしなければ、また同じように高ストレス者が発生し、従業員エクスペリエンスの向上は見込めません。ストレスチェックとあわせて労働環境の見直しも必ず行いましょう。
福利厚生を改善する
福利厚生を改善し、さまざまなライフスタイルの人が働きやすい環境をつくることで、従業員エクスペリエンスの向上が見込めます。働き方の多様化が進む中で必要な福利厚生の例を挙げていきます。
- リモートワーク
- 時短勤務
- 時差通勤
- ローテーション勤務
- フレックスタイム制
- オンライン会議
- コワーキングスペース利用
近年、上記のような場所や時間に捕らわれない働き方が推進されています。出産や育児、介護などのライフスタイルの変化があっても働き続けられる職場環境をつくることは、従業員エクスペリエンスの向上につながるでしょう。
また、働き方の多様化を推進することは生産性の向上にもつながります。リモートワークや時短勤務を採用することで、スキルや能力があっても家庭の事情で自宅を離れることが難しかったり、限られた時間内でしか働けなかったりする人も雇用が可能となり、人材確保の選択肢が広げられるでしょう。新たな人材が活躍すれば事業の成長速度が上がり、従業員エクスペリエンスの向上につながるかもしれません。
評価制度を見直す
人事評価制度を見直し、従業員のスキルや能力、業務量などを正当に評価できる仕組みをつくれば、従業員のモチベーションやエクスペリエンスの向上につながるでしょう。また、適切な評価が可能になれば従業員一人一人に合った配置転換が可能となり、能力を活かした業務が行えます。適材適所の配置により生産性の向上も期待できるでしょう。
自分のスキルに合った仕事をこなせれば従業員もやりがいを感じられ、企業にとっても働き手にとってもメリットがあるといえるでしょう。人事評価を見直すためには組織全体の理念やビジョン・価値観を明確にしておく必要があります。企業が求める人物像をはっきりさせ、評価の基準にするとよいでしょう。
職場環境改善のために投資する
従業員エクスペリエンスを向上させるためには、職場環境の改善が欠かせません。まずは、従業員が抱える仕事量や作業時間、業務に必要なスキルを把握しましょう。そのうえで、必要なツールやシステムを導入します。現場で働く従業員の需要に合わせた設備投資を行うことで、労働負担を大幅に軽減できるでしょう。
アナログ業務が多いと単純作業に時間を取られてしまいますが、デジタル化を進めて作業時間の短縮やペーパーレスによるコスト削減が実現すれば、従業員もやりがいのある仕事に集中でき、従業員エクスペリエンスが向上するでしょう。
最近では以下のようなITツールが登場し業務効率化に役立てられています。
- 社内コミュニケーション用のチャットツール
- 業務状況を可視化するプロジェクト管理ツール
- 社内問い合わせ対応を効率化するチャットボットツール
従業員エクスペリエンス向上の際のポイント
従業員エクスペリエンスを向上させるには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。以下にご紹介していますので、これから従業員エクスペリエンス向上の施策に取り組む方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
Employee Journey Mapを作成する
Employee Journey Mapとは、従業員の入社から退社までの一連のライフサイクルを図に描いたマップのことです。顧客体験をマップに描くカスタマージャーニーマップの従業員版と考えると分かりやすいでしょう。
マップの作成を行うことで、従業員と企業との接点・経験・体験などが可視化できるため、従業員エクスペリエンスを向上させるための的確な施策を行うことが可能となります。
Employee Journey Mapは、従業員エクスペリエンスの向上や改善を図る際の基本となるため、施策を実施するのであればまずはこちらの作成から着手するようにしましょう。
Radical Participationを意識する
Radical Participationとは、従業員が組織に貢献するために、自身が所属する組織作りに積極的・能動的・活動的に参加していくことを指すワードです。
経営陣・上層部のみが従業員エクスペリエンスの向上を図る施策を実施しても、当事者である従業員の意見や意図が反映されていなければ、現状にそぐわない組織や偏った組織となってしまうケースが多くあります。このような状況では、効果的に従業員エクスペリエンスを向上させていくことは難しいでしょう。
Radical Participationを意識して従業員参画型の組織作りを行うことで、効果的に従業員エクスペリエンスの向上を目指せる組織の構築が期待できます。
従業員目線で成長プロセスを考える
従業員エクスペリエンス向上の施策は、企業側目線で検討されている傾向にあります。経営戦略の一環として検討される施策であるためある程度仕方のない部分もありますが、企業側目線に偏った施策を無理に従業員に適用しても、表面的な施策に終始してしまい思うような成果を得られないケースが多くあります。
そこで重要となるポイントが、従業員目線を重視して施策を検討することです。従業員についての理解を深め、伴走のような形で成長プロセスを考えることで、共感やコミットメントを獲得して効果的な施策を実施していくことが可能となります。
積極的にミーティング・面談・対話の機会を設け、従業員を主体とした従業員エクスペリエンスを実施していくようにしましょう。
最初は小規模な施策から
従業員エクスペリエンスを向上させるための施策は、特定の人材だけでなく企業で働く多くの人材に対して実施する大規模かつ長期的な施策です。しかし、できるだけ短期間で大きな成果を得たいと最初から大々的な施策を実施してしまうと、問題が生じた際の対処が難しく原因の特定も困難となります。
そのため、最初は小規模な施策から実施してブラッシュアップを繰り返し、徐々に規模を拡大していく方法が得策です。人材に対して実施する施策は地道な積み重ねが重要であるため、急がずに着実に歩を進めていくことが良い結果に繋がるポイントとなります。
従業員エクスペリエンスの向上に「チャットディーラーAI」

さきほど紹介したITツールの中でも、社内問い合わせ対応を効率化する「チャットボットツール」の活用は特におすすめです。
たとえば、総務部や人事部へ申請する書類で、書き方や書類の格納場所がわからないという問題は業務でもよくあることです。このような場面で、いちいち関係部署へ問い合わせて確認するのではなく、チャットボットを利用すればスピーディに解決できます。
質問側にとっては回答までのスピードが上がりますし、総務や人事など回答側は問い合わせ対応の負担軽減につながります。双方がより自分自身の業務に集中できるため、従業員エクスペリエンスの向上につながるでしょう。
社内向けチャットボットを導入するなら「チャットディーラーAI」が最適です。チャットディーラーAIは、導入の手軽さとサポートの手厚さで人気のチャットボットです。
AIによる高精度な自動対応はもちろん、自動対応で解決できなかった場合も専用のフォームから問い合わせることで有人対応へとスムーズに引き継がれます。フォームからの送信内容は問い合わせ管理機能によって効率的に管理できるため、社内問い合わせ対応全般の効率アップが可能になります。
問い合わせ対応部署の負担が大きい場合や、社内問い合わせの利便性が低い場合は、ぜひチャットディーラーAIの利用を検討してみてください。
まとめ
本記事では、従業員エクスペリエンスの向上が推進されている背景や、メリット、施策例を紹介しました。従業員エクスペリエンスの向上は、従業員にとっても企業にとってもメリットの多い取り組みです。
企業が成長し続けていくためにも、デジタル技術を積極的に活用して従業員エクスペリエンスの向上に努めましょう。
-
この記事を書いた人
ボットマガジン編集部
ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。